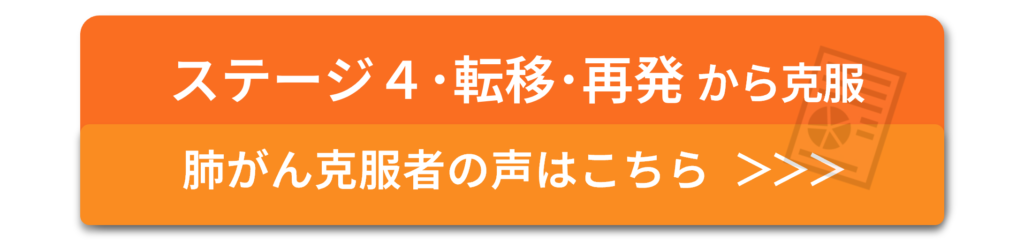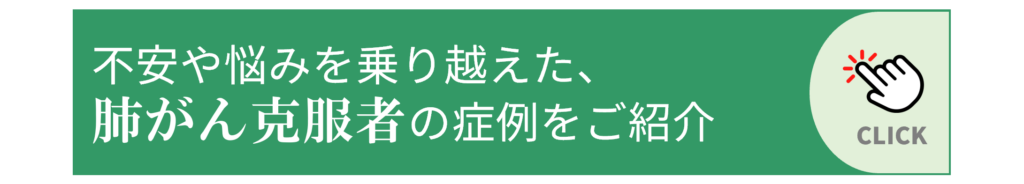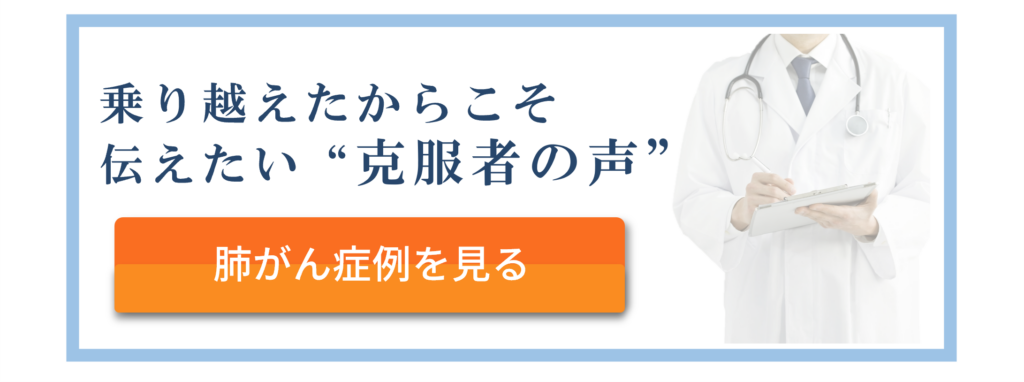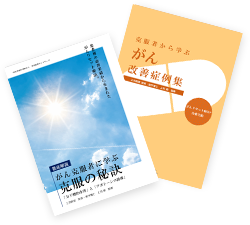- 2025.06.03
- 肺がん
生存率に差が出る!ステージ4肺がんの症状と対策
「肺がんは、日本で最も多くの人が亡くなるがんの一つです」
テレビやインターネットで、このような言葉を耳にしたことがあるかもしれません。
特に、肺がんと診断されたご本人や、そのご家族にとっては、不安を感じる言葉ではないでしょうか。
肺がんは、特に女性よりも男性に多く、50歳ごろから発症する方が増え始めます。そして、男女ともに80代での発症が多く見られるという統計もあります。
「ステージ4」と聞くと、とても厳しい状況だと思われるかもしれません。実際に、他のステージと比較すると、治療の経過や5年生存率に大きな差があることが、データからわかっています。
しかし、不安に駆られる必要はありません。これはあくまで統計上の話であり、一人ひとりの身体の状態や治療法、そして何よりも「これから」の過ごし方によって、未来は変わっていきます。
ご自身の病状や治療について知ることは、決して怖いことではありません。むしろ、しっかりと向き合うことで、ご家族とともに安心して治療を進めていくための第一歩になります。
現在、肺がんの治療法は日々進歩しています。標準的な治療法である抗がん剤を用いた治療に加え、分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬といった、新しい治療薬も次々と開発されています。
これらの治療法は、患者さんの身体への負担を減らし、より長い期間、生活の質を保ちながら治療を続けられることを目指しています。治療方針を決める際には、医師が様々な指標を総合的に考慮します。具体的には、がんがどのくらいの範囲に広がっているか、そして「組織型」と呼ばれるがんの種類、さらには患者さんご自身の全身状態などです。
また、国立がん研究センターが運営する「がん情報サービス」といった公的なサイトでは、がんの統計データや治療法、そして病院の情報などを調べることもできます。
こうした情報を活用することで、ご自身に合った治療法を見つける手助けになります。
このコラムでは、肺がんの診断を受けた方やご家族が、少しでも安心して前向きに治療と向き合えるよう、ステージ4肺がんに関する具体的な情報をお届けします。特に、ステージ4肺がんの症状や代表的な治療法について、分かりやすくご説明します。参考になれば幸いです。
1.肺がんのステージ4とは?
ステージ4肺がんは、肺がんの最も進行した段階であり、転移や隣接臓器への広がりが見られます。治療は主に症状の緩和を目的とし、根治が難しい状態です。
このステージでは、がん細胞がリンパ節を越えて他の臓器へと広がり、転移が発生しています。主な転移先は肝臓、骨、脳、副腎などで、症状は転移先の臓器や病状によって異なります。
ステージ4肺がんに対する治療方法として、化学療法、分子標的療法、免疫療法などがありますが、全体の生存率は低く、治療後の再発も多いです。
治療選択は患者の病状や体力、副作用のリスクと効果を考慮し、医師と相談して決めることが重要です。
ステージ4肺がんの患者さんや家族は、緩和ケアやサポートが必要な場合が多くなります。そのため、病院や地域のサポートサービスを利用することも大切です。

肺がんの分類とステージについて
肺がんは、進行の程度によってステージ1から4に分類されます。これは、がんの広がりや、リンパ節、そして他の臓器への転移の有無によって決まるものです。
・ステージ1
肺の中にだけがんがある、比較的早い段階です。
・ステージ2
がんが肺の中で少し広がり、リンパ節への転移も限定的です。
・ステージ3
肺やリンパ節にがんが広がっていて、周りの組織にも及んでいる状態です。
・ステージ4
がんができた場所(原発巣)から離れた臓器にまで転移している、最も進行した状態です。
ステージが初期の段階であるほど、外科手術や放射線治療、抗がん剤治療といった、がんを直接取り除く治療が選択肢となりやすく、一般的に5年生存率も高くなります。しかし、ステージが進むにつれて治療の選択肢が限られていき、死亡率も高くなる傾向があります。
早期にがんを見つけるためには、年齢や喫煙歴など、肺がんのリスクが高いとされている方は、定期的に受診して検査を受けることが重要です。
また、肺がんは、がん細胞のタイプによって、大きく二つの種類に分けられます。
・非小細胞性肺がん
肺癌全体の割合でいうと、約8割を占めています。進行が比較的ゆっくりで、術後の治療法も幅広く選択できます。
手術、放射線療法、化学療法、分子標的治療、免疫療法などが通常の治療法として挙げられます。
・小細胞性肺がん
約2割を占めます。進行が速いため、主に抗がん剤を用いた治療が中心となります。
非小細胞性肺がんは、さらに「腺がん」「扁平上皮がん」「大細胞がん」の3つに細かく分類され、それぞれに異なる治療法が選ばれたり、経過にも違いが出てきます。これらの細胞のタイプを正確に知ることは、最適な治療法を見つける上で欠かせません。
ステージ4肺がんの症状と転移について
ステージ4の肺がんでは、がんが肺から離れたリンパ節や、他の臓器へ転移している状態です。そのため、さまざまな症状が現れます。
例えば、慢性的な咳、痰に血が混じる、息切れ、胸の痛み、体重の減少、声のかすれなどが挙げられます。
特に注意が必要なのは、がんがどこに転移したかによって、それぞれに特有の症状が出てくることです。
・脳
脳に転移した場合、頭痛、めまい、視力低下、体のバランスが取りにくくなる、意識がもうろうとするなどの症状が出ることがあります。
・骨
骨に転移すると、骨の痛みや骨折の原因となることがあります。これは、日常生活を送る上で大きな影響を与えます。
・肝臓
肝臓に転移すると、肝臓の働きが悪くなり、皮膚や白目が黄色くなる(黄疸)などの症状が見られることがあります。
・副腎
副腎への転移は、自覚症状がほとんどない場合が多いです。
ステージ4肺がんの診断には、まず、X線やCT、MRI、PETスキャンといった画像検査が行われます。これらの検査で、がんの位置、大きさ、そしてどこに転移しているかを詳しく調べます。
さらに、気管支鏡検査や針を刺して組織の一部を採取する検査も行われます。採取した細胞や組織を調べることで、がん細胞の有無や種類が正確にわかります。
治療は、患者さんお一人おひとりの体の状態や、がんの種類、転移している場所によって異なります。一般的には、手術は難しいため、化学療法や免疫療法、分子標的療法などが中心となります。つらい症状を和らげるための緩和ケアも、大切な治療の一つです。
2.ステージ4の余命と生存率
ステージ4肺がん患者の余命や生存率は、個人差が大きく、がんの種類や治療法によっても変わります。統計的には、ステージ4肺がん患者の5年生存率は、約10%以下とされています。
ただし、近年の医療技術の進歩や免疫療法、分子標的治療の開発により、一部の患者の生存期間が延びることもあります。また、緩和ケアを含む総合的な治療によって、患者のQOL(生活の質)の向上や合併症の軽減が図られます。
ステージ4肺がん患者の予後を左右する要素には、がんの種類や分類、治療応答性、患者の年齢や一般的な健康状態、合併症の有無などがあります。適切な治療法の選択や医療チームとの連携が重要であり、患者や家族にとっての支援体制も大切です。

平均余命と生存率の現状
肺がんは、男性・女性問わず全てのがんの中で最も死亡率が高い病気であり、その治療の成功が患者の生存率に大きく影響します。生存率は、肺がんのステージや病状、治療法によって異なります。早期の段階であるステージ1や2の場合、手術や放射線治療によって治癒が可能であり、平均余命は10年以上となることが一般的です。しかし、進行が早く転移してしまったステージ3や4では、状況が一変し治療の効果が限定的となります。
放射線治療や化学療法を併用することで、一部の患者において生存率の向上が期待できますが、平均余命は2年程度と言われています。このため、早期発見が極めて重要であり、定期的な検査や症状に対する注意が求められます。最近では、免疫療法や標的治療が開発され、一部の患者に対して生存期間の延長が期待できる状況にあります。また、肺がんの原因となる遺伝子や分子標的の研究が進んでおり、将来的には個別化された治療が展開される可能性があります。
年代別の余命と生存率の違い
年代別の余命や生存率は、がんのステージや治療法だけでなく、患者の年齢や一般的な健康状態、免疫力にも関係しています。若い患者の場合、体力があり治療に耐えられる可能性が高いため、生存率が向上し、平均余命もより長くなります。一方、高齢者においては、免疫力や体力が低下していることから、治療の効果が限定的になりがちです。
また、高齢者の場合、他の疾患や持病が影響して生存率や平均余命が短くなることもあります。緩和ケアを含む治療方法の選択肢が限定されることが多く、病院や専門家と相談しながら適切な治療法を選択することが重要です。年代別のデータを見ると、早期発見と治療によって生存率が向上する傾向が明確にあり、症状や検査結果に応じて適切な治療法が選択されることが求められます。
免疫療法や標的治療で変わる生存率
近年の医療技術の進歩により、免疫療法や標的治療が肺がん治療の選択肢に加わり、それによって生存率が向上することが確認されています。免疫療法は、がん細胞を攻撃する免疫力を高めることで、がんの進行を抑制する効果が期待されます。標的治療は、がん細胞の成長や転移を促す遺伝子や分子に対して効果を発揮し、正常な細胞に対する副作用が少ないことが特徴です。
免疫療法や標的治療は、特定の遺伝子変異を持つ患者に対して効果を発揮することが多く、進行がんや転移がんの患者に対して生存率の改善が見込まれます。ただし、免疫療法や標的治療が必ずしも全ての患者に効果があるわけではなく、患者ごとの遺伝子や腫瘍の状態に応じて適切な治療法を選択する必要があります。免疫療法や標的治療が普及することで、今後さらに多くの患者がこの新たな治療法の恩恵を受け、生存率が向上することが期待されます。
3.治療法と選択のポイント
ステージ4肺がんは、がん細胞が肺以外の臓器にも広がっており、治療が困難な状態です。しかし、現代医療の進歩により、いくつかの治療法があります。
まず、化学療法ですが、薬物によりがん細胞の増殖を抑制します。特に標的治療薬は、がんの遺伝子に作用して効果が期待されます。
次に、放射線療法です。これは、高エネルギーの放射線をがんに照射して細胞を破壊し、腫瘍の縮小を目指します。
また、免疫療法も注目されています。自分の免疫力を利用してがん細胞を攻撃し、転移や再発を防ぐ効果があるとされています。
治療法を選択する際のポイントは、患者の年齢、体力、症状、がんの種類や進行具合によって異なります。また、治療法による副作用や負担も考慮する必要があります。具体的な治療法の選択は、専門の医師と相談して決めることが重要です。
ステージ4肺がんは治癒が難しいため、治療の有無に関わらず緩和ケアに取り組むことも大切です。痛みや呼吸困難などの症状緩和を目指し、患者と家族のQOL(生活の質)向上が目的となります。

化学療法や放射線療法の効果と副作用
化学療法は、がん細胞の成長を抑える効果がありますが、副作用もあります。主な副作用には、消化器症状(吐き気、嘔吐)、骨髄抑制(貧血、感染症)、脱毛、神経障害などがあります。これらの副作用は、治療が終われば徐々に改善されることが多いです。
放射線療法の効果は、がん細胞を破壊し、腫瘍の大きさを小さくすることです。副作用には、放射線皮膚炎(赤み、かゆみ)、食道炎(飲み込む際の痛み)、肺炎などがあります。放射線療法は患者によって副作用の程度が異なり、放射線量や照射部位によっても変わります。
副作用の軽減や対処法については医師と相談し、適切なケアを受けることが重要です。また、治療効果や副作用のリスクと、患者の状態や家族の意向を考慮し、緩和ケアや他の治療法と組み合わせることも検討されます。
ステージ4肺がんの治療は、多くの困難を伴いますが、効果的な治療法と副作用への対処法を綿密に検討し、医師と共に適切な治療選択を行うことが求められます。
免疫療法や標的治療の効果と適応条件
免疫療法とは、がん細胞を攻撃する免疫システムを活性化させて、がんを治療する方法です。標的治療は、がん細胞の特定の分子や遺伝子に働きかけ、正常な細胞に影響を与えずにがん細胞を抑制する治療法です。
免疫療法の効果は、患者さんの免疫力やがんの種類によって異なりますが、一部の進行がんや転移がんに対して、生存期間の延長や症状の緩和が期待できます。また、標的治療は効果が早期に現れることが多く、副作用も比較的少ないとされています。
しかし、免疫療法や標的治療はすべての患者さんに適応するわけではありません。免疫療法の適応条件としては、がんの種類や状態、患者さんの免疫力、そして治療歴が考慮されます。標的治療は、がん細胞に特定の遺伝子変異がある場合に適用されることが多いです。
具体的な適応条件と効果は、医師と相談の上で決定されるため、患者さんや家族は治療の選択肢を理解し、医療チームと連携して治療を進めていくことが大切です。
緩和ケアと家族や医療スタッフのサポート
緩和ケアとは、がんの進行や重症化に伴う症状や痛みを緩和し、患者さんのQOL(生活の質)を向上させるためのものです。緩和ケアは、治療と同時並行で行われることが多く、患者さんの心身の負担を軽減します。
緩和ケアに取り組む医療スタッフは、専門の知識や技術を持って患者さんの症状に対応し、痛みや不安を軽減するお手伝いをします。また、家族も緩和ケアに積極的に関与し、患者さんの心身のサポートに努めることが重要です。
家族や医療スタッフのサポートは、患者さんが安心して治療に取り組める環境を整えることにもつながります。適切な緩和ケアとサポートが行われることで、患者さんはより良い生活を送ることが可能となります。
4.予防策と早期発見の重要性
がんの予防策としては、健康的な生活習慣の維持や定期的な検診が推奨されます。喫煙や過度のアルコール摂取の制限、適度な運動や野菜を中心としたバランスの良い食生活が有効です。
早期発見が重要である理由は、がんが早期の段階であれば治療の選択肢が多く、治療効果も高まるからです。早期発見のためには、自分自身の体調に注意を払い、何らかの異常を感じた場合はためらわずすぐに医療機関で検査を受けることが大切です。
また、定期的な検診や健康診断でがんのリスクを評価し、必要に応じて専門医の診療を受けることが早期発見につながります。予防策と早期発見に取り組むことで、がんによる健康被害を最小限に抑えることが可能です。

原因やリスク要因の理解と対策
肺がんの原因には様々なものがありますが、最も重要な要因は喫煙です。他にも、大気汚染や劣化した環境、遺伝子異常、年齢、性別なども影響があります。理解した上で対策を考慮しましょう。
まず、喫煙を止めることが最も効果的な対策です。禁煙により肺がんリスクが著しく減少します。また、受動喫煙も肺がんのリスク要因ですので、周りの人にも配慮してください。
次に、健康的な生活習慣を実践しましょう。適度な運動やバランスの良い食事、十分な睡眠が重要です。また、ストレスを適切に発散する方法を見つけることも大切です。
さらに、遺伝子検査を受けることで、遺伝的なリスクを把握することができます。遺伝子検査の結果によっては、より早期に予防策を講じることが可能です。
最後に、定期検診を受けて早期発見を目指しましょう。肺がんは早期であれば治療効果が高まり、生存率が向上します。
定期検診や症状の早期発見のポイント
定期検診は、肺がんの早期発見に大いに役立ちます。定期検診では、胸部レントゲンやCTスキャンが行われ、異常が見つかればさらに詳しい検査が実施されます。
また、現れている症状に注意しましょう。肺がんの初期症状として挙げられるものは、せき、痰の出方の変化、息切れ、胸部の痛み等です。これらの症状が続く場合は、医師に相談することが重要です。
さらに、肺がん患者の家族には遺伝性要因が関与することが分かっています。そのため、家族に肺がん患者がいる場合は、早期に定期検診を受けることを検討しましょう。
最後に、労働環境にも注意が必要です。アスベストや放射線などの職場での曝露は肺がんリスクを高めます。保護具を着用し、定期検診を受けましょう。
5.まとめと今後の展望
「早期発見が重要」という言葉はよく聞かれますが、たとえ進行した状態であっても、決して一切の希望がなくなるわけではありません。
近年の医療技術の進歩はめざましく、患者さんの身体への負担が少ない分子標的薬や、ご自身の免疫の力を利用する免疫療法など、新しい治療法が次々と登場しています。
これらの治療法によって、以前よりも長く、かつ安心して過ごせるケースが増えてきました。
大切なのは、ご自身の状態に合わせて、適切な情報を得ることです。主治医とよく話し合い、治療方針について納得しながら決めていくことが、より良い治療の第一歩となります。
また、不安や疑問に思うことがあればそのままにせず、遠慮なく主治医や医療スタッフに相談してみてください。
私たちの身体は、治療によって大きく変化することもあります。しかし、つらい症状を和らげる緩和ケアや、治療を支えるさまざまなサポートも充実してきています。これらは患者さんご本人だけでなく、ご家族を含め、がんサバイバーの皆様の心の支えにもなります。
これからも、医療の進歩は続きます。新しい治療法や、診断技術の研究も日々進められています。ご自身のペースで、必要な情報を集めながら、病気と向き合っていってください。
※この記事は2024年6月20日に公開され、2025年6月3日に内容を更新しました。

快適医療ネットワーク理事長
監修
医学博士 上羽 毅
金沢医科大学卒業後、京都府立医科大学で研究医として中枢神経薬理学と消化器内科学を研究。特に消化器内科学では消化器系癌の早期発見に最も重要な内視鏡を用いた研究(臨床)を専攻。その後、済生会京都府病院の内科医長を経て、1995年に医院を開業。
統合医療に関する幅広し知識と経験を活かして、がんと闘う皆様のお手伝いが出来ればと、当法人で「がん患者様の電話相談」を行っております。