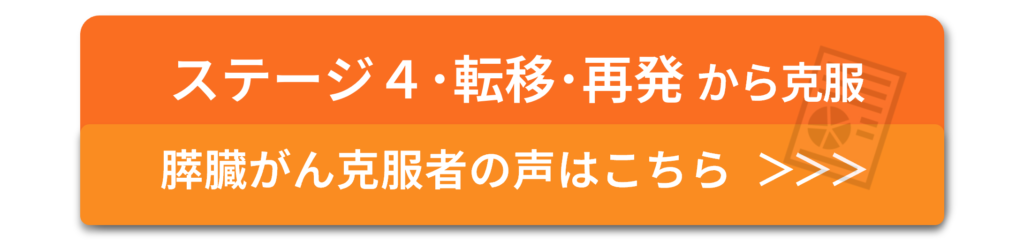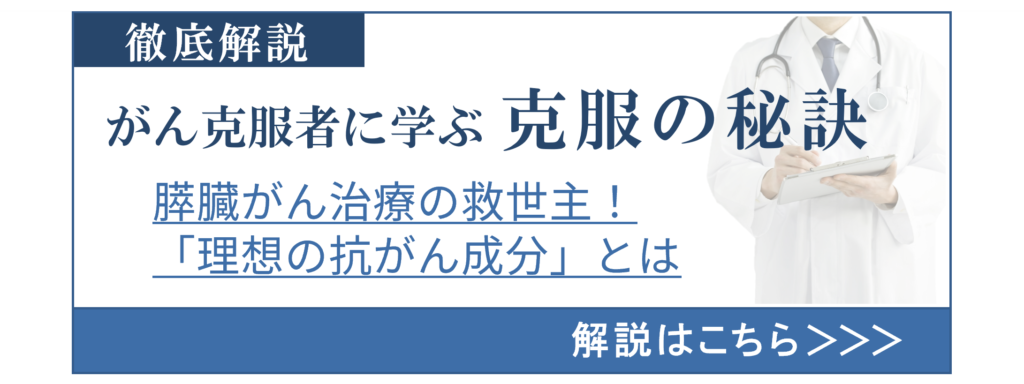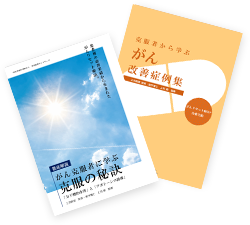- 2024.09.10
- 膵臓がん
膵臓がん早期発見!血液検査で闘病をサポート
膵臓がん(すい臓がん)は、初期の段階では自覚できる症状が少ないため、早期発見が難しいことで知られています。日本において、毎年多くの方が膵臓がんと診断されており、その数は増加傾向にあります。
このコラムでは、膵臓がんを早期に発見するために重要な血液検査に焦点を当ててお話しします。
なぜ血液検査が重要なのでしょうか。そして、どのような検査が行われるのでしょうか。
血液検査は、膵臓がんの診断において最初に行われることが多い検査の一つです。血液を採取するだけで、体への負担が少なく、比較的簡便に行えるという大きなメリットがあります。
血液検査では、がん細胞や、がん細胞に反応して体が作り出す特定の物質の量を調べます。この物質を腫瘍マーカーと呼びます。
膵臓がんの診断でよく用いられる腫瘍マーカーには、「CA19-9」や「CEA」等があります。これらの数値が高く、疑わしい時には、膵臓がんである可能性を示す一つの点となります。
しかし、腫瘍マーカーの数値は、膵臓がん以外の病気、例えば膵炎などでも上昇することがあります。そのため、腫瘍マーカーの数値だけでがんの確定診断をすることはできません。
腫瘍マーカーの数値に異常が認められた場合や、何らかの理由でがんの疑いが持たれた場合には、さらに詳しい精密検査が行われます。これには、腹部超音波検査(エコー)、CT、MRI、PETなどの画像診断があります。これらの検査によって、膵臓に病変があるかどうか、また病変のサイズや位置などを確認します。
さらに、より詳細な情報が必要な場合には、超音波内視鏡(EUS)や内視鏡的逆行性胆管膵管造影(ERCP)といった専門的な検査が行われることもあります。EUSでは、消化管内から超音波のプローブを挿入し、膵臓をより近くで診ることができます。病変が見つかった場合、EUSの画像を見ながら針を穿刺して組織や膵液を採取し、病理検査を行うこともあります。また、ERCPは、口から内視鏡を挿入し、乳頭部と呼ばれる胆管と膵管の合流する先端部分から造影剤を逆行させて注入し、膵管の状態を見る検査です。
これらの検査を組み合わせて総合的に判断し、初めて膵臓がんかどうかの診断が下されます。
このコラムでは、これらの血液検査や精密検査、検査方法について、より詳しく解説していきます。
1. 膵臓がん血液検査の重要性
膵臓がんは、初期症状がほとんどないため、診断が難しいことで知られています。しかし、がんの発見を助ける重要な手がかりが、私たちの血液中に含まれていることがあります。特に、腫瘍マーカーと呼ばれる特定の物質を調べる血液検査は、体への負担が少なく、比較的簡便に行えるという大きなメリットがあり、診療において重要な手助けとなります。
現在、日本の医療機関で主に活用されている腫瘍マーカーは、CA19-9とCEAなどです。これらの数値が高く、疑わしい場合には、膵臓がんの可能性を示す一つのきっかけとなります。
しかし、数値が高いからといって、必ずしも膵臓がんであると確定するわけではありません。例えば、膵炎や胆石症、胆管炎といった別の病気でも数値が上昇することが多くあります。
そのため、腫瘍マーカーの結果だけで判断するのではなく、より詳しい精密検査で確認することが大切になります。
腫瘍マーカーの役割と注意点
腫瘍マーカーは、がん細胞や、がん細胞に反応して体内で作られる物質で、その値を血液検査で調べます。膵臓がんの診断でよく用いられるのが、CA19-9とCEAです。
・CA19-9
膵臓がんの患者さんの多くで数値が上昇することが知られています。特に、進行度や治療の効果を評価する上で有用なマーカーとされています。
・CEA
大腸がんや胃がんなど、消化器系のがんでも上昇することがあるため、膵臓がんに特異的なマーカーではありません。しかし、CA19-9と併用することで、診断の精度を高めるために役立てられます。
これらの腫瘍マーカーは、あくまでもスクリーニング検査(病気の可能性を調べるふるい分け検査)としての役割を担います。腫瘍マーカーの数値が正常範囲内であっても、がんの可能性が完全にないとは言い切れません。
逆に、数値が高くても、それがすぐにがんを意味するわけではないため、結果に一喜一憂しすぎる必要はありません。
人間ドックやがん検診で血液検査を受ける際には、腫瘍マーカーの値だけでなく、他の検査項目と合わせて総合的に評価することが重要です。
ご自身の健康状態について、かかりつけの医師と相談しながら、日々の健康管理に役立てていくことが大切です。
2. 膵臓がんの検査方法
膵臓がんは、その位置や性質から診断が難しいとされていますが、診断を確定し、治療方針を決定するためには、さまざまな検査が診療に活用されます。
これらの検査は、それぞれ異なるメリットと役割を持っており、複数の検査を組み合わせて総合的に評価することが重要です。
CT検査
CT検査(コンピュータ断層撮影)は、膵臓がんの画像診断において、最も一般的に行われる検査の一つです。
高速で回転するX線を使って体を薄いスライス状に撮影し、コンピュータで処理することで、膵臓やその周辺の臓器を立体的に観察できます。特に造影剤を用いることで、血管の状態や腫瘍の血流、周囲への広がりなどを詳細に評価することが可能です。
これにより、がんのサイズや位置、リンパ節への転移の有無など、外科手術で切除できるかどうかを判断する上で重要な情報が得られます。CT検査は比較的短時間で終わり、痛みも少ないため、患者さんへの負担が少ないこともメリットの一つです。
MRI検査
MRI検査(磁気共鳴画像法)は、強力な磁場と電波を利用して、膵臓の内部構造や病変を鮮明に描出します。CT検査では見つけにくい小さな病変や、膵管内の微細な変化を捉えるのに優れており、早期の膵臓がんを発見する上で非常に有効な検査とされています。
また、MRI検査の一種であるMRCP(磁気共鳴胆・膵管造影)を行うことで、膵管や胆管を造影剤を使わずに見ることができ、膵管の拡張や狭窄、結石などの有無を調べることも可能です。これは、慢性膵炎や膵臓がんによる膵管の変化を評価する上で欠かせない検査です。
ただし、MRI検査はCT検査に比べて時間が長くかかり、検査中に大きな音がすること、体内にペースメーカーなどの金属が埋め込まれている場合には受けられないといった注意点があります。
EUS検査
EUS検査(超音波内視鏡検査)は、口から挿入した内視鏡の先端に、超音波のプローブが付いている特殊な検査です。胃や十二指腸の中から、すぐ近くにある膵臓を高解像度の超音波で診ることができます。これにより、通常の腹部超音波検査やCTでは見つけにくい小さな腫瘍や、膵管との関係を詳細に確認することが可能です。
EUS検査の最大のメリットは、リアルタイムに観察しながら、針を穿刺して病変の組織や膵液を採取し、病理検査を行う生検を同時に行えることです。このFNA(超音波内視鏡下穿刺吸引法)という手技により、がんであるかどうかを確定するための、より正確な情報が得られます。
その他の検査
これらの主要な検査に加え、PET(ペット)検査や血管造影検査など、別の検査が診療に用いられることもあります。
PET検査(陽電子放出断層撮影)
がん細胞がブドウ糖を多く取り込む性質を利用して、全身のがん細胞の有無や転移の有無を探す検査です。特に、遠隔転移がないかを確認する上で重要な役割を果たします。
血管造影検査
膵臓周辺の血管に造影剤を注入し、X線で撮影することで、腫瘍が血管に浸潤しているかどうかを調べる検査です。治療方針、特に外科手術の適応を判断する上で重要な情報となります。
これらの様々な検査法を、患者さんの症状や状態に応じて適切に組み合わせることで、医師は膵臓がんの正確な診断を下し、一人ひとりに合った最適な治療計画を作成します。ご自身がどのような検査を受けることになるのか、不安な点があれば、担当の医師に質問して知ることが大切です。
3.膵臓がん治療の選択肢
膵臓がんの治療は、がんの進行度合い(ステージ)や患者さんの体の状態、年齢、そしてご本人のご希望によって、複数の選択肢の中から決定されます。
ここでは、主に日本の医療機関で行われている代表的な治療法について、それぞれの特徴と役割を解説します。
膵臓がん治療の選択肢
・手術療法
膵臓がんの治療において、最も根治が期待できるのが外科手術です。
手術は、がんが膵臓の中に留まっており、周囲の重要な血管や臓器に浸潤していない場合に適用されます。
手術の方法は、がんが膵臓のどの部分にあるかによって異なります。
膵頭部にがんがある場合:膵頭十二指腸切除術
がんがある膵頭部とともに、十二指腸や胆管、胆のう、周囲のリンパ節などを切除します。
膵臓の切除範囲が多く、体への負担が大きい手術の一つですが、長年の経験と技術の進歩により、安全性が高まっています。
膵尾部にがんがある場合:膵体尾部切除術
がんがある膵臓の体部から尾部にかけてを切除します。多くの場合、脾臓も一緒に摘出されます。
手術は、がんを取り除くことによって根治を目指す一方で、合併症のリスクも伴います。
医師は、患者さんの全身状態や年齢、持病などを慎重に評価し、手術が可能かどうかを判断します。手術後は、早期の回復を目的に、リハビリテーションや栄養管理が不可欠となります。
・薬物療法
手術が難しい場合や、手術後の再発を抑える目的で、薬物療法が選択されます。
薬物療法には、抗がん剤を用いる化学療法と、特定の分子に作用する分子標的治療があります。
化学療法(抗がん剤治療)
抗がん剤は、がん細胞の増殖を抑え、死滅させることを目的とした薬剤です。点滴や内服によって投与され、血液に乗って全身を巡ることで、目に見えない小さながん細胞にも作用します。
多くの場合、複数の抗がん剤を組み合わせて治療効果を高めます。
分子標的治療
がん細胞が持つ特定の遺伝子や分子の働きを阻害する薬剤を用います。
正常な細胞への影響を少なくし、副作用を抑えながら、がん細胞だけを攻撃することを目的としています。
これらの薬物は、膵臓がんの進行を遅らせ、症状を和らげる効果が期待されます。
・放射線治療
放射線治療は、高エネルギーの放射線を体外からがんのある部位に照射し、がん細胞のDNAを破壊することで、がん細胞を死滅させることを目的とした治療法です。手術が難しい場合や、手術後の再発予防、痛みなどの症状緩和を目的として行われることがあります。
放射線治療は、主に局所のがんに対して効果を発揮するため、薬物療法と併用されることも多くあります。
これにより、全身のがん細胞の増殖を抑えつつ、局所のがんを集中的に攻撃することが可能となります。
患者と医師が共に考える治療選択
これらの治療法は、単独で行われることもありますが、患者さんの状態や病期(ステージ)に応じて、複数を組み合わせることもあります。日本では、診療ガイドラインが作成され、個々の患者さんに最適な治療の流れを検討するための基準が設けられています。
ご自身の治療方針について不安な点がある場合は、担当の医師に相談し、納得できるまで話し合うことが大切です。セカンドオピニオン(別の医師の意見を聞くこと)を利用して、より良い治療法を探すことも、選択肢の一つです。
4.膵臓がんの予防と日常生活
膵臓がんの発症リスクを完全にゼロにすることは難しいですが、いくつかの生活習慣を見直すことで、そのリスクを低減できることが、これまでの研究で分かっています。これらの習慣は、膵臓がんだけでなく、糖尿病など他の生活習慣病の予防にもつながります。
膵臓がん予防のための生活習慣
以下の項目は、健康な生活を送る上で、誰でも日々の暮らしに取り入れられるものです。
・健康的な食生活
野菜や果物、全粒穀物といった食物繊維が豊富な食品を多く摂取し、高脂肪・高カロリーな食事を控えることが推奨されます。
・適正体重の維持
肥満は膵臓がんを含む、様々ながんのリスクを高めるとされています。適正な体重を維持することで、これらのリスクを軽減できることが分かっています。
ご自身のBMI(肥満度を表す体格指数)を知ることも大切です。
・定期的な運動
定期的な運動は、体重管理だけでなく、免疫力を高め、体全体の健康を維持する上で重要です。
週に150分以上の中程度の運動、または75分以上の活発な運動が勧められています。
・禁煙と節度ある飲酒
喫煙は、膵臓がん発症の大きなリスク要因の一つです。禁煙は、膵臓がんだけでなく、全てのがんの予防につながります。
また、過度なアルコール摂取もリスクを高めることが知られています。
・質の良い睡眠とストレス管理
十分な睡眠と、日々のストレスを軽減することも大切です。趣味を楽しむことは、心と体の健康を保つ上で有効です。
定期的に検診を
膵臓がんは、初期には自覚できる症状が少ないため、早期発見が難しい病気です。だからこそ、定期的な健康診断や人間ドックが、がんを見つけるための最も重要な機会となります。
膵臓がんの早期発見には、これまでもご説明した血液検査や画像診断が欠かせません。特に、糖尿病を持つ方や、ご家族に膵臓がんの既往歴がある方は、リスクが高いとされているため、定期的ながん検診を受けることが強く勧められます。
もし、検査で腫瘍マーカーの数値に異常が認められたとしても、不安になることはありません。これは、精密検査をお願いするきっかけに過ぎません。医師と相談しながら、腹部超音波検査(エコー)やCT、MRIといった画像診断を受けることで、早期に病変を発見し、より良い治療結果につなげることができます。
ご自身の健康に意識を向けつつ定期的に検診を受け、気になる点があれば医療機関を受診すること。それが、膵臓がんに立ち向かうための、最も実践的な予防策と言えるでしょう。
5.まとめにかえて
膵臓がんは、その初期症状の少なさから、発見が難しい病気とされています。
しかし、今回のコラムでご紹介したように、定期的な健康診断や血液検査、そして精密な画像診断を受けることで、早期に病変を見つけることが可能となります。
早期発見は、より効果的な治療へと繋がり、ご自身の未来を切り拓くための大きな一歩となります。
ご自身やご家族に糖尿病の既往歴がある方や、ご家族に膵臓がんを患った方がいる方など、リスクが高いと考えられる場合には、かかりつけの医師に相談し定期的な検診や人間ドックを受けることを強くお勧めします。
このコラムが、皆さまがご自身の健康と向き合うきっかけとなり、安心して診療を受けられる一助となることを願っています。
※この記事は2024年2月5日に作成され、2025年9月10日に内容を更新しました。

快適医療ネットワーク理事長
監修
医学博士 上羽 毅
金沢医科大学卒業後、京都府立医科大学で研究医として中枢神経薬理学と消化器内科学を研究。特に消化器内科学では消化器系癌の早期発見に最も重要な内視鏡を用いた研究(臨床)を専攻。その後、済生会京都府病院の内科医長を経て、1995年に医院を開業。
統合医療に関する幅広し知識と経験を活かして、がんと闘う皆様のお手伝いが出来ればと、当法人で「がん患者様の電話相談」を行っております。