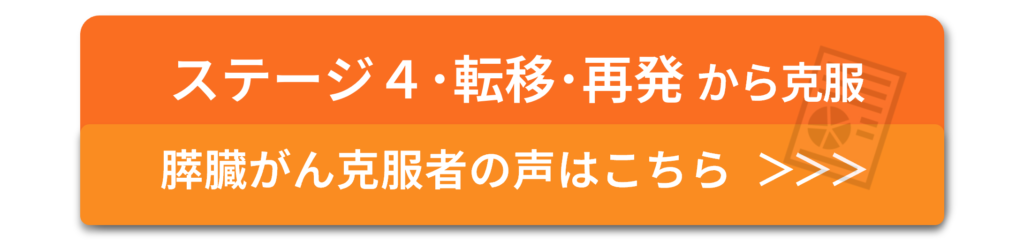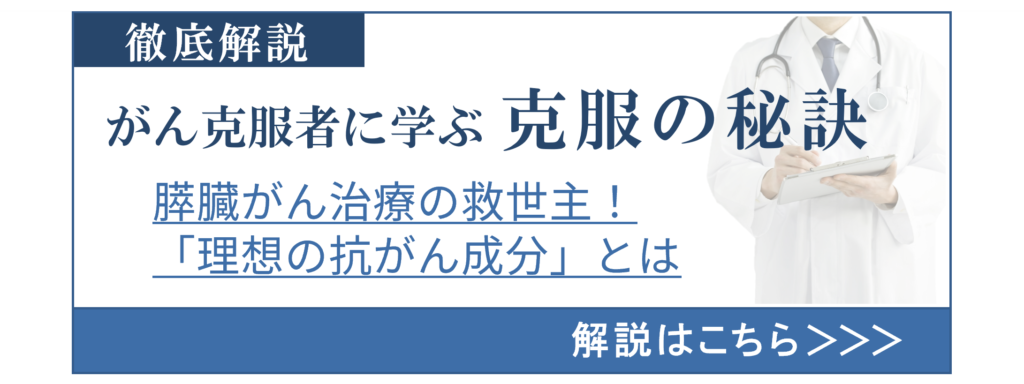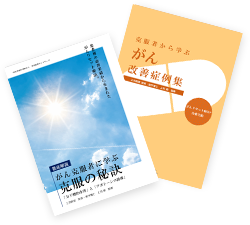- 2025.06.02
- 膵臓がん
膵臓がん初期症状を見逃すな!早期発見のポイント
膵臓癌は、膵臓という体の奥深くに位置する臓器から発生する悪性疾患です。
いわば消化の要と言われるこの膵臓は、肝臓や胆道など周囲の管構造とも密接に関係しています。
膵液には消化を助ける酵素も含まれ、その働きによって栄養の吸収が円滑に行われます。しかし、膵臓がんの初期ステージでは痛みなどの明確な症状が出にくいと指摘されており、発見が遅れると血管や大腸など周辺組織への浸潤が急速に進む危険が高く、負担が非常に大きくなるのが特徴です。
最近はIPMN(膵管内乳頭粘液性腫瘍)の段階で指摘されるケースが増加しており、早めに精密検査を受けることが推奨されています。
今、膵臓がんは前立腺がんや大腸がんと並んで注意すべき病態とされます。お腹や腰の痛み、体重減少などのサインが表れている場合、膵炎や単なる炎症と判断したり、自己判断で薬を使ったりせず、早めに病院を受診し内視鏡検査や造影検査など精密な手順を踏むことが欠かせません。
性別を問わず発症リスクがあるため、怪しい状態が続くのであれば医師へ相談するとよいでしょう。薬や点滴による対処が必要となるケースもあり、血糖値が乱れた場合はコントロールが難しくなることもあります。切除が可能な小さい段階で発見できれば、浸潤が深い部分まで進む前に治療が施されるため、より良い予後が期待できます。
膵臓がんが悪化すると肝臓など他の臓器へも広がりやすく、背側や左脇側を圧迫して強い痛みが出ることがあります。IPMNや膵炎を既往に持つ方は特に注意が必要です。膵液の異常な測定結果や、胃カメラ・超音波を使った検査で不審な所見がある場合、早めに専門医から案内を受けて対策を進めましょう。一度症状が落ち着いて戻るように見えても、ステージが進んでいる可能性は否めません。
前立腺がんや大腸がんと比較しても進行が速い膵がんは、発見しにくい分だけ危険度が高くなりがちです。少なくともわずかな変化やサインがあれば、薬や点滴などで体調をコントロールしつつ、精密検査を受けて状態を正確に把握するのが大切です。
このコラムでは、膵臓がん初期症状と対策についての基本知識についてご説明します。早期発見・適切な治療を目指すため、少しでも気になる兆候があれば最寄りの病院で医師に相談してください。
1.膵臓がんの初期症状
膵臓がんは、発見が難しい病気であり、初期症状がほとんどないため、知られていない事実が多いです。膵臓がんの症状は、消化不良や糖尿病が起こりやすいことがありますが、これらの症状が現れてもがんかどうかは明確ではありません。膵臓は消化酵素やインスリンを分泌し、食物の消化や血糖値の調整に関わっています。膵臓がんは、膵臓の細胞が異常に増殖し腫瘍ができる病気であり、進行すると他の臓器への転移や機能低下が引き起こされる可能性が高まります。早期発見が重要である一方、初期段階の症状は軽微で特徴的ではないため、発見が遅れがちです。初期症状に気づいた場合、すぐに医療機関で検査を受けることが大切です。また、市販薬で症状が改善されない場合や、長期間症状が続く場合も医療機関の受診が必要です。

初期症状がほとんど無い?膵臓がんの症状とは
すい臓がんの初期症状はほとんど無いとされていますが、実際には膵臓がんの初期段階で見られる症状がいくつかあります。それらは以下の通りです。
– みぞおちの痛み、腹痛、特に腹部中央や背中に痛みがある
– 消化不良、胃もたれ、食欲不振
– 体重の減少
– 便や尿の色の変化
しかし、これらの症状は他の消化器疾患や慢性膵炎などでも見られるため、膵臓がんとの鑑別が難しい場合があります。膵臓がんが進行すると、黄疸や血糖値の異常、腹部膨満感が現れることがあります。また、病気の進行に伴い膵管・胆管の閉塞が起こり、胆汁の流れが悪くなり黄疸が現れることがあります。これらの症状が現れた場合は、速やかに医療機関を受診し、必要な検査を受けることが重要です。
膵臓がんの高リスク患者
膵臓癌のリスクとなる要素はいくつかありますが、以下の条件に当てはまる人は特に注意が必要です。
– 家族に膵臓がん患者がいる
– 喫煙歴がある
– 過度のアルコール摂取
– 肥満や糖尿病の既往歴がある
これらの要素は膵臓がんの発症リスクを高めることが研究で明らかになっており、一般的な生活習慣の改善が膵臓がんの予防に繋がります。特に、男性の場合は喫煙の禁煙や飲酒の適度な摂取、適切な運動量や食事バランスの改善が膵臓がんの予防に効果的です。
早期発見の鍵:黄疸と体重減少を見逃さない
膵臓がんの早期発見の鍵は、黄疸や体重減少などの兆候に気づくことです。青白くなった目の白い部分や皮膚、濃い黄色や茶色の尿、便の色が薄いなどの症状が現れた場合は、早急に医療機関での受診が推奨されます。また、原因不明の体重減少は、膵臓がんや他のがん種の可能性を示唆することがあります。早期診断・治療が適切に行われることで、膵臓がんの生存率は向上するため、自分の体調や症状に注意を払いましょう。
他にも注意が必要な膵臓がんの初期症状
膵臓がんは、早期発見が非常に重要ながんの一種であり、初期症状に注意を払うことで、適切な治療を受けることで可能性が高まります。膵臓がんの初期症状には、以下のような特徴があります。
– 腹痛や背部の痛み
– 体重の減少と食欲不振
– 黄疸(皮膚や目の白い部分が黄色くなる)
– 便の色や形状の変化
– 糖尿病の急激な発症
これらの症状が現れた場合、膵臓癌の可能性があるため、早急に医療機関での検査が必要です。また、家族歴や生活習慣などのリスク要因も考慮し、早期発見に努めることが求められます。喫煙や肥満、慢性膵炎の歴などが膵臓がんのリスクを高めることが知られているため、生活習慣の改善や定期的な検査を行うことも重要です。最後に、膵臓がんの症状は他の消化器疾患と似ていることも多いため、専門医による診断が必要不可欠です。
2.膵臓がんの診断
膵臓癌の正確な診断のためには、最新の検査技術を駆使し、適切な選択が大切です。現在、膵臓がんの診断に用いられる主な検査技術は、血液検査、画像診断(CTやMRI)、内視鏡診断(EUS)、生体組織診断(細胞診や細胞検査)などがあります。これらの検査技術は、がんの進行状況や腫瘍の大きさ、転移の有無などを詳細に把握し、適切な治療方針を立てるために重要です。また、最新の研究により、がん治療の分子標的薬や遺伝子検査を活用した個別化医療が注目されており、膵臓がんの検査技術も更なる進歩が期待されています。患者の病状やリスク要因に応じて、最適な検査方法を選択し、早期治療を実現することが重要です。

膵臓がん検査の基本:血液検査と画像診断
膵臓がんの診断の基本は、血液検査と画像診断です。血液検査では、膵臓がんに特徴的な腫瘍マーカー(CA19-9やCEA)の検出を行い、がんの存在を確認します。ただし、血液検査だけでは診断が確定できないため、画像診断も併用して行われます。画像診断には、CTやMRI、超音波検査(EUS)などが用いられ、膵臓がんの大きさや数、位置、転移の有無などを把握します。これらの検査を組み合わせることで、膵臓がんの正確な診断が可能になり、適切な治療方針を策定することができます。症状やリスク要因に応じて、さらに詳細な検査や治療が必要となることもありますので、医療機関と密接な連携が重要です。
超音波検査、CT、MRI:各検査方法の特徴と使い分け
超音波検査、CT、MRIは、がんの発見や診断に用いられる主要な検査方法です。
まず、超音波検査は、音波を利用して体内の状態を調べる非侵襲的な方法で、特に腹部の臓器を調べる際に有効です。しかし、脂肪組織や骨のような硬い組織で音波が遮られるため、画像が不鮮明になることがあります。
次にCT検査は、X線を用いて体内の断層像を撮影し、従来のX線検査よりも詳細な画像を得ることができます。膵臓のような深部臓器の詳細な構造を観察する際に有効で、腫瘍の大きさや位置を正確に把握できます。
最後にMRIでは、磁気共鳴による緻密な画像を得ることができ、腫瘍の組織の性質まで詳細に調べることが可能です。特に、転移の有無や神経周囲の状況を診断する際に有用です。
以上の検査方法は、それぞれの特徴に応じて適切に使い分けられることが重要であり、医師と患者の相談の上で最適な方法が選択されます。
診断の決め手:内視鏡超音波検査(EUS)の重要性
内視鏡超音波検査(EUS)は、膵臓がんの診断において重要な役割を担っています。EUSでは、内視鏡を用いて超音波プローブを直接、膵臓に近接させて検査を行います。
この方法は、CTやMRIに比べて高い解像度の画像が得られるため、膵臓内の小さな腫瘍や膵管・胆管の異常をより正確に検出できます。また、EUSは手術前の腫瘍の病期評価やリンパ節転移の有無を判断する際にも非常に有用な検査法です。
さらに、EUSガイド下で細胞採取が可能であるため、膵臓外科の診療にも重要な情報が得られます。これにより、治療方針を適切に立てることが可能となります。
転移や膵臓外への拡大の確認:PET検査の役割
PET検査は、ポジトロン放射線断層撮影と呼ばれる技術で、がん細胞が集中している部位を明確に捉えることができます。この検査は、転移や膵臓外への拡大が疑われる場合に行われます。
PET検査では、がん細胞に取り込まれやすい放射性物質を使用して、全身のがん細胞の活動を観察できます。そのため、早期の転移や微小転移の発見が可能となります。
また、PET検査は、がん治療の効果判断や再発の診断にも利用されることがあります。これにより、治療の進行状況や再発の早期発見が可能となり、患者の治療や予後の改善に役立ちます。
3.膵臓がんの治療法
膵臓がん治療法は、病状や患者の体力などに応じて手術、放射線療法、化学療法(抗がん剤)などの方法が選択される。手術はがん細胞を直接除去する効果的な方法であるが、すべての患者に適応できるわけではない。放射線療法は、がん細胞に対して放射線を照射し、細胞の増殖を抑制する。また、化学療法(抗がん剤)は薬剤を用いてがん細胞の増殖を抑える方法であり、副作用があるものの、手術が難しい場合などに有効である。

手術治療:膵頭切除術や膵尾切除術の適応条件
手術治療は、膵臓がんの進行度や転移の有無によって、膵頭切除術や膵尾切除術が適応されることがある。膵頭切除術は、膵臓の頭部にがんができている場合に行われる手術で、膵臓の一部と周辺の臓器やリンパ節を一緒に摘出する。膵尾切除術は、膵臓の尾部にがんが見つかった場合に行われ、尾部のみを摘出する手術である。いずれの手術も、がんの進行が早期であり、周囲の臓器への転移や遠隔転移がない場合に適応される。
化学療法:さまざまな薬剤とその効果・副作用
化学療法は、膵臓がんに対して効果的な薬剤が開発されており、多くの患者に対して応用される。薬剤の選択は患者の病状や体力、薬剤の効果や副作用によって決定される。主な薬剤としては、ゲムシタビンやフルオロウラシル、イリノテカン、オキサリプラチンなどがあり、これらは単独や併用で使われることがある。副作用には、吐き気や嘔吐、食欲不振、脱毛、血液の異常、免疫力の低下などがあり、患者と医師が十分にコミュニケーションを取りながら治療を進めることが重要である。
放射線療法:患部への照射でがん細胞を死滅させる
放射線療法は、がん治療の一つで、患部に高エネルギーの放射線を照射することで、がん細胞を死滅させます。放射線は、細胞のDNAにダメージを与え、がん細胞の分裂を阻止します。この方法は、手術が困難な場合や他の治療法と併用されることが多く、患者の症状や腫瘍の大きさ、位置により治療計画が立てられます。
しかし、放射線療法は正常な細胞も影響を受けるため、副作用が発生することがあります。そのため、治療前に適切な診断が重要であり、CTやMRIなどの画像検査を行い、正確な腫瘍の位置や大きさを把握します。また、放射線治療は数回に分けて行われることが多く、病院やクリニックで定期的に通院しなければなりません。
予防と日常生活での工夫:膵臓がんの再発を防ぐ
膵臓がんの再発を防ぐためには、予防策と日常生活での工夫が重要です。まず、喫煙や肥満などのリスク因子を避け、適度な運動を行うことが大切です。また、食生活にも気を付け、食物繊維や抗酸化物質が豊富な野菜や果物を摂取し、脂質の過剰摂取を避けましょう。さらに、糖尿病の管理も重要です。
定期検査を受けることで、膵臓がんの早期発見や再発防止につながります。膵臓がんは無症状の初期が長いため、自覚症状がなくても定期的に血液検査や超音波検査を受けましょう。もし再発の兆候が見つかった場合は、速やかに再治療を検討し、医療スタッフと密接に連携してケアを受けることが大切です。
4.まとめ
膵臓がんは、膵(すい)と呼ばれる部位に生じる悪性腫瘍で、肝臓や胆道、血管など周囲臓器への浸潤が進むと治療の負担が高くなることが指摘されています。
初期症状はお腹や腰の痛み、食欲不振、体重減少など比較的に小さい変化として出にくい場合が多いです。こうしたサインを見逃さず、膵癌やIPMNなどのリスクを含まないかどうか早めに精密検査を受けることが重要です。
最近では膵液中の腫瘍マーカー測定や内視鏡検査、造影検査を組み合わせて膵の状態を詳しく調べるケースが増加しています。急に症状が表に出ることは少なく、症状が進行してからステージが高くなると、点滴や薬などの治療を行っても値がなかなか下がりにくい状況に陥る恐れがあります。
膵臓は体内で消化酵素やホルモンの働きをコントロールする大切な器官です。炎症や膵炎を起こすと膵管が詰まり、膵液の吸収や腸内での栄養分解に影響が出ることもあります。日常生活で急に痛みが現れた場合は専門医に相談し、必要に応じて造影や内視鏡検査を行うのが望ましいです。
特に胆道の乳頭部付近で腫瘍が大きくなると、管が圧迫され重篤化する可能性があります。 下記の点を意識し、膵臓がんの早期発見につなげましょう。
・定期的な精密検査や胃カメラでのチェックを怠らない
・膵の負担を下げるために栄養バランスを整える
・お腹や腰の違和感など、今ある症状を日々記録する
・疑いがある場合はすぐに専門医を受診
早期発見は治療時間を短くし、体への負担を少なくするうえで大変重要です。定期受診を行い、万一異常が見つかったら医療機関と連携しながら薬や点滴で悪化をコントロールしましょう。
症状が出にくい膵臓がんこそ、「早めの精密検査」が最大の防御策といえます。いざというときは迅速に受診し、状況に応じて治療プランを立て、健康な状態へ戻ることを目指しましょう。
※この記事は2024年9月13日に公開され、2025年6月2日に内容を更新しました。

快適医療ネットワーク理事長
監修
医学博士 上羽 毅
金沢医科大学卒業後、京都府立医科大学で研究医として中枢神経薬理学と消化器内科学を研究。特に消化器内科学では消化器系癌の早期発見に最も重要な内視鏡を用いた研究(臨床)を専攻。その後、済生会京都府病院の内科医長を経て、1995年に医院を開業。
統合医療に関する幅広し知識と経験を活かして、がんと闘う皆様のお手伝いが出来ればと、当法人で「がん患者様の電話相談」を行っております。