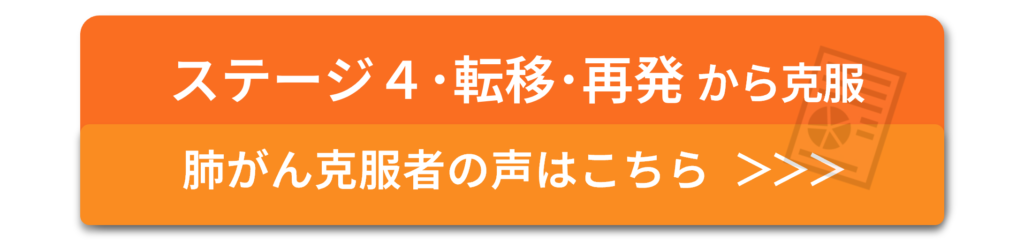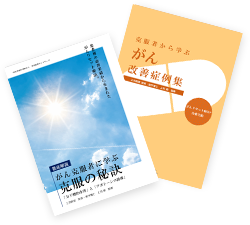- 2024.06.17
- 肺がん
脳転移を抱える肺がん患者のための情報ガイド
肺がんは、がんの中でも死亡率が高い疾患です。かつ、進行がんの患者においては、脳への転移が非常に重要な問題となっています。
このコラムでは、肺がんからの脳転移について、その概要や発生メカニズム、症状、診断方法、治療法などを解説します。
脳転移の早期発見と適切な治療が、患者さんの生活の質の向上や生存期間の延長につながります。 この情報を通じて、肺がん患者さんやそのご家族の皆様が、適切な対処ができる一助となれば幸いです。
1.肺がんからの脳転移。その原因と危険性
肺がんから脳への転移は、がん細胞が血液やリンパ液を介して脳内に運ばれ、脳腫瘍を引き起こす現象です。転移が発生する主な原因は、肺がん細胞が免疫系によって破壊されずに生き残り、さらに分裂・増殖することです。
肺がんの脳転移は、患者の生活の質を低下させるだけでなく、生存率にも影響を与えます。脳転移が発覚すると、治療方法や選択肢が限定され、全身療法や放射線治療を中心とした対応となります。
脳転移の危険性は、脳がんによる神経障害や認知機能の低下、さらには麻痺や意識障害など、身体機能全般に影響を及ぼすことです。

ステージと進行による、脳転移率の差異
肺がんの脳転移率は、ステージや進行具合によって異なります。初期段階の肺がんでは転移のリスクは低いですが、進行するにつれて転移率が上昇します。特に、ステージIII~IVの肺がん患者では、脳転移のリスクが大幅に増加するとされています。
転移率の差異は、がん細胞の浸潤力や免疫系との相互作用、さらには治療効果によっても左右されます。早期発見と適切な治療が、転移リスクを抑える上で重要となります。
脳転移の検査方法
脳転移の検査方法には、MRI(磁気共鳴画像)とCTスキャン(コンピュータ断層撮影)があります。
MRIは、電磁波と磁場を利用して脳組織の詳細な画像を取得する方法で、脳腫瘍や脳梁浮腫を高い解像度で捉えることが可能です。また、神経組織に対する詳細な情報も得られるため、脳転移の診断に有用です。
一方、CTスキャンは、X線を用いて脳組織の断面像を作成する方法で、腫瘍の大きさや位置を判断できます。ただし、MRIよりも解像度が劣るため、微細な病変の特定には限界があります。
脳転移の診断には、MRIとCTスキャンの併用が推奨されることが多いです。
肺がんの他の転移部位
肺がんは、脳以外にも多くの部位に転移することがあります。よく見られる転移部位は、骨、肝臓、皮膚、腎臓、副腎などです。骨への転移は、痛みや骨折のリスクを増加させることがあります。肝臓への転移は、肝機能障害や黄疸を引き起こすことがあります。
皮膚への転移は、皮膚の腫れや痛みを伴うことがあるほか、局所的な感染リスクも増加します。腎臓や副腎への転移は、尿路の閉塞や腎不全の原因となることがあります。
検査や治療の過程で転移部位を特定し、適切な療法を選択することが重要です。
2.脳転移の症状と診断
脳転移は、主に肺がんや乳がんなど他の臓器に発生したがん細胞が血液やリンパを介して脳に達し、脳内で増殖する現象です。
脳転移の症状と診断については、頭痛や神経機能の低下に注意が必要です。
頭痛は脳転移の典型的な症状で、腫瘍が脳組織を圧迫し、脳内の圧力が上昇することにより引き起こされます。その他にも、神経機能の低下が見られる場合があり、視覚障害や感覚麻痺、運動麻痺などの症状が現れることがあります。
脳転移の診断は、MRIやCT検査を用いて行われ、これらの画像診断で患者の脳内に腫瘍が確認されると、脳転移と診断されます。また、腫瘍の種類によっては、血液検査や生体組織検査も行われることがあります。
脳転移は、患者の状態が急速に悪化する場合があるため、早期発見が重要です。症状が現れた際には、速やかに専門医に相談し、適切な診断と治療を受けることが求められます。

転移性脳腫瘍の機能障害
転移性脳腫瘍は、脳の機能を損なうことがあり、麻痺や言語障害などの神経機能障害が生じることがあります。これらの障害は、腫瘍が脳の機能を司る部位に影響を与えることで発生します。
麻痺は、腫瘍が運動野や感覚野に影響を与えた場合に生じ、手足の力が入らなくなったり、感覚が鈍くなったりすることがあります。言語障害は、腫瘍がブローカー野やウェルニッケ野に影響を与えた場合に発生し、話すことや理解することが困難になります。
これらの神経機能障害が現れた場合、脳腫瘍の可能性が高まるため、速やかに医療機関で検査を受けることが重要です。早期の診断と治療により、脳の機能障害の進行を遅らせることが可能となります。
脳転移の再発とその兆候
脳転移が治療後に再発することがあります。その兆候には、前回と同様の頭痛や神経機能障害が挙げられます。再発の早期発見は、患者の生活の質や生存期間に大きな影響を与えるため、非常に重要です。
再発の兆候を感じた場合は、すぐに医療機関で検査を受けることが求められます。再発した腫瘍に対しては、再手術や放射線治療、化学療法などの治療が選択されます。
脳転移の再発を防ぐためには、定期的な検査が不可欠です。また、健康的な生活習慣を続け、免疫力を維持することも再発予防に役立ちます。
医師との相談
主治医としっかり話し合いを重ね、診断や治療方針を理解することが重要です。
その理由は、適切な治療を受けることで症状の改善や生活の質の向上が期待できるからです。
具体的には、MRIやCTなどの画像検査によって脳転移の部位や状態が把握でき、その結果を基に治療選択が行われます。
また、患者の全身状態や他臓器の状況、病状の進行度なども考慮されます。
診断結果や治療方針については、医師と十分な話し合いを行い、理解を深めることが必要です。
病院や医療チームと連携して、最適な治療法を選択し、治療を進めることで、よりよい経過が期待できます。
3.脳転移における治療法の選択
脳転移治療法には、放射線治療、手術、薬物療法があります。
放射線治療では、定位放射線治療やガンマナイフが選択されることが多く、病変の周囲の正常組織への影響を最小限に抑えながら、がん細胞を破壊する効果が期待できます。
手術治療は、病変の大きさや位置によって適応が限られますが、脳腫瘍の切除や圧迫部位の緩和を目的として行われます。
薬物療法では、抗がん剤や分子標的薬の投与により、がん細胞の増殖を抑制し、病変の縮小を目指します。
治療法の選択は、患者の病状や転移部位、全身状態などを総合的に判断し、医師と相談しながら決定されます。

ガンマナイフと放射線照射
ガンマナイフと放射線照射は、どちらも脳転移に対する放射線治療ですが、適応や効果に違いがあります。
ガンマナイフは、高い精度で照射が可能であり、病変の周囲の正常組織への影響を最小限に抑えることができます。
適応は、病変数が多い場合や、手術が困難な部位にある場合などです。
放射線照射では、広範囲の病変や複数の病変に対して効果が期待でき、一般的には局所照射と全脳照射の2つの方法があります。
適応は、ガンマナイフと重複する部分もありますが、全脳照射は脳転移が広範囲にわたる場合に選択されます。
医師との相談を通じ、患者の病状や治療目的に合わせた最適な放射線治療法を選択することが大切です。
化学療法と標的薬物療法
化学療法は全身に作用する薬剤を用いてがん細胞の増殖を抑える治療法であり、標的薬物療法は特定の分子標的に働きかけがん細胞の増殖や転移を抑制する方法です。この二つの療法は、脳転移患者に対しても一定の効果が期待されます。
しかし、病状の進行を遅らせることが主な目的であり、根治的な治療とはなりにくいことが多いです。また、副作用が伴う場合があり、患者の全身状態や他の療法との併用を考慮する必要があります。
最近では、新たな標的薬物や血液脳関門を通過しやすい薬剤の開発が進んでおり、今後の治療効果向上が期待されます。しかし、現段階では、化学療法と標的薬物療法による脳転移の効果は限界があるため、他の療法と組み合わせることが重要です。
手術の適応と術後のQOL向上
脳転移の手術は、脳腫瘍の切除を目的とした外科的治療法であり、適応となる患者は限られています。
適応となる条件は主に、局所的な転移であること、神経機能の維持が可能であること、全身状態が手術を許容する範囲であることなどが挙げられます。
手術の主な目的は、腫瘍による圧迫を解除し、神経機能の改善や症状の緩和を図ることです。そのため、手術後の患者のQOL(生活の質)の向上が期待できます。また、手術によって腫瘍組織を摘出できるため、他の治療法との併用が可能となり、病状のコントロールや生存期間の延長にもつながります。
しかし、手術にはリスクが伴いますし、全ての脳転移患者に適応となるわけではありません。そのため、十分な検査や診断のもと、医療チームと患者が治療方針を検討することが重要です。
4.脳転移患者の余命・緩和ケア
脳転移患者の余命は、その病状や適用される治療によって異なります。余命が短くなる可能性がある場合、緩和ケアが重要となります。緩和ケアでは、患者の症状緩和やQOL向上を目指して、さまざまな方法が提供されます。
緩和ケアの主な方法は、薬物療法や放射線療法による症状緩和、心理的サポート、介護サービス、栄養指導などがあります。これらの方法は、病状の進行を遅らせることは難しいものの、患者や家族のQOLを向上させることができます。
脳転移患者の緩和ケアは、患者とその家族にとって重要なサポートです。適切な緩和ケアを受けることで、余命の期間をより快適に過ごすことができるでしょう。緩和ケアは、専門の医療チームや施設が提供するため、適切な相談や情報収集が求められます。

脳転移の余命と生存率
脳転移の余命と生存率は、患者さんの個々の状況によって大きく変わります。
一般的には、全身状態や脳腫瘍の場所、転移がんの種類、治療の選択肢や効果、さらには副作用など、さまざまな要素が影響します。
主に、治療の方法や効果が生存率に関わっており、例えば放射線治療やガンマナイフを受けることで、生存期間が延びることが期待されています。
しかし、脳転移の治療は個々に適応が異なるため、医療チームと相談しながら適切な治療方針を立てることが重要です。
症状緩和と生活の質の向上を目指すために
緩和ケアは、がん患者さんの症状緩和や生活の質の向上を目指す医療の一環です。
脳転移の場合、頭痛や神経機能の障害、麻痺などの症状が生じることがあります。
緩和ケアでは、放射線療法や化学療法などの治療法と併用されることが多く、症状の改善や副作用の緩和を目指します。
また、患者さんの心身の状態や生活環境にも配慮し、アセスメントを行いながら最適なケアを提供します。
緩和ケアの目的は、患者さんができるだけ良好な状態で治療を受けられるようサポートすることです。
5.まとめ
脳転移の治療では、患者さんの状況に応じて最適な治療法を選択することが大切です。
医療チームと協力して治療方針を立て、症状の緩和や生活の質の向上を目指すことが求められます。
また、緩和ケアを適切に活用することで、治療をスムーズに進めることができます。
最後に、脳転移治療に関する情報や支援を受けることも大切な要素です。
信頼できる専門家やサイトを利用し、主治医とのコミュニケーションを重ね、治療選択やサポートを受けるための情報を集めましょう。

快適医療ネットワーク理事長
監修
医学博士 上羽 毅
金沢医科大学卒業後、京都府立医科大学で研究医として中枢神経薬理学と消化器内科学を研究。特に消化器内科学では消化器系癌の早期発見に最も重要な内視鏡を用いた研究(臨床)を専攻。その後、済生会京都府病院の内科医長を経て、1995年に医院を開業。
統合医療に関する幅広し知識と経験を活かして、がんと闘う皆様のお手伝いが出来ればと、当法人で「がん患者様の電話相談」を行っております。