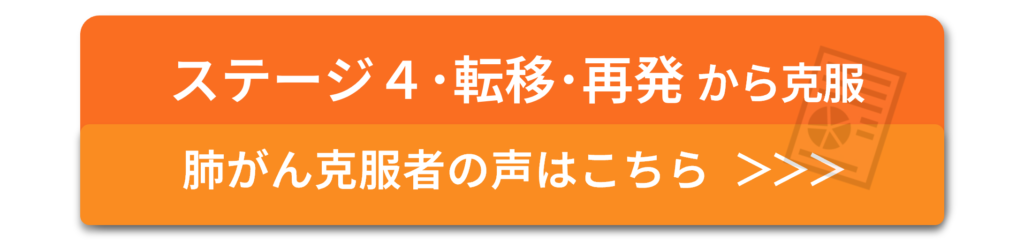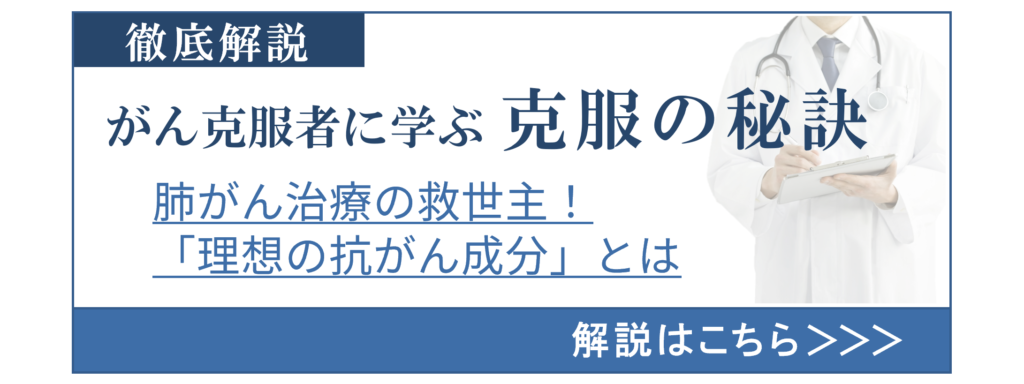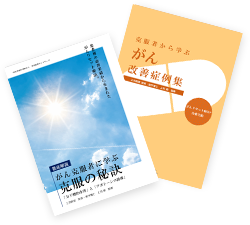- 2025.06.11
- 肺がん
肺がんの初期症状を見逃さないために。早期発見と対処法を解説
肺がんは、日本において男性・女性を問わず高い死亡率を示している病気のひとつです。
呼吸器の中でも肺は重要な部位の一つであり、肺がんの原因についてはアスベストなどの有害物質や煙の吸入など、環境との関係も指摘されています。初期症状を見逃すと、病変が肺門からリンパ節、さらに骨や肝臓、脳などへ広がってステージが進行し、治療の負担が大きくなるケースが多いです。
しかしながら、明確な初期症状がない状態で発症することもあり、軽い息苦しさや発熱、動悸、あるいは気管支炎のような症状と混じったりと、風邪による呼吸器症状やストレスによる症状だと考えて肺がんの前兆を見逃してしまう場合も少なくありません。
こうした体の変化を感じた際は決して放置せず、症状が2週間以上続くようであれば病院を受診したほうがよいでしょう。また、症状等がなくとも40歳を過ぎたら定期的に検診を受けることで、小さく発生したがんを早期に発見できる可能性が高まります。
この記事では、肺がんの早期発見・早期対策について述べ、肺がんの概要や原因を深く知り、適切な対処法をご説明します。
大切なのは、症状を自分の体からのサインと捉え、軽視せずに迅速な対応を取ることです。肺がんへの理解を深め、気になるサインや症状があれば、医師に相談してください。
1.肺がんの概要と早期発見の重要性
肺がんは肺の組織や肺門を中心に広がっていき、リンパ節や骨、脳、肝臓といった別の場所へ転移するケースもあります。進行すると呼吸困難や動悸、頭痛などの症状が起こることもあり、仕事や日常生活への負担が増す可能性があります。早期発見の重要性は大きく、より早く予兆に気付き、初期の段階でがんを見つけられるほどに治療の成功率は高まります。
がん検診としては、定期的に胸部CTやレントゲン検査を受けることがおすすめです。喫煙やアスベストなど有害物質と関係が深い肺がんは、特に煙を吸いやすい環境で長期間過ごした人でリスクが高まります。喫煙習慣のある40歳以上の方や、胃がんなどほかのがん既往歴がある方は、定期的な受診を検討し体の状態をチェックするとよいでしょう。
肺がんの型や組織型によって治療法は変わりますが、手術・放射線・抗がん剤治療のほか、点滴による免疫療法が行われるケースもあります。ステージに応じて治療の流れが大きく異なるため、病院で十分に調べ、担当医に質問されることを推奨します。

日本における肺がんの状況
日本では、肺がんは最も多いがんのひとつであり、がんによる死亡原因の多くを占めます。
一方で、近年の医療技術の進歩により、早期肺がんの治療法が向上し、生存率も上昇しています。しかし、初期症状が少なく、発見が遅れることが多いため、早期発見への取り組みが重要です。
そのため、定期的な健康診断や検診が求められています。
肺がんの主な原因とリスク要因
肺がんの主な原因として最も知られているのは喫煙です。
喫煙者は、非喫煙者に比べて肺がんのリスクが10倍以上高まります。また、受動喫煙も肺がんのリスクを高める要因となります。
その他のリスク要因として、大気汚染や労働環境の影響、遺伝的要因が挙げられます。特に、遺伝的要因は、家族歴がある場合や特定の遺伝子変異を持っている場合に、肺がんのリスクが高まります。
肺がんの予防策としては、まず喫煙の禁煙が最も効果的です。また、健康的な生活習慣を維持し、ストレスを適切に管理することも重要です。定期的な健康診断や検診、遺伝的要因に対するカウンセリングなども、リスクの把握と早期発見に役立ちます。
小細胞肺がんと非小細胞肺がんの違い
肺がんは、小細胞肺がんと非小細胞肺がんの2つの大きなグループに分けられます。これらの違いは主に組織学的性質に基づいており、治療方法や予後も異なります。
小細胞肺がんは、肺がん全体の約15%を占め、急速に成長しやすく転移しやすい特徴を持っています。病気の進行が速く、早期に全身に転移することが一般的であり、主に喫煙による影響が原因です。
一方、非小細胞肺がんは肺がん全体の約85%を占め、成長が比較的遅く、転移しにくい特徴を持っています。非小細胞肺がんは、さらに3つのサブタイプに分類されることがあります。これらは、扁平上皮がん、腺がん、および大細胞がんです。各タイプは、組織学的な特徴と病態に基づいて区分されます。
肺がんの種類と組織は、患者の治療選択肢や予後に大きな影響を与えるため、診断時には正確な種類や組織の特定が重要です。適切な治療法を選択することで、肺がん患者の生存率や生活の質が改善される可能性があります。
2.肺がんの初期症状
肺がんの初期症状は非常に多様であり、種類や進行状況によって異なります。初期段階では自覚症状がほとんどないことが多く、見逃されがちですが、以下の兆候に注意し、早期発見に繋げることが重要です。
・持続的な咳や咳の悪化
・喀痰の量や性状の変化
・喀血(血痰)の出現
・呼吸困難や息切れ
・無原因の体重減少
・疲労感や全身倦怠感
・胸痛や背部痛
どのような症状が現れた場合でも、専門の医療機関に相談し、適切な検査を受けることが大切です。

肺がん初期の一般的な症状
肺がんの初期症状として最も一般的なもののひとつに、咳と痰の変化があります。
肺がんが発症すると、気管支や肺組織に異常が生じ、咳や痰の量や性状に変化が現れることがあります。ただし、風邪や肺炎などの一般的な肺疾患と症状が似ているため、正式に肺がんと診断されるまで気づかないことも少なくありません。
なんとなく息苦しい感じや、自然と出るような通常の咳ではない異常な咳や痰がみられる場合には、早めに医療機関を受診し、病気の早期発見に努めることが重要です。
呼吸困難と胸痛
肺がんは、肺細胞の異常増殖により腫瘍が発生し、気管支や周囲の組織に影響を与えます。このため、患者は呼吸困難や胸痛を感じることがあります。
以下、その理由と具体例を解説します。
・肺がんの腫瘍が大きくなると、気管支を圧迫し、呼吸を妨げます。
・腫瘍が周囲の組織に拡大し、炎症や刺激が生じることで、胸痛が引き起こされます。
・肺の機能低下により、血液中の酸素が減少し、息切れや呼吸困難が生じます。
肺がんが進行すると見られる症状
肺がんは呼吸器系の代表的な悪性腫瘍の一つであり、初期段階では自覚症状が乏しい場合が多いです。したがって、身体が発するわずかな予兆を見逃さず、定期的な検査やセルフチェックを行うことが肝要です。特に進行すると腫瘍が周囲組織に影響を及ぼし、呼吸が苦しいと感じたり、血痰が出るなどの特徴的な症状が表れることがあります。
代表的な症状は以下の通りです。
・咳
肺がんの初期には慢性的な咳が続くことがあります。急に咳の質や頻度が変わった場合は要注意です。
・喀痰
腫瘍が気管支の壁を侵すと出血が起こり、痰に血が混じる血痰として現れることがあります。いつもと違う色調や量は見逃さず、専門医の診察を受けることが望ましいです。
・息切れ
肺がんによる腫瘍が気管支を圧迫すると、呼吸が浅くなり息苦しい状態が生じます。特に、階段の昇降や軽い運動でも息切れしやすくなったら警戒が必要です。
・疼痛
腫瘍がリンパ腺に転移して気管支周辺を圧迫する場合、胸部や肺の周辺に持続的な痛みが起こることがあります。また、声帯付近に影響が及ぶと声のかすれが生じ、喉の痛みを伴うケースも報告されています。
・胸の圧迫感
肺組織が腫瘍によって圧迫されることで、呼吸がしづらい感覚や胸の重苦しさを感じることがあります。普段と異なる圧迫感が続くときは専門医に相談することをおすすめします。
これらの症状が見られる場合、早期に検査を受けることで治癒の可能性を高めることができます。
近年は手術や放射線、化学療法など多角的な治療法が確立されており、症状の進行度に応じた最適な選択肢を検討できます。肺がんは転移しやすい性質をもつため、何もしなくても自然とよくなると期待するのは危険です。日頃から生活習慣に注意し、体調の変化をこまめにチェックすることで症状に早く気づき、適切な治療を受けることが大切です。
一見軽微な兆候でも、その背後には肺がんをはじめとする重大な病気が隠れている可能性があります。少しでも異変を感じたら専門機関を受診し、早期発見と早期治療を目指す姿勢が重要です。さらに正しい知識と冷静な対処を心がけることで、自身の健康リスクを最小限に抑えられます。
3.肺がん早期発見のための検査と検診
肺がんの早期発見には、効果的な検査方法と検診が重要です。
特に、以下の検査方法が有効です。
・CT検査
画像診断の一つで、肺腫瘍の存在や大きさを詳細に調べることができます。
・胸部X線検査
肺がんの初期段階での発見が可能な場合があります。
・喀痰細胞診検査
喀痰中の細胞を顕微鏡で観察し、異常細胞の存在を確認します。
また、喫煙者など肺がんのリスクが高い方は、疑わしい症状の有無に関わらず、定期的な検診を受けることが望ましいです。検診は、市町村や企業が実施する一般検診や、医療機関が提供する肺がん専門の検診があります。

CT検査とレントゲン
初期肺がんでは症状がほとんど現れず、早期発見が難しいため、診断にはCT検査とレントゲンが不可欠です。
CT検査は高い精度で異常を捉えられるため、初期肺がんの発見に適しています。例えば、肺内の腫瘍や組織の状態を詳細に調べることが可能です。
一方、レントゲンは広範囲の肺部分をスクリーニングできるため、初期段階の肺がんを発見しやすくなります。
CT検査とレントゲンは初期肺がんの診断ツールとして、早期発見と治療への道を開く強力な手段です。
肺がん検診の重要性
肺がん検診は早期発見によって治療効果が上昇することから、重要性が高まっています。早期のステージで発見できれば、治療の選択肢も増え、治癒の可能性や患者の生活の質も向上します。
肺がんの初期症状は目立たないため、患者が病気に気付くことが難しいです。これが早期発見の妨げとなっています。しかし、定期的な肺がん検診によって、症状が出る前に発見することが可能となります。
肺がん検診に参加することで、検査機関や医師と連携し、正確な診断や治療法を選択することができます。そのため、肺がん検診は予防や早期治療に繋がる大切なプロセスです。
4.肺がんの初期治療
肺がんは一般的ながんの中でも死亡率が高いとされる病気ですが、初期治療が適切に行われることで、生存率は向上します。
肺がんの治療はその進行状態や種類によって異なりますが、早期発見が可能であれば、その時の状況によって手術療法や放射線治療、薬物療法などの選択肢が広がります。
また、リスク因子の把握や予防法も重要です。ここでは、肺がんの初期治療について解説します。

手術療法
肺がんの早期治療で最も効果的な方法は手術療法です。手術によってがん細胞を完全に取り除くことができ、再発のリスクを最小限に抑えることが期待できます。そのため、手術療法は肺がん初期治療の第一選択とされています。
ただし、患者の年齢や健康状態、肺がんのタイプや位置などによって、手術適応が異なります。
適切な診断・検査を行い、医師と患者が納得のいく方法で治療を進めることが大切です。
放射線治療と薬物療法
放射線治療は、肺がん細胞に対して高エネルギーの放射線を照射し、細胞を破壊する方法です。手術が難しい場合や、手術後の再発予防として用いられます。薬物療法には、抗がん剤や分子標的薬、免疫チェックポイント阻害剤などがあり、肺がん細胞の増殖を抑制したり、免疫力を活用してがん細胞を攻撃する効果があります。これらの治療法は、手術療法と併用することで、さらに効果を高めることが期待できます。
適切な治療法の選択と組み合わせが、肺がんの初期治療の鍵となります。
5.肺がん初期症状についてのまとめ
肺がんの初期症状は、咳や喀痰、息切れなどが比較的目立ちにくく、体全体で大きな変化を感じにくくなることも多いです。男性・女性を問わず、リンパ節や肺門などの部位を経由して別の臓器へ広がっていくケースもあり、骨や脳、肝臓などへ転移するリスクがあります。特にアスベストなどの有害物質を含まない環境づくりや、煙の混じった空気をできるだけ避ける対策は、早期の段階で行うことが推奨されます。
万一、肺癌が判明した場合、もし小さな腫瘍の状態で発見できれば、ステージにもよりますが手術や点滴を含む治療の選択肢が増え、体への負担を低く抑えられる可能性があります。医療機関で行われる検査には、組織型を調べるための細胞採取や画像検査、水分や血液の変化を調べる方法など多岐にわたります。
このコラムを参考にしながら、医療従事者と十分にコミュニケーションを取り、ご自身に合った治療プランを加えつつ検討することが大切です。適切な医療機関や関係機関に早めの相談を行い、体と心のケアを優先して治療を進めていきましょう。
※この記事は2024年7月1日に作成され、2025年6月11日に内容を更新しました。

快適医療ネットワーク理事長
監修
医学博士 上羽 毅
金沢医科大学卒業後、京都府立医科大学で研究医として中枢神経薬理学と消化器内科学を研究。特に消化器内科学では消化器系癌の早期発見に最も重要な内視鏡を用いた研究(臨床)を専攻。その後、済生会京都府病院の内科医長を経て、1995年に医院を開業。
統合医療に関する幅広し知識と経験を活かして、がんと闘う皆様のお手伝いが出来ればと、当法人で「がん患者様の電話相談」を行っております。