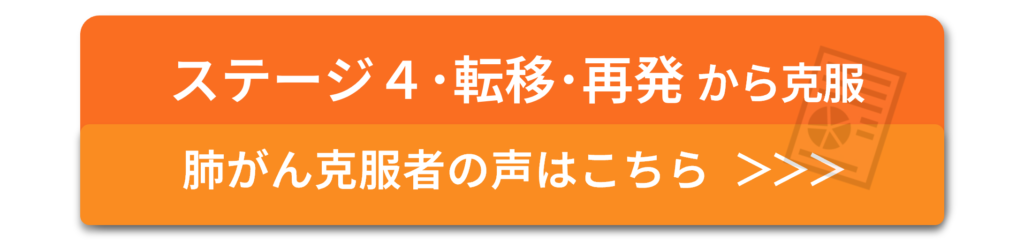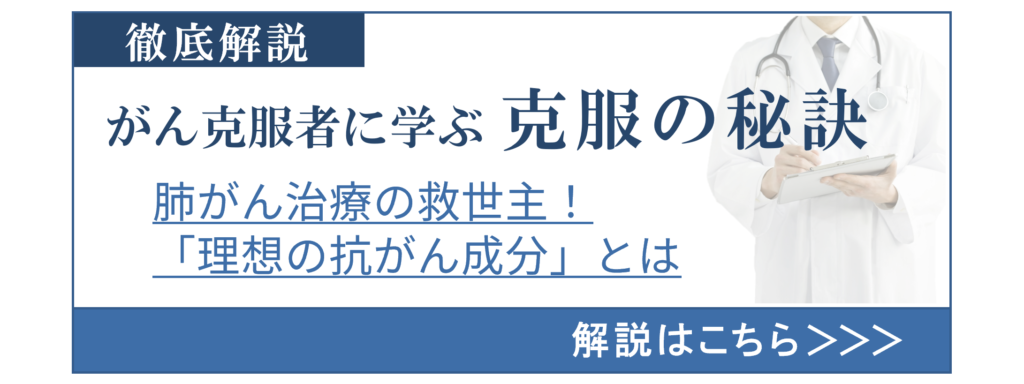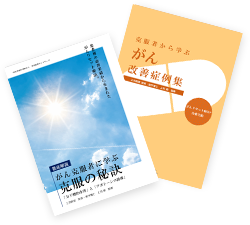- 2025.10.16
- 肺がん
肺がんに影響する喫煙と遺伝子の関わり
肺がんは、日本において死亡率が高いがんの一つであり、喫煙や遺伝的要因など、さまざまな影響を受けて発症することが知られています。特に早期段階では自覚症状が長期間にわたって現れにくいため、正しい知識を持つことがご自身と家族の健康を守る上で極めて重要です。
日本の喫煙率は過去に比べ低下傾向にあるものの、依然として肺がんの最大のリスク要因です。男性はもちろん、女性の肺癌発症においても、能動的に吸う方だけでなく、周囲のタバコの煙(受動喫煙)による影響も無視できません。
国立がん研究センターなどのデータによると、日本における肺がんによる死亡者数は依然として高い水準にあります。過去の研究では、男性の肺がんのうち約7割(68%)が喫煙に関係しているといわれていますが、吸わない方でも発症するケースも少なくありません。これは、遺伝子の影響や環境要因、過去の病歴など、以外のさまざまな要素が複雑に関わっているためです。
本コラムは、肺がんのリスクについて、喫煙の因果関係や遺伝子の影響を客観的に解説し、読者の方々が日々の生活で実践できる対策を提示することを目的としています。
初期の兆候やリスクの評価方法、早期発見のための検査、そして治療と予防に関する選択肢など、肺がんに向き合う上で必要な知識を包括的に提供いたします。
1.肺がんの初期症状と種類
肺がんは、肺の細胞が異常に増殖する病気であり、治療の成功には早期発見が非常に重要となります。この章では、肺がんの基本的な情報として、見逃されやすい初期症状やがんの種類について解説します。さらに、コラムの主要なテーマである喫煙と遺伝子が肺がんの発症や治療にどのように関わっているのかを詳しく見ていきましょう。

肺がんの初期症状と種類
肺がんは初期段階では自覚症状が出にくいことが多いため、定期的な検診が推奨されます。もし次のような症状が続く場合は、肺がんの可能性があるため、医療機関に相談しましょう。
・咳(せき)
・痰(たん)
・呼吸困難(息切れ)
・胸痛(胸の痛み)
・喀血(かっけつ、痰に血が混じること)
また、肺がんは小細胞肺がんと非小細胞肺がんの二つに分類されます。特に非小細胞肺がんは、肺腺がん、肺扁平上皮がん、大細胞がんの3種類に分けられます。治療方法や予後(病気の経過の見通し)は、この肺がんの種類によって大きく異なります。
喫煙と遺伝子の関わり
肺がんの主な原因は喫煙ですが、遺伝子の異常も重要な要素であり、その関わりはリスクと治療戦略の二つの側面から理解することが大切です。
喫煙とリスクの因果関係として、喫煙は、肺がんの発生リスクを大幅に高める最大の要因です。喫煙者は非喫煙者に比べ、肺がんリスクが10倍以上高まると言われています。たばこの煙に含まれる有害物質は、肺の細胞に損傷を与え、遺伝子変異を引き起こすことが報告されています。また、受動喫煙でも肺がんリスクが増加します。喫煙歴がある場合でも、禁煙することで肺がんリスクは着実に減少し、10年以上禁煙している人は非喫煙者と同等のリスクに戻ることが研究で明らかになっています。
一方、遺伝子と治療戦略の関係として、がん細胞は、細胞の増殖を制御する遺伝子に変異が発生することで発生します。この遺伝子異常に関連する肺がんには、特定の分子(タンパク質)が関与しており、EGFR遺伝子やALK遺伝子などが代表的です。これらの遺伝子変異を持つ患者さんには、特定の薬物療法(分子標的薬)が効果的です。そのため、治療を始める前に遺伝子解析(遺伝子検査)を行い、患者さんのがん細胞の特性を知ることが、適切な治療法を選択し、予後を改善するための重要な戦略となっています。
2.早期発見の重要性
肺がんは、早期発見が治療成功のカギを握る病気であり、その重要性は言うまでもありません。早期発見することで治療効果が高まり、患者の生活の質も向上します。
肺がんの検診方法として、まず一般的なのが胸部 X 線による検査です。しかし、胸部 X 線では小さな腫瘍は見逃されることがあるため、CT 検査を併用することで、より精度の高い検査が可能です。
また、喫煙や遺伝子などのリスク要因を把握し、それらに対する生活改善や予防策を取ることも、肺がんの早期発見につながります。
さらに、定期的に受診することで、自身の健康状態を把握し、症状の変化を早期に察知することができます。

がん検診・健診を活用した予防策
肺がんをはじめとするがんの予防策として、定期的ながん検診・健診の受診が重要です。この機会に自身のリスク因子を評価し、早期発見につなげましょう。
・喫煙習慣の改善
・身体活動レベルの向上
・健全な食習慣の維持
・アルコール摂取量の抑制
また、こうした予防策を効果的に実践するために、医療機関や専門家の指導を受けながら改善点を見つけ出し、計画的に取り組むことが望ましいです。
肺がん検診での「要精検」とは?
肺がん検診での「要精検」とは、初期検査の結果から、さらなる精密検査が必要と判断される状態を指します。要精検と判断された場合、腫瘍の疑いが高まりますが、確定診断はまだされていません。
要精検の判断基準には、胸部 X 線や CT での異常所見や影の大きさ、喫煙歴、年齢などが考慮されます。要精検が判定されると、さらに細胞性診断や組織診断を行う精密検査が実施されることになります。
これによって、肺がんの有無や進行度を正確に判断することができます。
精密検査の内容と注意点
肺がんの精密検査には、以下のような方法があります。
・CT ガイド下の穿刺生検
・喀痰細胞診
・気管支鏡検査
・胸腔鏡検査
これらの検査は、病状に応じて医師の判断で選択されます。精密検査はリスクも伴うため、事前に医師と相談しながらリスクとメリットを十分に検討しましょう。
また、精密検査の結果が出るまでの間は不安がつのることもありますが、確定診断が下されるまで焦らず、医師とコミュニケーションを密にし、適切な対応を心掛けることが大切です。
3.肺がん治療における選択肢
肺がんの治療方法は、病気の進行度や患者の健康状態によって異なります。一般的な治療選択肢には、手術・放射線・薬物療法・免疫療法などがあります。
手術は、がん細胞を取り除く方法で、早期発見された肺がんの場合は、手術が第一選択とされます。放射線治療は、がん細胞に対して放射線を照射し、細胞の遺伝子を損傷させることで、がんの増殖を抑えます。
薬物療法は、抗がん剤や分子標的治療薬を用いて、がん細胞の増殖・転移を抑制します。免疫療法は、がん細胞を攻撃する自然免疫機能を活性化させることで、がんの成長を抑制します。
治療選択肢は、医師と患者が十分に話し合い、最適な治療方法を決めることが重要です。

手術や放射線治療の適用条件
手術や放射線治療は、肺がんの初期治療法として用いられることが多いです。しかし、これらの治療法が適用される条件は、腫瘍の大きさ・位置・ステージなどによって異なります。
例えば、手術が適用される場合、腫瘍が局所的で、肺機能や全身状態が手術に耐えうることが条件となります。また、リンパ節転移がないことや、他の臓器への転移がないことも重要な判断基準となります。
一方、放射線治療は、手術が困難な場合や、高齢・基礎疾患などの理由で手術に適さない患者に適用されることが多いです。放射線治療の適用条件には、腫瘍の位置や大きさ、肺の機能などが考慮されます。
治療適用条件は、医師の判断により決定され、患者と十分に話し合われることが望ましいです。
免疫療法や新たな薬物療法の進展
免疫療法は、近年注目されている新たな肺がん治療法で、自然免疫機能を活性化させ、がん細胞を攻撃することで効果が期待されます。特に、PD-1/PD-L1阻害薬は、免疫チェックポイントを抑制し、免疫応答を強化することで、肺がん細胞の増殖・転移を抑制します。
一方、分子標的治療薬は、がん細胞の特定の遺伝子変異を標的として作用し、がんの増殖を抑える効果があります。EGFR阻害薬やALK阻害薬などが、肺がん患者に適用されることがあります。
これらの新たな治療法は、従来の治療法に抵抗性を示すがん細胞にも有効であることが報告されており、今後の肺がん治療に大きな期待が寄せられます。患者や医師が最新の情報を持ち、治療選択肢をより広げることで、より良い治療成績が期待されます。
4.肺がん予防のための対策
肺がんの発症には、喫煙を含め様々なリスク要因が関わっており、日々の生活における予防的な取り組みが非常に重要です。
この予防策の中心となるのが、生活習慣の改善です。具体的には、タバコの禁煙、受動喫煙対策、健康的な食生活の維持、適度な運動習慣の取り入れが挙げられます。これらの生活習慣改善によって、肺がんのリスクを大きく減らすことが可能です。

禁煙と受動喫煙対策の徹底
肺がんの予防において、喫煙対策は最も重要な項目です。喫煙は肺がんの最大の原因であり、吸う本数や期間に応じて発症程度が高くなります。
客観的なデータとして、吸わない人に比べて、タバコを吸う男性では約4.5倍、女性では約4.2倍肺癌になりやすいというデータが国立がん研究センターなどの研究から明らかになっています。
したがって、喫煙や受動喫煙を避け、禁煙することが、肺がんリスクを低下させる最も効果的かつ直接的な方法です。
日本の喫煙率は低下傾向にありますが、学会や国立がん研究センターのサイトが推奨するように、禁煙に取り組む際には、禁煙外来や禁煙支援プログラムを利用することが、喫煙習慣の克服に大きく役立ちます。禁煙を開始した年齢や期間にかかわらず、死亡リスクは低下していくことが、過去のデータで示されています。
次に、受動喫煙も肺がんリスクを上げる重要な要因です。周囲に喫煙者がいる環境を避けること、タバコを吸う場所を制限する対策が必要となります。
タバコを吸わない方において、受動喫煙は特に考慮すべきリスクであるため、こうした対策によって受動喫煙による肺がんリスクを軽減することが期待できます。
健康的な食生活と運動習慣の確立
喫煙対策に加えて、健康的な食生活と運動習慣を確立することは、肺がん予防に重要な役割を果たします。これらは、喫煙以外の様々な要因によって発症する肺がんに対しても、予防効果を発揮すると考えられています。
食生活では、体の酸化を防ぐ抗酸化作用のあるビタミン(A、C、Eなど)を含む食品や、食物繊維を積極的に摂ることが推奨されます。特定の食品に偏らず、主食・主菜・副菜のバランスを整えることが、免疫力向上とがん細胞の発生を抑える効果につながります。同時に、過剰な脂肪の摂取を控えることも、肺がんリスクを低減させるために大切です。
運動習慣に関しても、適度な運動を行うことで免疫力が高まり、がん細胞の発生や増殖を抑制する効果があることが示されています。特にウォーキング、ジョギング、水泳といった有酸素運動が効果的です。運動は筋力や体力の維持にもつながり、治療中の体調管理を助けるという側面もあります。
健康的な食生活と運動習慣は、それぞれが相互に影響し合うことで、予防の効果をさらに高めることができます。これらを日々の生活に継続的に取り入れることが、肺がん予防への効果的な働きかけにつながります。
5.まとめにかえて
今回は、肺がんのリスク要因、特に喫煙と遺伝子の関係について解説し、日々の生活で実践できる予防策としての生活習慣の改善について詳しく見てきました。
肺がんのリスクは、男性では約7割が喫煙に関係するとされるほど、タバコの影響が大きいことは事実です。しかし、この事実を知る目的は、決して不安を抱くことではありません。
むしろ、「行動を起こせばリスクを大きく減らせる」という前向きな可能性を理解し、具体的な対策を講じることこそが重要です。
禁煙や受動喫煙の回避は、ご自身の健康だけでなく、大切なご家族の健康を守る最も強力な手段となります。また、抗酸化作用のある食品をバランス良く摂取し、適度な運動を継続することは、免疫力を高め、がんの予防と闘病中の体調維持、そして何より生活の質(QOL)の向上に直結します。
もし、ご自身やご家族の喫煙歴、またはご家系に肺がんの既往があるなど、何らかのリスクに対して不安を感じた場合は、決して自己判断に留まらないでください。
不安や疑問、現在の健康状態について、積極的に専門の医療機関や医師に相談することが、早期発見と納得のいく治療選択への第一歩となります。
※この記事は2024年12月16日に作成され、2025年10月16日に内容を更新しました。

快適医療ネットワーク理事長
監修
医学博士 上羽 毅
金沢医科大学卒業後、京都府立医科大学で研究医として中枢神経薬理学と消化器内科学を研究。特に消化器内科学では消化器系癌の早期発見に最も重要な内視鏡を用いた研究(臨床)を専攻。その後、済生会京都府病院の内科医長を経て、1995年に医院を開業。
統合医療に関する幅広し知識と経験を活かして、がんと闘う皆様のお手伝いが出来ればと、当法人で「がん患者様の電話相談」を行っております。