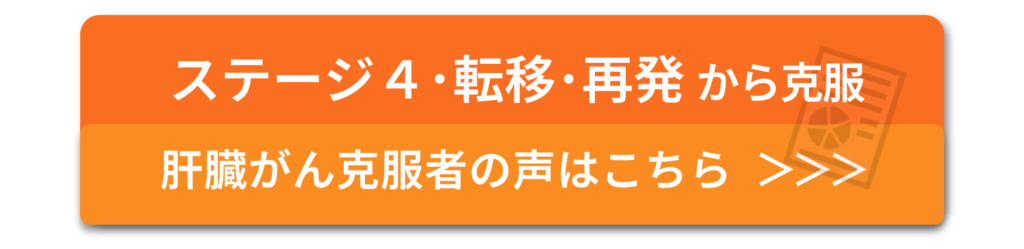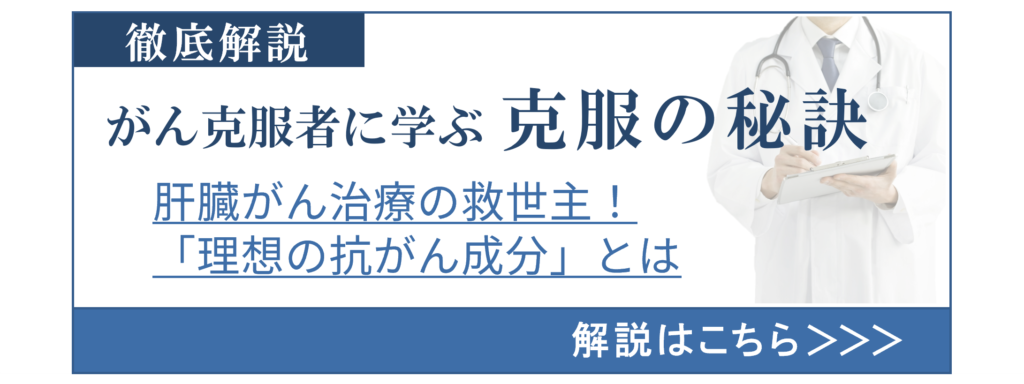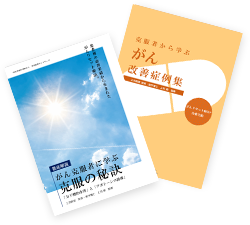- 2025.08.04
- 肝臓がん
肝細胞がんの特徴・原因・治療とは?
肝細胞がんと聞くと、誰もが不安を感じるかもしれません。しかし、原発性肝がんの正しい知識を持つことが、ご自身や大切な方の安心につながります。
肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、初期段階では自覚症状がほとんど現れません。このため、診断時には予後が限られてしまったり、がんがかなり進行した程度で判明するケースも少なくありません。残念ながら、腹膜播種による腹水や肝臓の破裂が見られる場合もあります。日本では肝癌は年間約数万人が診断されており、決して他人事ではない病気です。
しかし、希望はあります。肝細胞癌の発症には、長期間にわたる肝臓への負担が深く関係しています。慢性肝炎や肝硬変等といった疾患は、がん化のリスクを高める主要な要因です。日々の健康診断や腹部超音波検査、CT、MRIといった画像診断、また腫瘍マーカーの血液検査は、自覚症状がなくても肝がんの小さな変化を診つけるための重要な手がかりとなります。全国の病院では、これらの検査を定期的に受けることが早期発見への第一歩だと強調しています。
現在、日本肝臓学会の定めている診療ガイドラインに基づき、治療法は日々進化しています。外科手術による切除、ラジオ波凝固療法、さらには臨床試験や治験も行われる薬物療法(分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬等)や放射線治療など、患者さんの病状や肝機能に合わせた多様な治療法が確立されています。がんが肝臓の血管に広がる門脈腫瘍栓など、進行度に応じた治療戦略も計画されます。
このコラムでは、肝がんの代表的な特徴、肝細胞に変化をもたらす主な原因、診断のための検査方法、そして目覚ましい進歩を遂げている治療法について概要をお届けします。特に、なぜ早期発見がこれほどまでに重要なのか、そしてそれが皆さんの予後にどう関連するのかについて、深く掘り下げていきます。
肝がんへの漠然とした不安が少しでも和らぎ、ご自身の健康を見つめ直し、前向きな一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。
1.肝細胞がんとは
肝細胞がんは、肝臓の細胞が異常に増えることでしこり(腫瘍)ができる病気です。「悪性腫瘍」と呼ばれますが、まずはその原因や症状について理解し、ご自分の体と向き合う第一歩を踏み出しましょう。

肝細胞がんを引き起こす主な要因と生活習慣
肝細胞がんが発生しやすくなる背景には、いくつかのポイントがあります。
特に注意したいのは、次のようなものです。
・ウイルス性肝炎
B型やC型肝炎ウイルスへの感染によって肝臓に長く炎症が続くことで、がん発症のきっかけになることが多いです。
・アルコール性肝炎
お酒の飲み過ぎは肝臓への大きな負担となります。肝臓の細胞が傷つき、炎症や肝硬変を進行させることで発がんリスクが高まります。
・肝硬変
肝臓の機能低下によって肝臓が固くなり、正常な働きを失った状態です。肝細胞がんができやすい土台となります。
・遺伝や体質
一部の遺伝性の病気が関わることもあります。ご家族に肝臓がんが多い場合は注意が必要です。
・肥満や糖尿病
生活習慣病も肝臓に負担をかけるため、長い目で見るとがん発生に関係することがあります。
肝細胞がんの主な症状と初期サイン
肝臓は「沈黙の臓器」とも呼ばれ、肝細胞がんの初期にはほとんど症状を感じません。
しかし、進行してくると次のようなサインがあらわれることがあります。
・お腹の痛みや違和感
腫瘍が大きくなってくると、お腹の右上を中心に痛みや圧迫感を感じることがあります。
・食欲不振
肝臓の働きが低下すると消化機能にも影響し、食欲が落ちやすくなります。
・全身のだるさや疲れ
肝臓の病気では、体全体のだるさや疲れやすさが出ることも多いです。
・微熱
体の中でがんや炎症が起きていると、原因不明の発熱が起きることがあります。
・黄疸
皮膚や白目が黄色っぽくなることがあります。肝臓の機能がかなり低下したサインのひとつです。
これらの症状は、他の病気でも現れる場合がありますが、「普段と違う」と感じたときは、あまり我慢せず早めの受診をおすすめします。何よりも、気になることを一人で抱えこまないことが大切です。
2.診断方法
肝細胞がんの診断は、患者の症状や臨床検査結果を基に行われます。検査方法には、超音波検査、CTスキャン、MRI検査などがあります。これらの検査により、腫瘍の位置や大きさ、転移の有無が明らかになります。診断後には、病期判定とステージ分類が行われ、適切な治療法が選択されます。病期判定には、腫瘍の大きさやリンパ節への転移、遠隔転移の有無が考慮される一方、ステージ分類は、肝臓の機能や患者の栄養状態なども評価される点で異なります。では、肝細胞がんの診断に用いられる検査方法とステージ分類について詳しく見ていきましょう。
肝臓がんの診断に役立つ主な検査
・超音波検査
体の外から肝臓の様子を写し出し、しこりなどの異常を確認します。苦痛も少なく、定期検診にもよく使われます。
・CTやMRI
より詳細に肝臓のしこりの場所や大きさ、周囲の広がりなどを調べるための画像検査です。他の臓器への広がりもチェックできます。
・血液検査と腫瘍マーカー
AFP(アルファフェトプロテイン)やPIVKA-IIといった、がんができることで数値が上がりやすい特殊な物質を調べます。あくまで参考情報ですが、画像検査と組み合わせて診断に役立てます。
肝細胞がんの病期(ステージ)と治療方針
肝細胞がんの進み具合(ステージ)は、腫瘍の大きさ、肝臓以外への広がり、リンパ節などへの転移の有無で段階分けされます。
【I期】
腫瘍が1つで小さく(一般的に2cm以下)、リンパ節や肝臓以外の臓器へは広がっていない段階です。
この時期は自覚症状がほとんどない場合も多く、腫瘍マーカーや画像診断などの定期的な検査によって偶然発見されることもあります。
早期治療が可能で、手術や局所療法が有効とされることがあります。
【II期】
腫瘍が大きくなるか、複数の腫瘍が現れる状態です。
ただし、他の臓器やリンパ節への転移はまだ認められません。肝臓内にとどまっているものの、血管への浸潤(特に門脈など)を伴うこともあり、進行の兆しが見られます。
【III期】
腫瘍の数が多い、または血管(門脈や肝静脈など)への明確な浸潤が認められ、病変が肝臓内の広範囲に広がっている段階です。
リンパ節への転移が現れるケースもあり、治療方法はより慎重な選択が求められます。
治療は薬物療法や放射線治療の併用が検討されることがあります。
【Ⅳ期】
肝臓以外の臓器(肺や骨など)や遠くのリンパ節への転移が確認され、病気が体の広い範囲に広がっている状態です。症状もあらわれやすくなり、全身的な治療が中心となります。
生活の質を保ちながら、症状の緩和や進行の抑制を目指す治療が行われます。
この判定に加え、肝臓そのものの働きや全身状態・栄養状態もよく調べた上で、どんな治療が体に負担が少なく、効果的かを医師が一緒に考えます。医療者とじっくり話し合い、納得した上で治療方針を決めることが大事です。
わからないことや不安なことは、遠慮せず何でも主治医に相談しましょう。
3.肝細胞がんの治療
肝細胞がんの治療は、その方の病状や体の状態に合わせ、いくつかの選択肢から最適な方法が選ばれます。近年は治療法の進歩もめざましく、治療後の日常生活を大切にしたい方にも希望が持てる時代になっています。
手術(外科的切除)や肝移植、局所治療について
・手術による切除
腫瘍が肝臓の一部に限られ、肝臓の働きが十分保たれている場合に選ばれる方法です。
がん部分と周囲の正常な組織を一緒に切除します。回復後の生活が比較的元に戻ることから、状態が合えば根治を目指せる治療です。
・肝移植
肝臓の機能が極端に低下して手術が難しい場合には、条件が合えば他の人から肝臓を移植する方法が検討されることもあります。
手術が難しい場合や、腫瘍が小さい場合には体への負担が少ない「局所治療」が選択されます。
・ラジオ波焼灼療法(RFA)
細い針を腫瘍に刺し、高周波の熱でがんを焼き切る治療法です。小さめの腫瘍に対して特に効果が期待できます。
・経動脈的化学塞栓療法(TACE)
がんに栄養を送る肝臓の血管に、抗がん剤と詰め物を注入し、がんの成長に必要な血流を遮断します。
これらの方法を、病状やご本人の希望に合わせて組み合わせたり、単独で行うこともあります。治療の内容や流れについては、しっかりと主治医と相談してください。
薬による治療と放射線治療の進歩
・薬による治療(分子標的薬・免疫療法)
がん細胞だけを狙った薬や、ご自身の免疫力を高めてがんを攻撃する新しい薬が登場しています。
進行した肝細胞がんや、他の治療が難しい場合にも用いられ、副作用についても様子を見ながら進めます。
・放射線療法
特殊な機械でがん部分を狙って放射線を当てて治療する方法です。手術が難しい場合や、がんが一部に限局している場合に有効です。
近年はより正確に照射できる技術が進み、周りの正常な臓器への影響をできるだけ減らす工夫が進んでいます。
治療の選択肢が広がったことで、患者さんごとに「何を一番大切にしたいか」を尊重した治療が実現しやすくなっています。医師とご自身・ご家族でよく話し合って、納得できる治療法を選ぶことが安心につながります。
4.治療中の生活
肝細胞がんの治療や病気と付き合う時には、体や心への負担が増えることもあります。しかし、日常生活でのちょっとした工夫や改善に取り組むことで、生活の質(QOL)を保ち、安心して過ごすことができます。
以下は、日常生活で気を付けたいポイントです。
・栄養バランスの良い食事
肝臓をいたわりつつ、必要な栄養をしっかりとることが大切です。ご自身の状態に合った食事内容については、医師や管理栄養士に相談しましょう。
・適度な運動
疲れすぎず無理のない範囲で、散歩や軽い体操など身体を動かす習慣を取り入れましょう。体力維持や気分転換にもつながります。運動を始める前には医師へ相談し、負担をかけすぎない内容にしましょう。
・こまめな水分補給
特に治療中の期間は、脱水を防ぐために意識してこまめに水分をとりましょう。
・お酒は控えめに、またはやめる
肝臓への負担を減らすため、アルコールは極力避けることが重要です。病気の進行や再発を予防する意味でも大切なポイントです。
こういった項目から、ご自身が「今できること」に目を向け、安心して治療や日常生活を送っていただければと思います。
5.予防と早期発見
肝細胞がんは、予防と早期発見がとても大切な病気です。現時点で肝細胞がんと診断を受けていない方は、普段の生活の見直しや定期的な検査で、ご自身と大切なご家族の健康を守ることができます。
定期的な検査とウイルス性肝炎の管理
・肝機能検査
定期的に血液検査を受けて、肝臓の働きに異常がないか調べましょう。
・腫瘍マーカー検査
AFPやPIVKA-IIなどを定期的にチェックすることで、がんのサインを早めに発見できます。
・超音波検査
体に負担が少なく、腫瘍の早期発見に役立つ検査です。定期的な受診が勧められています。
また、関連する要素として、B型やC型肝炎ウイルスを持っている方はがんのリスクが高いとされています。主治医と相談し、ウイルス量の測定や抗ウイルス薬の利用など、きちんとした管理を心がけてください。B型肝炎ではワクチン接種も予防の大きな力になります。
肝臓を守る日々の暮らし方
・バランスの良い食事
脂肪や糖分の摂りすぎに注意し、野菜や果物、食物繊維、抗酸化成分も意識してとり入れましょう。
塩分も控えめにし、薄味を心がけることで肝臓への負担が減ります。
また、お酒はできる限り控えましょう。
・運動習慣
日々の散歩や軽い体操などを継続しましょう。肥満を防ぎ、肝臓の健康維持にも効果があります。
無理のない運動で十分です。持病がある方は必ず主治医と相談しましょう。
・禁煙
タバコは肝臓を含め多くのがんの原因となります。できれば禁煙を目指しましょう。
毎日の習慣を少しずつ変えていくことで、肝臓への負担を減らし、がん予防や早期発見にもつながります。
6.まとめにかえて
肝臓がんは「沈黙の臓器」とも呼ばれ、初期には自覚症状が少ないのが特徴です。しかし、だからこそ適切な予防と早期発見が何よりも大切になります。定期的な健康診断や、肝炎ウイルスをお持ちの方であれば積極的なウイルス管理と必要な治療を行いましょう。これらの取り組みは、肝細胞がんのリスクを減らすだけでなく、万が一がんが見つかった場合でも、治療の選択肢を広げ、より良い結果へと関連づける可能性を大きく高めます。
現代の医療は日々進化しており、肝細胞がんの治療法も例外ではありません。外科手術はもちろん、ラジオ波凝固療法のような体に負担の少ない局所治療、そして分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬といった新しい薬物療法が登場しています。
これらの治療法は、がんを効果的に抑えるだけでなく、患者さんの生活の質(QOL)をできる限り保ちながら治療に取り組めるよう、大きく貢献しています。病状やライフスタイルに合わせて最適な治療法を選択できる時代になっているのです。
病気と向き合うことは、大きな不安や孤独を伴うかもしれませんが、なるべく一人で抱え込まないでください。ご自身の体調や生活習慣を見直し、健康的な食事や適度な運動を行うなど、病気そのものよりも今できることを意識するようにしましょう。
そして、少しでも不安や疑問を感じたら、ためらわずに医療機関や専門の医療チームに相談してください。医師や看護師、医療ソーシャルワーカーなど、多くの専門スタッフが皆さんのそばでサポートする準備ができています。
肝細胞がんと診断されても、適切な知識とサポートがあれば、きっと安心して日々を過ごしていくことができます。この先も、皆さんが希望を持って前向きに歩んでいけるよう、心から応援しています。
※この記事は2024年4月19日に作成され、2025年8月4日に内容を更新しました。

快適医療ネットワーク理事長
監修
医学博士 上羽 毅
金沢医科大学卒業後、京都府立医科大学で研究医として中枢神経薬理学と消化器内科学を研究。特に消化器内科学では消化器系癌の早期発見に最も重要な内視鏡を用いた研究(臨床)を専攻。その後、済生会京都府病院の内科医長を経て、1995年に医院を開業。
統合医療に関する幅広し知識と経験を活かして、がんと闘う皆様のお手伝いが出来ればと、当法人で「がん患者様の電話相談」を行っております。