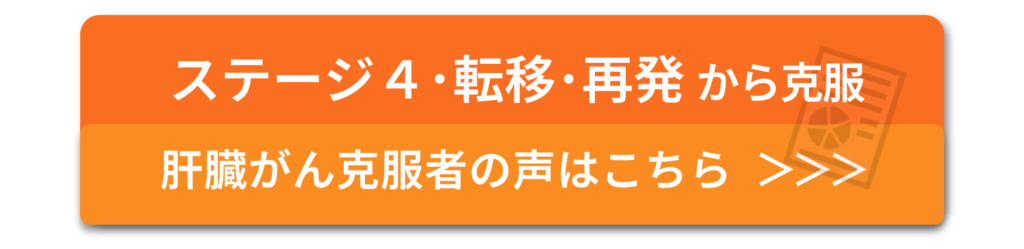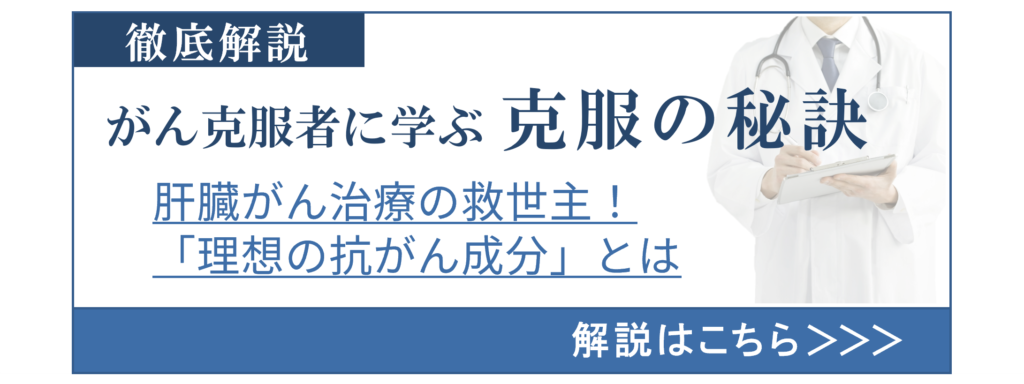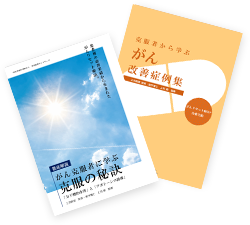- 2025.06.16
- 肝臓がん
肝臓がんの余命を左右する治療の選択
肝臓がんは、日本においても比較的多くみられる疾患であり、特に肝細胞癌と呼ばれるタイプが主流を占めます。
近年では、診療ガイドラインの改訂や分子標的薬の進歩、さらに免疫療法の併用など、肝臓がんに対する新しい治療選択肢が次々と登場しているため、患者さんやそのご家族にとっては情報の整理がますます重要になっています。
とはいえ、治療の方針はがんのステージや原発の場所、血流の流れ、さらには患者さん自身の肝機能障害の程度など、多岐にわたる要素によって左右されます。肝がんの進行度だけでなく、慢性肝炎の有無やウイルス感染の状況といった背景因子も考慮しなければなりません。また、治療費のことであったり、患者が高齢者であった場合のリスク等、不安に思う点も出てくるでしょう。
このようにさまざまな要素があるなかで、余命を左右する治療選択は慎重に行う必要があります。一口に「肝臓がん」といっても、治療法には外科的切除、肝移植、カテーテルを使用したTACE(肝動脈化学塞栓療法)、分子標的薬や免疫療法まで多岐にわたります。医療機関によっては腹腔鏡を使った手術や、より先端的な薬剤の併用が行われる場合もあるため、受診する病院を選ぶ際は最新情報の確認が欠かせません。
このコラムでは、肝臓がんの治療について紹介し、余命を左右するカギとなる要点を詳しく解説します。先端医療の進展が続く今こそ、最適な治療戦略を見いだし、よりよい一歩を踏み出すきっかけにしていただきたいと思います。
1.肝臓がんの原因
肝臓がんは、肝臓の細胞が異常に増殖し、腫瘍を形成する病気です。肝臓は、栄養を代謝し、体内の毒素や老廃物を排出する重要な臓器であり、その機能が低下すると全身に影響を及ぼす可能性があります。
肝臓がんは一般的に、肝細胞がんと胆管細胞がんの2つに分類されます。肝細胞がんは肝臓の主要な細胞である肝細胞から発生し、胆管細胞がんは肝臓内の胆管細胞から始まります。肝臓がんのリスク要因には、肝炎ウイルス感染、肝硬変、脂肪肝、アルコール摂取などがあります。
肝臓がんの治療法は、病状や進行状態によって選択され、手術や放射線治療、化学療法が行われます。
肝臓がんは全身に影響を及ぼす可能性があるため、早期発見が重要です。症状の現れに注意し、定期的な検査を受けることが大切です。また、肝臓の機能が低下すると、消化器系や血液の状態にも悪影響を与えるため、生活習慣の改善も重要です。
では、肝臓がんの基本的な知識や症状、原因、予防方法について詳しく解説していきます。
肝臓がんの主な症状
肝臓がん(肝細胞癌)は初期症状が乏しく、早期発見が難しい疾患です。
比較的進行した段階になると、以下の症状が出現することが多く、注意が必要です。
・腹痛
・食欲不振
・体重減少
・腹部膨満
・黄疸(皮膚や眼球が黄色くなる)
これらが見られた際には、速やかに医療機関へ相談することが推奨されます。日本では肝炎ウイルス感染や慢性肝障害を背景に肝がんが発生する例が多く、さらに進行すると外科的切除が難しくなることがあります。そのため、定期的な肝機能検査や超音波検査を受けることが重要です。
近年は免疫療法や分子標的薬など新しい治療が導入され、臨床試験を経て標準治療と呼ばれるようになっています。ただし、大きな病変や肝機能障害の程度によっては効果が限られる場合もあるため、早期診断・早期発見が重要であり、定期検査の継続が将来の予後を左右します。症状の有無にかかわらず、体調に不安を感じた場合は早めに担当医に相談し、適切な専門医療を受けることをおすすめします。
予防と診断
肝臓がんは、肝炎ウイルスの感染やアルコール性肝疾患、非アルコール性脂肪肝症、肝硬変など、複数の要因が複雑に絡み合って発症する病気です。
特にB型やC型といった肝炎ウイルスに感染すると肝機能が低下しやすく、周囲の肝細胞が変性を起こしてがん化しやすい特徴があります。
予防のためには、肝炎ウイルスの感染予防や適度なアルコール摂取を心掛けるほか、日頃から生活習慣を整え、定期的に肝胆科や消化器科で検査を受けることが重要です。
肝臓がんは早期段階で症状が出にくく、発見が遅れると血管造影で脈を確認した際に大きな腫瘍が判明するケースもあります。とくに約3cm以上のサイズにまで成長すると、肝移植やrfa(ラジオ波焼灼術)を検討することも増えてきます。
生体肝移植は一部の医療機関で実績が高い治療法として確立されつつあり、保険適用の有無や対象範囲などは病院や専門サイトのページを参照するとよいでしょう。なお、肝移植や陽子線・重粒子線といった先進的な治験には、適応条件や人数が限られる場合があります。
肝癌を予防するうえで特に考慮したいのは、ウイルス感染の管理です。B型肝炎やC型肝炎が疑われる人は、治療薬を使った適切なウイルス抑制を進めることが推奨されます。また、アルコールの摂取量を適度以内に抑え、脂肪肝や肥満を防ぐことも大切です。食事メニューの見直しや運動習慣の導入は、肝機能の維持に寄与します。 検査としては、次のような項目が代表的です。
・血液検査:肝炎ウイルスの有無や腫瘍マーカーを確認します
・超音波検査:肝臓の状態をリアルタイムで観察でき、侵襲が少なく安全です
・CT・MRI:造影剤を使用して詳細な画像を撮り、周りの血管や腫瘍の中心部を評価します
・生検:必要に応じ、針を刺して組織を採取し、確定診断を行います
・血管造影:動脈に注を行い、がんへの血流や脈動を把握し、治療方針を決めます
治療法としては、手術やカテーテル治療、さらには抗がん剤や免疫阻害薬の活用があります。なお、治療方針を決める際は主治医やスタッフと十分に相談し、個数や腫瘍の分け方など患者ごとに状況を見極める必要があります。最新ガイドラインも検索し、最新の案内を知ることが望ましいです。周りや周囲のサポートを受けながら、自分に合った治療を選択し、早期から継続的なフォローアップを進めていくことが、肝癌克服への大きな一歩となります。
2.肝臓がんの治療方法
肝臓がんの治療法には、手術、放射線治療、化学療法、分子標的治療などがあります。治療法の選択は、患者のがんの進行状況や肝機能、全身状態などを考慮して行われます。
選択のポイントには以下のものが挙げられます。
- がんの進行状況: 早期であれば手術や局所治療が選択されることが多いです。
- 肝機能: 患者の肝機能によって適切な治療法が選択されます。
- 全身状態: 患者の体力や持病、年齢なども治療選択に影響します。
最適な治療法は、医師と患者が十分に話し合った上で決定されることが望ましいです。
手術による切除療法
肝臓がんの治療法の中でも、外科的に腫瘍を切除する方法は大きく症状を改善する可能性があります。そのため進行度によりますが、肝臓がんに対する基本的な治療としては外科手術による切除が挙げられます。
外科的に腫瘍部分を取り除くことで、体全体のがん細胞の数を大きく減らせる可能性があります。肝臓へは門脈と動脈の両方から血流が供給されるため、切除時にはそれらの管を適切に処理する必要があります。肝臓組織は出血しやすい特性を持つため、切除範囲を決定する際には、腫瘍の数や体への影響度、外の臓器への転移の有無などを総合的に評価し凝固を促す装置などを用いながら丁寧に切開を行います。大きく切除しすぎると体への負担が増すため、限られた範囲の外科切除が推奨される場合も多いです。
腫瘍の位置や広がりを正確に把握するために、画像診断を綿密に行ったうえで適切な切除範囲を決定します。
穿刺局所療法
穿刺局所療法は皮膚を通じて直接がん組織に針を挿入し、ラジオ波やマイクロ波などで焼灼を行う治療法です。
ラジオ波焼灼療法では、ラジオ波エネルギーを用いて腫瘍組織を熱凝固させ、がん細胞を死滅に導きます。極めて細い専用の管を用いて腫瘍部位を狙い撃ちするため、外科的な切開以外でがんを破壊でき、正常組織への損傷を軽減できる点が特徴です。局所麻酔下で実施できるケースも多く、体にかかる負担を抑えやすい方法のため、特に腫瘍の数が少ない場合や、手術が難しい方に適した治療手段といえます。小さめの肝臓がんに適していますが、腫瘍の位置や動脈との関係などによっては適用が制限されることがあります。
塞栓療法
塞栓療法とは、腫瘍を栄養する動脈に細いカテーテルを通し、塞栓物質を注入して血流を遮断する方法です。肝臓のがん組織は動脈を栄養の経路とし、ここからの血流に強く依存するため、この経路を塞ぐことでがん細胞を弱体化できます。門脈領域からの血流は残るため、正常組織へのダメージを最小限に抑えやすい利点があります。さらに、化学物質を同時に注入する化学塞栓療法も行われることが多いです。塞栓療法は外来で実施可能なケースもあり、身体への負担が比較的少ないため、腫瘍が大きく広がったような外科手術が難しい患者さんにも選択肢が広がります。
化学療法
抗がん剤治療は、体の中に薬剤を投与することでがん細胞の増殖を抑制する治療です。局所療法だけでは対処しきれない複数病変を持つ場合にも適用されます。近年は分子標的薬など新しい薬剤が開発され、従来の治療に比べ効果と安全性のバランスが大きく改善しており、患者の予後を大きく改善する選択肢が増えています。組み合わせによっては抗がん剤治療だけでなく、塞栓療法や焼灼などと併用して総合的にアプローチすることも行われます。
3.他臓器への影響
肝臓がんは、肝臓の機能低下や腫瘍の進行により、他の臓器にも影響を与えることがあります。
- 隣接する臓器への転移: 胆のうや膵臓、大腸など
- 腹水や黄疸: 肝機能の低下や閉塞性黄疸により発生
- 肺や骨への転移: 肝臓がんが血管内に侵入し、全身に転移
肝臓がんの早期発見と適切な治療で、患者の生活の質(QOL)や生存期間の延長が期待できます。家族や医療チームのサポートも大切です。
肝臓がんは、進行すると他の臓器に転移する可能性があります。転移先の一般的な臓器は肺、大腸、骨です。転移が発生する理由は、がん細胞が血管やリンパを通じて他の部位に移動し、そこで増殖することによります。
転移のリスクを早期に把握するため、定期的な検査が重要です。CTスキャンやMRI、血液検査などの検査方法が用いられます。また、症状が現れた場合、迅速に医療機関で診察を受けることが必要です。
転移を防ぐための治療方法は、がんの進行を抑えることが最も効果的です。手術による切除、化学療法、放射線療法など、病状と患者の体調に応じた適切な治療を選択することが大切です。
転移が疑われる場合、できるだけ早く治療を開始することが生存率を向上させる上で重要です。医師とよく相談し、最善の治療方法を選択しましょう。
肝臓がんに伴う合併症の対処
肝臓がんに伴う合併症には、以下のようなものがあります。
- 肝不全
- 腹水
- 急性出血
- 胆道閉鎖
これらの合併症に対処するためには、まず医師と密接に連携し、症状の変化に対応することが重要です。また、適切な治療やケアを受けることで、症状の悪化を抑えることができます。
例えば、肝不全の場合は肝臓の機能をサポートする薬物療法や食事療法が行われます。腹水に対しては、利尿剤や腹水の除去手術が適用されることがあります。急性出血の場合は、内視鏡処置や止血対応が行われます。胆道閉鎖は、内視鏡的にステントを挿入する手術や胆道バイパス手術が行われます。
適切な対処法を選ぶためには、医師との相談が不可欠です。自己判断で対処せず、医師に診断を受けましょう。
合併症と肝機能の維持方法
肝臓がん患者の合併症と肝機能の維持方法には、以下のような対策があります。
- 適切な治療:手術、化学療法、放射線療法など、肝臓がんの病状に応じた治療を選択し、適切に行うことで合併症を防ぐことができます。
- 定期的な検診:肝機能検査や腫瘍マーカー検査を定期的に受けることで、早期に問題を発見し、治療につなげることができます。
- 食事療法:食事療法を行い、栄養バランスの良い食事を摂取することで、肝機能の維持に役立ちます。医師や栄養士と相談して、適切な食事療法を決定しましょう。
- アルコールの摂取制限:肝臓がん患者にとって、アルコール摂取は肝臓への負担を増やすため避けることが望ましいです。
- 薬物の管理:肝臓がん患者は、医師の指示に従い、適切な薬物を管理しましょう。
- 心身のケア:心身のストレスを軽減することで、病状の悪化や合併症を防ぐことができます。リラクゼーション法や適度な運動を取り入れましょう。
これらの方法で、合併症と肝機能の維持が可能です。医療専門家と連携して、自身の状態に合った対策を取りましょう。
4.患者へのケア
肝臓がん患者のケアは、病気を抱える患者本人だけでなく、家族にとっても重要な役割です。家族がサポートするポイントは以下の通りです。
- 医療情報の共有:家族が医師からの説明や治療方針を理解し、患者と共有することで、治療に対する理解と安心感を得られます。
- 病状の観察:家族が患者の症状や体調の変化を観察し、医師への報告に繋げることで、適切なケアが行われます。
- 食事や薬物管理のサポート:家族が食事療法や薬物管理のサポートを行うことで、患者の肝機能維持や症状の改善に役立ちます。
- 心のケア:家族が患者とのコミュニケーションを大切にし、精神的サポートを提供することで、患者の心身の負担を軽減できます。
- 介護・生活サポート:家族が患者の日常生活や介護に協力することで、患者の体力温存や生活の質の向上に繋がります。
患者本人と家族が協力し合い、医療専門家と連携しながら適切なケアを実践することが、肝臓がん患者のケアと家族のサポートになります。
医療チームとの密接な連携
医療チームと患者の密接な連携は、がん治療において非常に重要です。理由は、医療チームの専門家たちがそれぞれの分野で最適な治療方法を選択し、病状や症状に応じて連携が行われることで、患者の生存率やQOL(Quality of Life)が向上するためです。
具体的には、病院の医師や看護師、薬剤師、栄養士、臨床心理士などが連携して診療に当たります。また、腫瘍の大きさや進行度、治療負担を最小限に抑えることを考慮することが重要です。さらに、患者や家族との十分な情報共有やサポートも行われます。
患者と家族の心のケア方法
患者と家族の心のケア方法は、がん治療において大切な要素の一つです。以下に代表的なケア方法を挙げます。
- カウンセリングや相談支援:心のケア専門家(臨床心理士、精神科医など)が、患者や家族の不安や悩みに寄り添い、適切なアドバイスを提供します。
- サポートグループ:同じ病気を抱える仲間と交流し、経験や知識を共有することで、互いに助け合い、心の支えとなることが期待できます。
- 緩和ケア:痛みや副作用を軽減し、患者の生活の質を向上させることを目的としたケアです。緩和ケアは、患者や家族の心の安定にも繋がります。
- 精神的サポート:家族や友人からの声かけや連絡、病院での心のケアや催し物なども、患者の心のケアに役立ちます。
5.肝臓がんのまとめ
肝臓がんには肝細胞癌や肝内胆管がんなどが含まれ、ステージや腫瘍の場所、患者の全身状態によって治療の選択肢が異なります。日本の診療ガイドラインにおいては、手術やラジオ波焼灼療法、塞栓療法などが標準的な治療として推奨されており、近年は免疫療法や分子標的薬も導入されつつあります。
いずれの治療を行う場合でも、慢性肝炎や肝硬変など基礎疾患があるかどうかを含め、肝機能障害の程度を十分に評価することが大切です。 早期診断と適切な治療により、予後や生活の質が大きく変わります。
特に腫瘍が小さい段階で見つかれば、切除や局所療法が有効で、比較的良好な経過が期待できます。定期的な超音波検査や血液検査を受けることで、肝細胞がんの早期発見に繋げることが望ましいです。
治療方針を決定するときは、患者さんやご家族が十分に納得したうえで行うことが重要です。 最後に、治療とともに心のケアや生活面でのサポートを得ることで、不安を軽減し前向きに治療へ臨むことができます。主治医や家族と連携し、十分な情報をもとに行動することが重要です。
※この記事は2024年4月29日に作成され、2025年6月16日に内容を更新しました。

快適医療ネットワーク理事長
監修
医学博士 上羽 毅
金沢医科大学卒業後、京都府立医科大学で研究医として中枢神経薬理学と消化器内科学を研究。特に消化器内科学では消化器系癌の早期発見に最も重要な内視鏡を用いた研究(臨床)を専攻。その後、済生会京都府病院の内科医長を経て、1995年に医院を開業。
統合医療に関する幅広し知識と経験を活かして、がんと闘う皆様のお手伝いが出来ればと、当法人で「がん患者様の電話相談」を行っております。