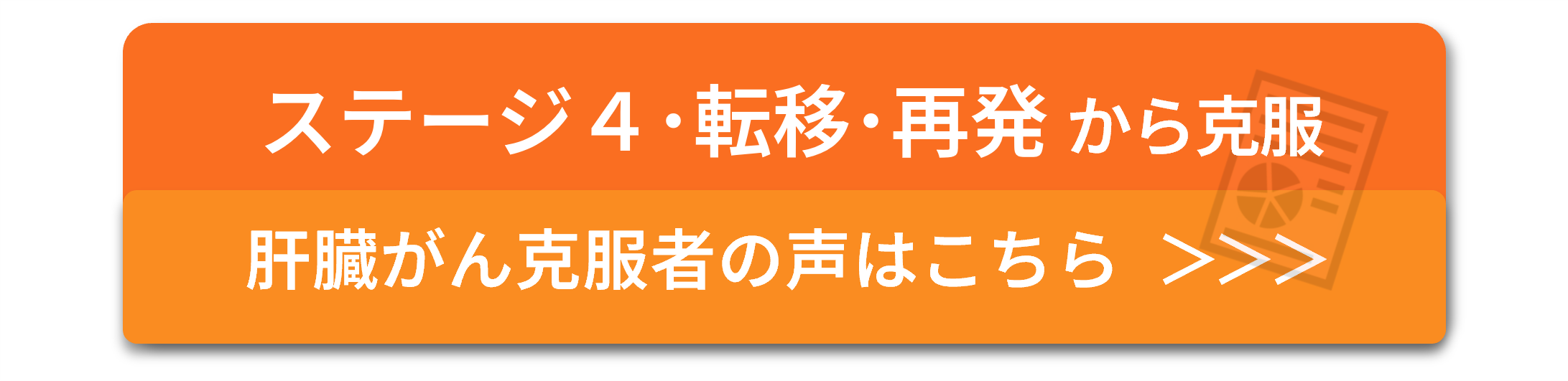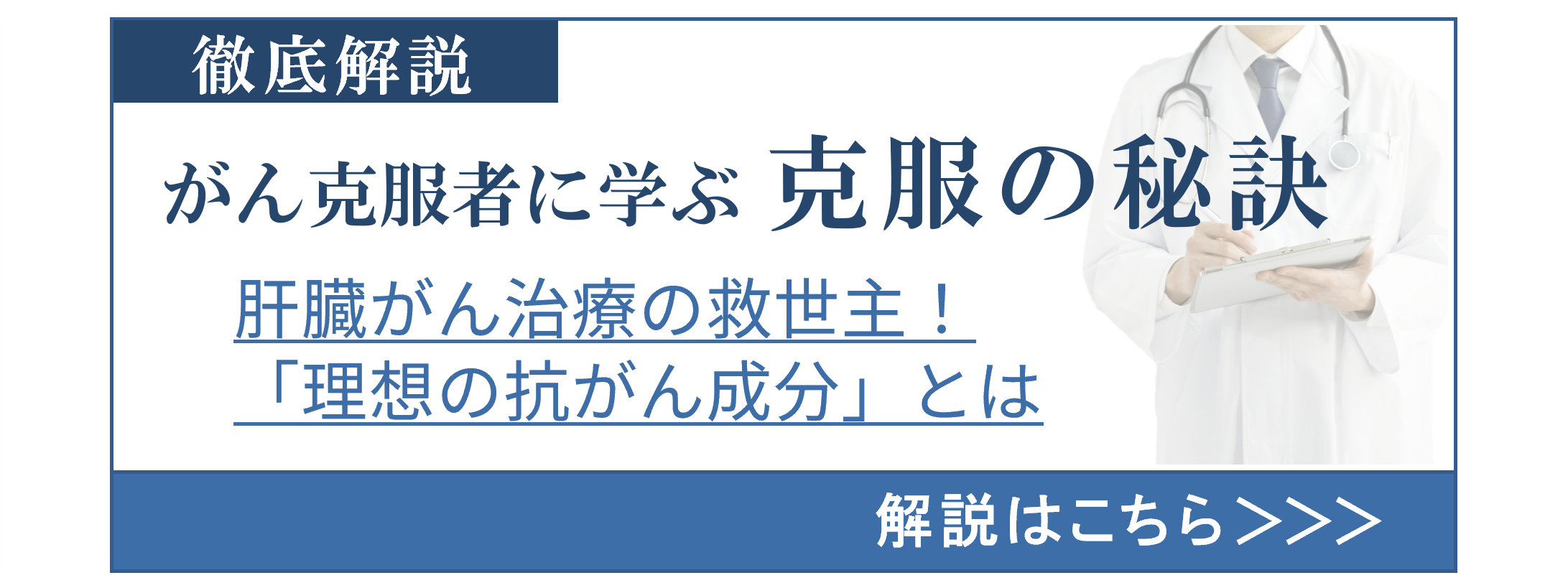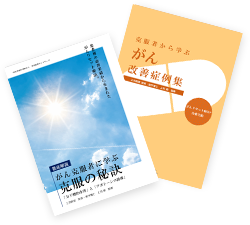- 2025.03.14
- 肝臓がん
肝臓癌の抗癌剤治療~最新薬と副作用を知る~
肝臓がんは「沈黙の臓器」と呼ばれる肝臓に起こるがんで、病変がかなり進行するまで目立った自覚症状が出にくいのが特徴です。B型やC型の肝炎ウイルス感染、アルコール性肝障害、化学物質への長期曝露など複数の要因が重なり、長期間の慢性肝障害を経てがん化へと至るケースが多く見られます。気づいた時にはすでにステージが進んでいる場合も少なくなく、治療選択を検討するときには、その進行度や転移状況が大きな懸念材料となるでしょう。
近年は、治験や臨床試験の成果により、新しいタイプの分子標的薬や免疫療法、先進的な放射線治療などが次々に登場しています。とくに2019年以降、ラムシルマブをはじめとする薬剤への注目度が高まり、骨や肺への転移にも対応する多角的なアプローチが研究・開発されているのが現状です。本稿では、肝臓がんが持つ特性を押さえながら、日本における代表的な治療法や制度面のポイント、治験の意義などを幅広く紹介します。患者さんやご家族が治療を検討する際の参考となるよう、5つのセクションに大きく分けて解説します。
1.肝臓がんの基礎知識
肝臓は、栄養の代謝や有害物質の解毒、胆汁の生成など多彩な機能を担う生命維持に欠かせない臓器です。組織構造の特性上、異常が起きても気づきにくく「沈黙の臓器」と呼ばれます。このため、肝臓がんの初期段階ではほとんど症状が出ません。肝臓がんには、肝細胞がんなど肝組織そのものから生じる原発性と、胃や大腸など他の臓器からがん細胞が移行する転移性が存在します。B型・C型肝炎ウイルスやアルコール性炎症、脂肪肝炎などが慢性的に続くと、肝細胞の変性・がん化が起こりやすいです。
早期発見とリスク要因
肝臓がんは進行するまで自覚症状が乏しく、疲労感や食欲不振といった軽微な異変も見逃されがちです。定期的な健康検査が非常に重要になります。特に血液検査や腹部エコー、CT、MRIを組み合わせた検診は、がんを小さい段階で捉える助けになります。下記に挙げる要因を持つ方は、より注意が必要です。
●B型肝炎ウイルスのキャリア
●C型肝炎ウイルス感染
●過度なアルコール摂取
●非アルコール性脂肪肝炎(NASH)
●化学物質や毒素への長期接触
がんが小さいうちに発見されれば、外科的切除や局所療法など複数の治療オプションを検討しやすくなります。また、診断時に骨や肺への転移が認められる場合もあるため、総合的なフォローアップの質が治療成果に大きく関わります。さらに、肝硬変や慢性肝炎を抱える方は、主治医の指示に従い、定期的な経過観察やウイルス治療の継続を行うことが望ましいです。生活習慣の改善、適切な栄養管理、そして禁酒の徹底なども肝機能の維持には不可欠でしょう。近年は、肝臓がんの治療手段も進化し、ラジオ波焼灼術や分子標的薬など新しいアプローチが存在します。とはいえ、いずれも早期に疾患を見つけるほど効果が高まりやすいため、定期的な検査や日頃からの体調管理は欠かせません。
2.治験と新薬開発 ~日本における最新動向~
肝臓がん治療は、近年急速な進歩を遂げています。新薬や新しい治療法を実用化する際は、国の認可を得るために欠かせない治験が行われます。治験とは、薬の安全性と有効性を検証する最終段階で、患者さんは専門スタッフの厳重な管理下で治療を受け、定期的に経過を観察されながら慎重に進められています。2019年以降、分子標的薬や免疫療法薬の開発が加速し、ソラフェニブやレンバチニブだけでなく、血管新生阻害のメカニズムを持つラムシルマブに期待が高まっています。保険適用された薬剤は公的に有効性と安全性を認められたものですが、実際の処方では肝機能や既往歴、副作用など多角的な検討が必要です。
治験に参加するメリットとリスク
最新の治験に参加すると、まだ一般には使われていない薬を試す機会があります。反面、未知の副作用や治験スケジュールへの適応など、負担が増す可能性もあります。参加を考える際は、医療スタッフとの対話を重ねて自分の生活背景や家族の協力体制を確認しましょう。
●早期に新薬を利用できるチャンス
●注意深い観察が受けられる安心感
新薬開発の広がり
臨床試験が重ねられるほど肝臓がんの治療選択肢は増えます。遠隔転移がある場合でも、分子標的薬による腫瘍の成長抑制や免疫療法の活用が進み、放射線との併用で相乗効果を狙う治療も模索されています。
●血管新生阻害薬の適用で腫瘍増殖を抑制
●免疫療法との組み合わせで多面的な治療戦略
今後も新薬が治験を通じて承認されれば、従来の治療では対応が難しかった症例にも光が差します。治験と新薬開発の進歩が、より多くの患者さんに適切な治療を届ける基盤となるでしょう。
3.主要な治療アプローチと選択肢
肝臓がんの治療は、腫瘍の大きさや数、肝機能の状態、転移の有無などによって最適な手段が異なります。ここでは代表的な治療アプローチを整理し、それぞれの特徴を解説します。
外科的治療と局所療法
外科的手術(肝切除)は、病変が肝臓内で限局している場合に大きな選択肢となります。肝機能に余裕があり、腫瘍数が比較的少ないケースでは、腫瘍を切除して完治を目指すことも可能です。また、肝移植は肝硬変が重度で移植に適応する患者さんにとっては有力な候補ですが、ドナーの確保などハードルが高いのが現実です。
局所療法としては、以下の方法が代表的です。
●ラジオ波焼灼術(RFA):特殊な針で高周波エネルギーを与え、がん細胞を焼灼
●塞栓療法(TACEなど):がんへ栄養を供給する血管を塞ぎ、腫瘍への血流を遮断
いずれも腫瘍の大きさや数に制限があり、転移がある場合や腫瘍が広範囲にわたる場合には、単独では効果が限定的な場合があります。とはいえ、局所療法を組み合わせることで症状をコントロールする重要な役割を担うため、ステージに応じては第一選択肢になることもあります。
化学療法と分子標的薬
全身的に作用する化学療法は、腫瘍の広がりが大きい場合や転移病変が複数あるケースで検討されます。従来型の抗がん剤は、骨髄抑制や消化器症状などの副作用が一般的で、副作用へのケアが非常に重要です。肝機能が低下している患者さんでは、投与量や頻度を慎重に調整する必要があります。
近年は、分子標的薬が肝臓がん領域で大きな注目を集めています。ソラフェニブ、レンバチニブなどに加え、2019年以降はラムシルマブが注視されています。これらは血管新生を抑制し、がん細胞への栄養供給を断つメカニズムで効果を発揮します。また、免疫療法薬との併用など、新たな組み合わせも研究が進んでおり、多様な治療戦略の柱となっています。
肝動注化学療法と全身化学療法の違い
肝動注化学療法は、カテーテルを肝動脈に直接挿入し、高濃度の抗がん剤を患部に集中して届ける方法です。腫瘍への局所効果は期待できますが、患者さんの血管や肝機能の状態によっては実施が難しい場合もあります。
一方、点滴や内服による全身化学療法は、転移が広範囲に及んでいる際に検討されやすい選択肢です。ただし、副作用のコントロールが課題であり、外来通院であっても血液検査や体調管理を頻繁に行う必要があります。患者さんそれぞれの状態や希望をもとに、最適な治療計画を立てることが重要です。
4.医療体制と生活面の配慮
肝臓がんの治療は、長期的な管理や再発の可能性を見据えながら進める必要があります。入院と外来のどちらが良いかは、治療内容や患者さんの生活状況、サポート体制などを考慮し、医療者と話し合いを重ねて決めると安心です。ここでは治療費や公的支援制度、医療機関の選び方などを含めた生活面の配慮について触れます。
入院治療と外来治療
手術や肝動注化学療法、集中管理が必要な放射線治療などは入院での実施が多いです。術後の回復や副作用対策を医療スタッフが手厚くフォローできるメリットがある一方、入院費や仕事・家庭への影響は小さくありません。
分子標的薬や一部化学療法では、外来通院での治療が可能な場合もあります。通院頻度が高くなることもありますが、入院ほど生活のパターンを変えずに済む利点があります。主治医や看護師と相談しながら、外来でも安全に治療を継続できるかどうかを検討しましょう。
治療費と公的支援制度
肝臓がん治療は、多彩な選択肢を組み合わせるほど費用がかさむ傾向があります。日本では健康保険制度のほか、以下のような支援制度を利用できます。
●高額療養費制度:一定額を超えた医療費が払い戻される
●医療費控除:確定申告で医療費の一部を所得から控除
●難病指定の申請:適応となる疾患の場合、負担額軽減が可能
治験に参加する場合、薬剤費の一部負担が減るケースもありますが、通常診療にかかわる費用など全てが免除されるわけではありません。経済面に不安があれば、病院のソーシャルワーカーや各種相談機関に問い合わせ、制度活用の方法を検討すると良いでしょう。
医療機関の選択とチーム医療
肝臓がんはさまざまな治療法が存在し、それらを組み合わせることで効果を高められる可能性があります。以下の観点で医療機関を検討すると安心です。
●手術実績や肝移植など外科的治療の経験
●局所療法(ラジオ波焼灼術、肝動脈塞栓など)の症例数
●先進的な放射線治療機器の有無(重粒子線、陽子線など)
●最新の分子標的治療や免疫療法への対応力
●治験や臨床試験に積極的であるか
●患者さんへの説明やサポート体制の充実度
複数の意見を聞きたい場合は、セカンドオピニオンを活用するのも良い方法です。医師によって治療の得意分野や重視する観点が異なるため、納得のいく判断をするための材料を集める意味でも、積極的に利用しましょう。
5.再発と転移に向き合うために
肝臓がんは、一度治療が成功しても再び発症しやすいがんの一つとして広く知られています。慢性的に障害を受けた肝臓では、新たながん細胞が発生するリスクが消えません。また、骨や肺などへの転移が見つかった場合には、放射線治療や分子標的薬など複数のアプローチを組み合わせることも検討されます。表面的には病変が落ち着いているように見えても、慢性肝炎や肝硬変などの基礎疾患があるときは特に注意が必要です。
再発リスクを考慮した定期検査の重要性
再発や転移を早期に捉え、適切な治療方針に切り替えるには、定期的な画像検査や血液検査を欠かさないことが大切です。特に腫瘍マーカー(AFPやPIVKA-IIなど)のわずかな変動にも敏感になり、主治医に相談する姿勢が望まれます。再発した場合は初回治療と異なる方法を試すことがあり、局所療法が再度適用できるケースも考えられます。肝臓がんは長期的なフォローアップが求められるため、専門医とのコミュニケーションを継続し、常に身体の状態を把握しておきましょう。
生活習慣の見直しと多職種連携
肝機能を保ちながら治療を続けるには、生活習慣を整えることが避けて通れません。具体的には、次のようなセルフケアが推奨されます。
●アルコール摂取をできるだけ控える
●塩分や脂肪分の多い食事を過度にとらない
●無理のない範囲で適度な運動を取り入れる
治療によって体力が大きく消耗していると感じる場合は、リハビリスタッフや管理栄養士など多職種と連携しましょう。個々の体調に合わせて運動量や食事内容を調整することで、肝臓への負担を減らしながら効率的に体力を回復させる道筋が見えてきます。
個々の状況に合わせた治療計画
肝臓がんには多彩な治療オプションがあり、患者さん自身の希望や暮らしの背景をふまえた意思決定が欠かせません。近年、新薬や治験の候補が着実に増え、かつては難しいと考えられていたステージにも、複数の専門家の知恵を集めることで思わぬ打開策が得られる場合があります。特に再発や転移を想定するうえでは、患者さん自身が納得できる治療計画を作り、身体の状態を継続的にチェックしていくことが重要です。
一人で不安を抱え込むのではなく、家族や看護師、医師、時にソーシャルワーカーや専門チームと連携することが治療の負担を軽減します。入院で集中的に治療を行う方針もあれば、外来通院を続けながら日常生活を維持する方法もあり、患者さんの状況や希望に合わせて選択肢を柔軟に検討することが大きなポイントです。
肝臓がん治療の新たな展望
肝臓がんは早期発見が難しく再発リスクも高い病気ですが、近年は分子標的薬であるラムシルマブや免疫療法、さらに放射線治療技術の進歩などが注目され、ステージに応じて新旧のアプローチを組み合わせながら治療方針を模索する動きが広がっています。以下の点が治療の幅を広げるうえで大きな鍵となります。
●治験や先進医療を活用し、新薬へアクセスする道を探る
●公的補助制度を利用し、医療費の負担を軽減する
●長期戦を想定し、肝臓がん特有の性質を深く学び理解を深める
●場合によっては外科手術や局所療法を併用し、多角的に再発率を抑える
患者さんが主体となって治療を築くには、さまざまな手段を組み合わせつつ、こまめなフォローアップを続けることが欠かせません。最新の技術や薬剤情報にアンテナを張り、一人ひとりに合ったプランを導き出す姿勢が大切です。治療には時間や費用がかかる現実はありますが、選択肢を広げることで突破口を見いだすチャンスが増すでしょう。

快適医療ネットワーク理事長
監修
医学博士 上羽 毅
金沢医科大学卒業後、京都府立医科大学で研究医として中枢神経薬理学と消化器内科学を研究。特に消化器内科学では消化器系癌の早期発見に最も重要な内視鏡を用いた研究(臨床)を専攻。その後、済生会京都府病院の内科医長を経て、1995年に医院を開業。
統合医療に関する幅広し知識と経験を活かして、がんと闘う皆様のお手伝いが出来ればと、当法人で「がん患者様の電話相談」を行っております。