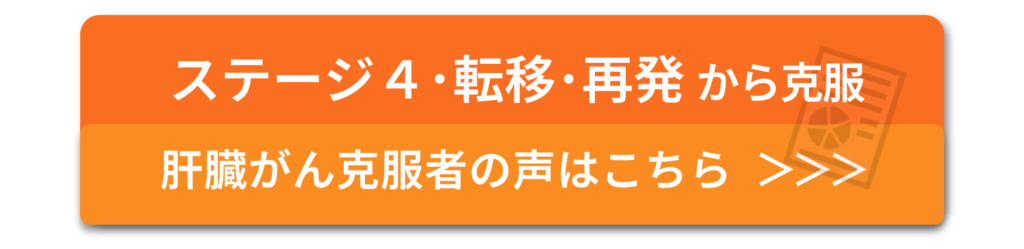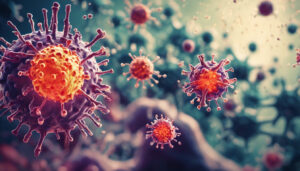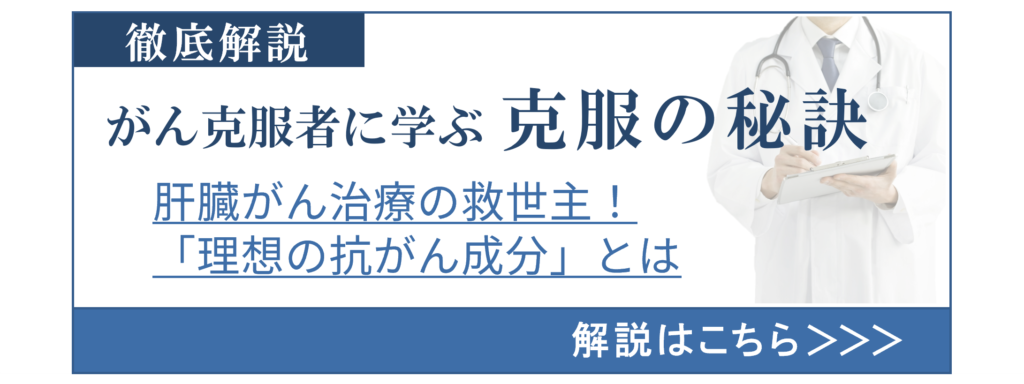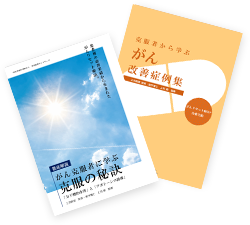- 2025.06.11
- 肝臓がん
肝臓がんの原因・飲酒や喫煙との関係とは ~沈黙の臓器の異変~
肝臓は、私たちが口から食べ物を食べて得た栄養や、飲酒によって摂取したアルコールを分解する上で欠かせない臓器です。ところが「沈黙の臓器」とも呼ばれるように、初期段階では病気のサインが分かりにくく、気づいたときには肝臓がんへ進行しているケースが珍しくありません。若い人も例外ではなく、特に30代からは生活習慣が積み重なり始めるため、油断してはいけません。
肝臓がんの大きな要因の一つが、B型やC型肝炎ウイルスです。ウイルスに感染すると肝細胞に慢性的な炎症が起こり、それが長期にわたると細胞の変異を促し、がんのリスクが高まります。そこに過度な飲酒や肥満、糖尿病などの要素が加わると、相乗的に肝臓を痛めてしまうことがあります。お酒を飲むと肝臓はアルコールを分解しようと働きますが、過剰に摂取すると肝細胞が疲弊し、結果としてがん発症の可能性が高まるのです。
肝臓がんの予防や早期発見のためには、定期的な血液検査や画像診断が重要です。CTやMRIなどは肝内部の微細な変化を捉えることに役立ち、早期治療を開始すれば、比較的治る見込みを高めることも可能です。さらに日々の生活習慣の見直しが鍵となります。アルコール摂取を控え、栄養バランスに配慮した食べ物を意識して食べ、自然な範囲の運動を取り入れると肝臓を守るうえで大きな効果があります。
肝臓が正常に働くためには、さまざまな要素が相互に影響し合っています。放置してはいけない症状を見逃さず、少しでも違和感を覚えたら専門医を受診し、適切な診断と治療につなげることが大切です。忙しい現代社会でも、自分や家族を守るために肝臓のケアを意識し、早めに予防と対策を進めることで、健康な未来に近づけます。
1.肝臓癌の特徴と傾向
肝臓は脳に次いで大きな臓器であり、全身の代謝や解毒、胆汁の生成、栄養の貯蔵など多くの役割を果たします。肝臓の細胞は一部損傷を受けても、他の細胞が代わりに働く予備能力が高く、かなり進行しない限り症状が現れません。この高い代償機能のため、「沈黙の臓器」と呼ばれ、病気の発見が遅れる原因となります。
進行した肝臓がんでは、腹部のしこりや黄疸、腹水など深刻な症状が出ますが、それまでは倦怠感や軽い違和感など目立たない症状にとどまります。多くは発見時点で治療が難しい状態まで進行しています。自覚症状が現れてから病院を受診するケースも多く、特に酒を頻繁に飲む方、脂肪肝や糖尿病、肝炎ウイルスに感染している方は早めの検査が大切です。女性にも、生活習慣病やウイルス感染による発症が増えているため、性別に関わらず注意が必要です。
肝臓がんの多様な種類と特徴
肝臓がんは大きく原発性と転移性の二つに分類され、それぞれに明確な違いがあります。
原発性のなかでも肝細胞がんはB型・C型肝炎ウイルスをはじめ、過度な飲酒や脂肪肝、糖尿病など多彩な要因が重なり合って発症へと進むケースが多いです。肝臓はアルコールを分解する主要な役割を担いますが、若い人でも無理を重ねれば機能低下につながる可能性があるため油断できません。転移性肝がんは他臓器のがんが血液やリンパを介して肝臓へ達するため、早期発見が難しいのが特徴です。
肝臓がんは初期症状が乏しく、気づかぬまま進行しやすいです。進行すると黄疸や腹水、食欲低下といった症状が現れますが、適切な治療を行えば治る望みがまったくないわけではありません。検査には腹部超音波(エコー)やCT、MRIなどが用いられ、AFPやPIVKA-IIなどの腫瘍マーカーを調べる血液検査も重要です。これらを併用することでがんの位置や大きさ、周囲への広がりを把握し、最適な治療方針を立てることが可能です。
生活習慣においては普段の食べ物や飲酒量に注意を払う必要があります。飲み過ぎや深夜の暴飲暴食はいけません。脂肪肝や肝炎のリスクを増大させないためにも、食べ過ぎを避け、自然に近いバランスの良い食生活を心がけることが肝要です。
治療法の選択はがんの種類や進行度、肝機能の状態によって異なります。定期検査や早期診断を徹底すれば、予後改善につながる可能性がありますので、症状がなくても定期的にチェックを受けることをおすすめします。
日本人に多い肝臓がんの傾向とは
日本では、肝臓がんの主な原因はC型肝炎ウイルスとB型肝炎ウイルスの慢性感染です。これらは長い時間をかけて肝硬変や慢性肝炎を引き起こし、その後がんに進展します。他にも、酒(アルコール)を長期間多量に摂取している人、最近急増している脂肪肝由来のNASH(非アルコール性脂肪性肝炎)が要因となる例も増加しています。
高齢化や生活習慣病の増加に伴い、肝臓がんを引き起こすリスク因子も多様化しています。従来は男性に多い病気とされてきましたが、女性も脂肪肝や糖尿病など現代的なリスクを持つ場合が多くなっています。
肝臓がんの発症リスクを下げるためには、肝炎ウイルスに感染していないかどうかの確認、酒を控える生活習慣の見直し、肥満や糖尿病を早めに治療することが重要です。特に検診や人間ドックで肝機能異常を指摘された場合は、医療機関で詳しい画像診断や血液検査を受けてください。
2.肝臓癌の主な原因とは?
肝臓がんの主な誘因は、C型・B型肝炎ウイルスの長期感染です。ウイルスが長期間にわたり肝細胞に住みつくことで、慢性炎症→肝細胞の再生&修復→遺伝子異常→がん化、という悪循環が繰り返されます。
●母子感染
●輸血や注射器の共用
●性行為
●針刺し事故
といった経路でウイルスに感染する場合があります。無症状のまま長期間キャリアとなっていることも多く、特に酒をよく飲む人や、脂肪肝・糖尿病などの生活習慣病を持つ人は要注意です。
B型・C型肝炎ウイルスによる肝臓がん発症の流れ
ウイルスに感染すると、免疫の働きによる炎症と肝細胞修復が繰り返されます。炎症が長期間続くことでDNA損傷が蓄積しがん化しやすくなります。B型・C型肝炎の進行はゆっくりですが、長期キャリアでは肝硬変・肝臓がんのリスクが年々高まります。
治療方法も進化しており、C型肝炎にはインターフェロンフリー治療、B型肝炎には核酸アナログ製剤の内服薬でウイルス増殖を抑制し、がん化のリスク軽減が期待できます。女性もB型肝炎ウイルスのキャリアが多く、性別に関係なく定期検査が重要です。
アルコール(酒)摂取がもたらす肝臓への影響
酒を長期間大量に飲み続けると、肝細胞が慢性的なダメージを受け、脂肪肝→アルコール性肝炎→肝硬変と進展します。肝臓の代償機能により一時は症状が出にくくても、細胞修復の繰り返しで遺伝子変異やがん化につながる危険性があります。
また、アルコールは脂肪肝や急性の下痢を誘発することがあり、肝臓が弱ることで女性にも腹部症状や消化器症状が出る場合があります。酒を控えることが、肝臓がんのリスク低減や治癒への近道となります。
脂肪肝と肝臓がんリスクの増加
脂肪肝は現代の食生活や運動不足によって急増している疾患です。脂肪が過剰に蓄積した肝臓は炎症を起こしやすく、NASHなど進行した状態では肝硬変や肝臓がんへのリスクが跳ね上がります。
脂肪肝はお酒を飲まない女性でも発症し、さらに糖尿病や肥満といった基礎疾患と重なることで、がん発症率が上昇します。脂肪肝の段階から生活習慣を改善・体重管理を心がけ、定期的な検査を行うことが重要です。
糖尿病・肥満と肝臓がんのつながり
糖尿病や肥満は肝臓内の代謝異常や炎症を誘発し、慢性的な細胞障害が起こります。肝臓がん患者の多くは、こうした基礎疾患を持ち合わせている場合が多く、男女ともに無視できません。
血糖コントロールや適正体重の維持、生活習慣病の治療が、肝臓がんのみならず他の生活習慣病やがんの治癒にもつながります。
3.肝臓癌の代表的な兆候と予防
肝臓がんになりやすい人には、いくつか共通点があります。
●B型・C型肝炎ウイルスキャリア
●過去に肝炎・肝硬変を指摘されたことがある
●酒をよく飲む(アルコール多飲歴)
●肥満または脂肪肝・糖尿病がある
●家族に肝臓がんの人がいる
これらに当てはまる場合、特に女性でも見逃されがちなので、必ず定期検査を受けてください。初期には下痢や倦怠感、食欲不振などの軽い症状から始まることもあります。異常を感じたら早めの診断が重要です。
4.肝臓癌の代表的な初期症状
肝臓がんは「沈黙の臓器」に発生するがんのため、初期には自覚症状がほとんどありません。しかし症状が出始めた時にはすでに進行していることが多いです。以下の症状がみられた場合は注意が必要です。
●倦怠感、疲れやすさ
●食欲不振・体重減少
●腹部膨満感・圧迫感
●黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)
●下痢や便通異常
●腹水・むくみ
●女性では生理不順、ホルモンバランスの乱れも
進行すると、腹部のしこりや強い腹痛、腫瘍破裂による腹腔内出血などの急性症状も現れ、生命に危険を及ぼします。
慢性肝炎や肝硬変に由来するサインも見逃さずに
肝臓がんは、肝炎や肝硬変を背景に発症することが中心です。日常の中で倦怠感や軽い下痢、食欲不振、腹部膨満、黄疸の症状があれば、早めに医療機関を受診してください。特に女性はホルモンバランスの関係で消化器症状が出やすく、軽い異常でも見過ごさないことが大切です。
5.肝臓癌の早期発見を目指して
肝臓がんの予防と早期発見に欠かせないのが検査です。肝炎ウイルスの有無を調べる血液検査、肝機能検査、腫瘍マーカー測定に加え、画像診断(腹部エコー・CT・MRI)が重要な役割を果たしています。
●肝炎ウイルス検査(B型・C型)
●肝機能・腫瘍マーカー(AFP・PIVKA-II・AFP-L3分画)
●腹部超音波検査(まず行うスクリーニング)
●CT・MRI(腫瘍の詳細な位置・性質評価)
これらの検査を定期的に受けることで、無症状の段階で異常をキャッチし早期治療や経過観察が可能となります。酒を飲む習慣がある方、脂肪肝や糖尿病、女性では産後や更年期の体調変化があるときにも受診をおすすめします。
最新の画像診断技術とその意義
肝臓がんは初期症状が乏しく、自覚がないまま進行する可能性があるため、定期的な検査が推奨されます。腹部超音波検査は痛みが少なく比較的簡便で、肝臓の形状や腫瘍の有無を手早く把握できます。CTでは造影剤を用いることで、腫瘍の血流パターンや周囲組織への浸潤度を詳細に観察できます。MRIは特に小さな肝臓がんや早期の病変を捉える精度が高く、確定診断や治療方針の決定に欠かせない手法です。
これらの検査の特徴は以下の通りです。
・腹部超音波検査:被ばくがなく、費用負担が比較的軽い
・CT:腫瘍の位置や大きさを多方向から正確に把握できる
・MRI:微小病変を検出しやすく、組織性状の評価にも優れる
検査結果の総合的な評価により、肝臓がんの早期発見や適切な治療選択が可能になります。リスク要因を抱えている方や症状に不安がある場合は、医療機関での定期的なチェックを検討されると安心です。さらに最新機器や専門知識の集積がある病院では、より高度な診断が期待できます。
腫瘍マーカー検査の重要性
AFP(アルファ・フェトプロテイン)は肝細胞がんに特有の腫瘍マーカーとして利用されますが、他の良性疾患でも高くなることがあります。異常値が検出された場合は、画像検査と組み合わせて総合的に評価しましょう。
複数の腫瘍マーカーを組み合わせることで、診断精度が向上し、肝臓がんの早期発見率が向上します。長期間のモニタリングが肝臓がん治療の効果評価や再発検知に役立つ点にも注目されています。
6.肝臓癌を予防するために
日本人のがん死亡原因の上位に位置する肝臓がん。その主な根本原因は長期にわたるC型・B型肝炎ウイルスの感染ですが、近年は脂肪肝や酒(アルコール)性肝炎の増加も見逃せません。現代人の生活習慣の変化により女性の脂肪肝や酒の飲みすぎによる肝障害も増えており、誰もが発症リスクを抱えています。
肝臓がんを予防し、治癒の可能性を高めるためには、肝炎ウイルス感染の早期発見と治療、酒を控える健全な生活、肥満や糖尿病の徹底管理が必要です。肝臓がんは初期症状が少なく、下痢などの軽い消化器症状が出る程度でも見過ごさず、早めに受診しましょう。特に、以下の点に注意が必要です。
●健康診断や自治体が行う肝炎ウイルス検査の活用
●酒の量を減らし、休肝日を作る
●体重管理・運動・バランスの良い食事
●女性はホルモンバランスの変化にも注意
●定期的な腹部超音波、CT、MRI、腫瘍マーカー測定
自分や家族の健康状態を知り、肝臓がんのリスクが高いと感じた場合は、自己判断せずに医療機関で診断と治療を受けましょう。情報収集と早めの行動が、あなたの未来の健康の第一歩です。早期発見と適切な治療によって、肝臓がんは治癒できる可能性が高まります。
もし気になる症状(倦怠感、下痢、腹部違和感、食欲不振、黄疸など)が現れたら、放置せず専門医の診察を受けましょう。肝臓がんの予防は、日々の小さな積み重ねから始まります。酒を適量にし、バランスの取れた生活を意識し、定期的な検診を習慣にしましょう。
あなたとご家族の健康を守るため、沈黙の臓器「肝臓」の声なきSOSを見逃さず、早期発見・治癒を目指しましょう。
※この記事は2025年5月8日に公開され、2025年6月11日に内容を修正しました。

快適医療ネットワーク理事長
監修
医学博士 上羽 毅
金沢医科大学卒業後、京都府立医科大学で研究医として中枢神経薬理学と消化器内科学を研究。特に消化器内科学では消化器系癌の早期発見に最も重要な内視鏡を用いた研究(臨床)を専攻。その後、済生会京都府病院の内科医長を経て、1995年に医院を開業。
統合医療に関する幅広し知識と経験を活かして、がんと闘う皆様のお手伝いが出来ればと、当法人で「がん患者様の電話相談」を行っております。