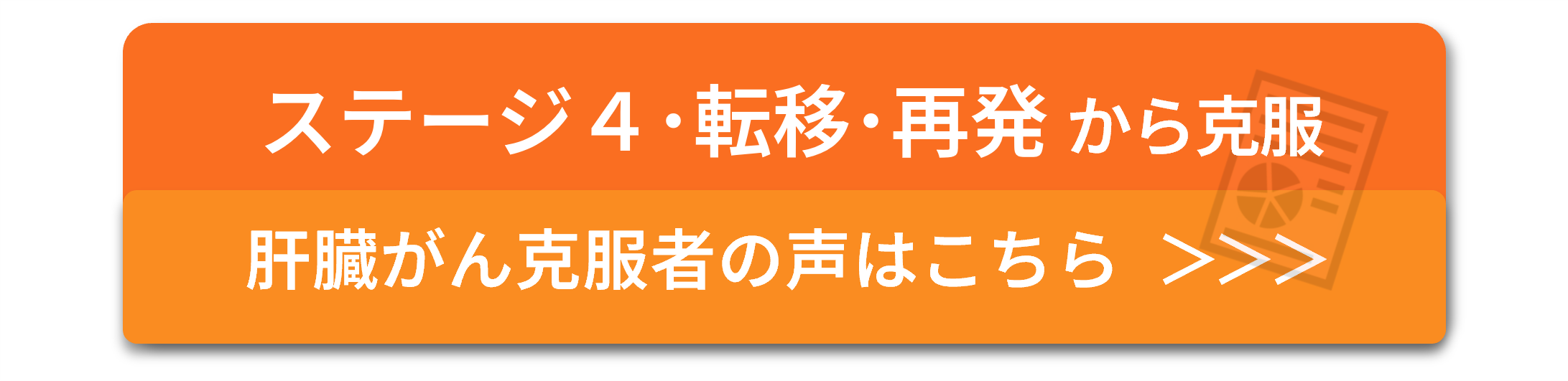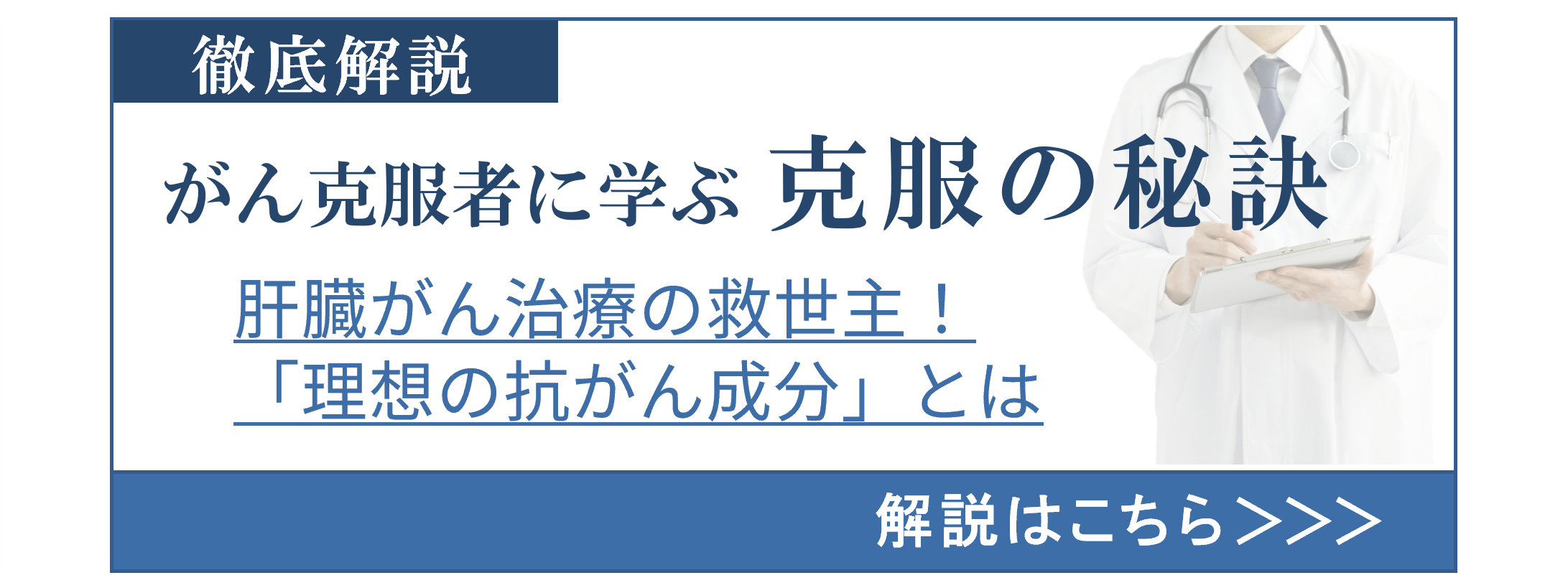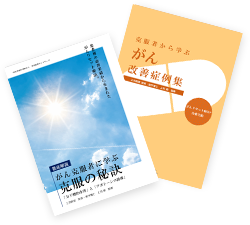- 2025.05.08
- 肝臓がん
肝臓がんの初期症状とは?気をつけたいサイン
肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、自覚症状が乏しいまま進行する特徴があります。肝臓がんは進行すると生命に大きな影響を及ぼしますが、初期段階では体重減少や倦怠感、食欲不振などの全身症状や腹部の違和感といった分かりにくいサインが現れることも多いです。
ウイルス感染や肝炎、脂肪肝、またはアルコール摂取などがリスクとなるため、疾患の発見が遅れる場合が少なくありません。定期的な血液検査や腫瘍マーカー、画像診断により早期発見が可能となり、診断や治療の幅が広がります。
本コラムでは、肝臓がんの症状や原因、予防方法、早期診断と治療方法まで詳しく解説しますので、今後の健康管理に役立ててください。
1.肝臓がんとは
肝臓がんは、早期には自覚症状がほとんどなく、健康診断や血液検査で初めて肝機能の異常を指摘されることが多い疾患です。特に多くの患者が「元気なのになぜ?」と感じる背景には、肝臓が再生能力や予備能が高く、ある程度障害を受けても症状が表れにくい特徴があるためです。このため「沈黙の臓器」と呼ばれ、肝臓がんも進行するまで症状がほとんど現れず、がんが確定したときは末期だった、というケースもあります。
肝臓がんには原発性肝臓がんと転移性肝がんがあり、原発性の多くは肝細胞がんです。肝細胞がんの進行や転移のリスクは高く、定期的な検査がない場合は早期発見が難しいのが現状です。
発生の主な原因としてはB型・C型肝炎ウイルス感染、慢性肝疾患、アルコール、脂肪肝などが挙げられ、これらが関与することで肝臓細胞を繰り返し傷つけ、やがて腫瘍形成に至ります。肝臓がんの診断には、採血による肝機能・腫瘍マーカー検査、腹部超音波やCTが使用され、専門医による総合的な診療が必要です。
肝臓がんを早期発見・治療するためには、日頃から生活習慣の改善とともに、定期的な健康診断や医師への相談が不可欠です。自覚症状に頼らず、健康管理を徹底することが、将来の健康を守る重要な方法です。
肝細胞がんと他の肝臓腫瘍はどう違う?その特徴を解説
肝臓がんは、発生した場所や原因により大きく分類されます。原発性肝がんは、肝臓由来の細胞ががん化したもので、主に肝細胞がんと肝内胆管がんに分かれています。一般的に肝臓がんと呼ばれる場合、その多くが肝細胞がんを指します。
肝細胞がんは、肝細胞への慢性的な炎症や再生が繰り返されることで発症しやすく、B型・C型肝炎ウイルスの感染、アルコール性肝疾患、脂肪肝などが主な原因です。一方、転移性肝がんは胃や大腸など他の臓器のがん細胞が血液を介して肝臓に転移するもので、肝臓内に多発性に腫瘍を形成しやすい特徴があります。
肝細胞がんは再発が多いことも特徴です。初回治療後も肝臓組織自体がダメージを受けており、肝機能が低下している患者が多く、リンパ節や肺、骨、脳に転移することがあるため、定期的なマーカー検査や画像診断が必要です。
このように肝臓がんの種類や特徴を正しく理解し、個人のリスクや原因に応じた検査と診断、早期の治療方針の選択が重要となります。
2.肝臓がんの初期症状
肝臓がんの初期段階ではほとんど自覚症状がなく、症状が現れるのは疾患が進行した場合が多いです。これは肝臓が高い修復能力を持つ臓器であり、大部分が障害を受けるまで異常を感じにくいからです。
進行すると、腹部にしこりや圧迫感、痛みが出現し、さらに悪化すると肝不全の症状へと発展します。そのため、腹水の貯留や黄疸、肝性脳症などの重篤な症状がみられる場合は、すでに肝臓がんがかなり進行していることが推察されます。
また、肝臓がん発症前の段階では、慢性肝疾患、脂肪肝、B型・C型ウイルス性肝炎、アルコール性肝障害などが併存していることが多く、これらによってむくみ、痒み、皮膚や白目の黄疸、全身倦怠感などが出る場合もあります。これらの異常サインは肝臓に関連した疾患の可能性を示唆しています。
肝臓がんの予防や早期発見には、症状の有無だけでなく定期的な健康診断や血液検査が欠かせません。特に肝機能の異常を指摘された場合や、生活習慣にリスク因子がある人は、状態を過小評価せず、積極的に医師と相談することが推奨されます。
見逃しやすい「倦怠感」「食欲不振」などの全身症状をチェック
慢性肝炎や肝硬変も肝臓がんと同様、初期症状は非常に少なく、特にウイルス性肝炎や脂肪肝の場合は無症状で経過することが多いです。症状として現れるのは、食欲不振、むくみ、倦怠感など他の病気でも見られるものに限られ、自己判断で見過ごされるケースが多々あります。
血液検査での異常値や慢性疾患の定期的な確認は、肝疾患の早期発見に不可欠です。肝硬変が進行すれば、疲れやすさや全身倦怠感、足のむくみ、腹水による腹部膨満、夜間から明け方のこむら返り、皮膚や白目の黄疸、へその周囲の静脈拡張、手のひらや顔の赤斑や乳房の腫大(男性の場合)など、より特徴的な症状が現れます。
これらを見逃さず、継続した内科や消化器内科での診療が肝臓疾患の悪化予防だけでなく、肝臓がんの早期発見・治療に直結します。気になる症状がみられた場合は、迷わず医師への受診をおすすめします。
腹部の違和感や右上腹部の圧迫感、これは要注意のサイン?
腹部や特に右上腹部の違和感、圧迫感は注意が必要な体調のサインです。慢性的に続く右下腹部の痛みや、生理でないのに継続する腟からの出血、茶色のおりもの、尿道のかゆみや不快感などの症状は、複数の疾患リスクを示している可能性があります。
患者が50代男性の場合でも、腹部の圧迫感や違和感は消化器系の異常を示すことがあるため、消化器内科や内科での診療を推奨します。精神的ストレスや肉体的疲労も体の不調に関連しているため、症状が改善しない場合や異常が持続する場合は、医師に相談し詳細検査を受けることが大切です。
早期診断を行うことで重大な疾患の進行リスクを軽減できます。症状に気づいたときには自己判断せず、速やかな受診を考えましょう。
3.肝臓がんの原因とは
肝臓がんの主なリスクはB型肝炎ウイルス(HBV)およびC型肝炎ウイルス(HCV)などのウイルス性肝炎です。国内外の調査データからも、肝細胞がんの約半数がC型、1割以上がB型ウイルス感染によって発症していることがわかります。また、最近は非ウイルス性の肝臓がんとして、アルコール性肝疾患や非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD/NASH)など生活習慣に関連した要因も増加しています。
非ウイルス性肝臓がんの主因はアルコールの過剰摂取で、患者の32.3%に及びます。続くNAFLD/NASHも脂質異常や肥満、糖尿病に深い関わりがあり、15.1%が該当します。加齢や喫煙、肥満、糖尿病なども肝腫瘍リスク因子です。
肝臓は体内で解毒、代謝、栄養蓄積など重要な役割を担いますが、これらのリスクが持続的に肝細胞へダメージを与え、炎症と再生が繰り返されることで腫瘍化に繋がります。
肝臓がんの予防やリスク軽減には、ウイルス検査の受診、禁酒や節酒、バランスの取れた食事、適度な運動など生活習慣の改善が有効です。このように、多因子による肝臓がん発生リスクを理解し、医師の助言をもとに対策する必要があります。
慢性肝炎や肝硬変がある人は肝臓がん発生リスクが高いって本当?
慢性肝炎や肝硬変をもつ患者は、肝臓がんへの発症リスクが非常に高いことが明らかです。特にB型・C型肝炎ウイルス感染者、肝硬変患者は一般の方よりもずっと高い確率で肝細胞がんを発症します。
・B型肝炎ウイルス(HBV)やC型肝炎ウイルス(HCV)感染
・肝硬変
・男性、高齢者
・アルコール摂取、喫煙
・肥満、脂肪肝、糖尿病
これらが代表的なリスク因子です。とくにHBV・HCV感染や肝硬変を有する方には、3~6ヶ月ごとの定期検査や画像検査、腫瘍マーカーのチェックが推奨されています。近年は生活習慣病やメタボリックシンドロームに伴う脂肪肝、糖尿病由来の肝がんも増えているため、これらの基礎疾患を有する方は、生活習慣の見直しとともに消化器専門医による経過観察が大切です。
肝臓疾患がある場合は、日々の健康管理とあわせて、必要な医療介入を怠らないよう意識すべきです。
お酒や脂肪肝が肝臓がんの原因になる可能性と予防方法
お酒の飲みすぎや脂肪肝は肝臓がん発症のリスク因子として知られています。喫煙や肝炎ウイルス感染、肥満、糖尿病なども肝腫瘍発生に関与しています。
肝臓がんの予防には、まずB型・C型肝炎ウイルスへの感染予防のためワクチン接種が重要です。また、禁煙やアルコール摂取量のコントロール、健康的な食事や適度な運動習慣もリスク低減に有用です。
予防策は患者や家族の健康状態に基づき、医師と相談しながら取り組むことが効果的です。日常生活の中で定期的な健康チェックと疾患の早期発見を心がけ、肝臓を守る行動を積極的に行いましょう。
4.早期発見に必要な検査
肝臓がんを早期発見・診断するためには、肝炎ウイルスの感染リスクを把握し、早めの検査を受けることが基本となります。公的機関や医療機関でB型・C型肝炎ウイルス検査(HCV抗体、HBs抗原)を無料で受けられる制度もあるため、未検査の場合は積極的な利用が勧められます。
健康診断での肝機能検査(AST、ALT、γ-GTPなど)や血液中の腫瘍マーカー測定は、脂肪肝や慢性肝炎の早期発見に有効です。肥満やアルコール多飲、糖尿病など背景疾患がある方は、医師の指導のもと生活習慣の見直しを心掛けましょう。
肝臓がんは症状が出にくい一方で、CTや腹部超音波(エコー)、MRIなどの画像診断を用いることで微細な腫瘍や肝機能異常も早期に発見できます。当クリニックでも肝臓がんに関連する幅広い検査を実施しています。
リスクの高い方は、血液マーカーと画像診断を組み合わせた定期的なチェックが不可欠です。抑えるべきポイントを理解し、医師と相談の上で最適な予防と診断の体制を整えることが、早期発見と治療成功の鍵となります。
血液検査の数値異常や腫瘍マーカーが示す肝臓がんリスクとは
肝臓がんのリスク評価においては、血液検査および腫瘍マーカーの測定が重要です。AFP(アルファ・フェト・プロテイン)やAFP-L3分画、PIVKA-IIなどの腫瘍マーカーは、肝臓がんの場合高値を示すことが多く、診断や治療効果判定、経過観察に利用されます。
また、腹部超音波検査では肝臓内の腫瘍の大きさや部位、周囲血管との関係性、腹水の有無などが分かり、安心して受けられる非侵襲的検査として有用です。
CTやMRIなどの画像診断を併用することで、腫瘍の広がり、転移の有無、他臓器への影響を詳細に把握できます。
早期段階での血液異常や画像診断所見の発見により、迅速な治療介入へ結びつけることができ、肝臓がんの治療成績の向上に繋がります。
腹部超音波検査やCT検査による肝がんの早期発見と診断
腹部超音波検査やCT検査は肝臓がんの早期発見に不可欠な診断方法です。肝臓がんの主要因である肝炎ウイルス感染の有無を早期に把握することが、予防と早期治療への第一歩となります。B型・C型肝炎ウイルス検査は公的な無料検査も行われており、自覚症状がない場合も積極的に利用しましょう。
健康診断で肝機能の定期チェックを行い、がんのリスクが高い場合は適宜画像検査を追加することで、無症候ながらも進行した肝腫瘍の発見率が上がります。肥満や大量飲酒、糖尿病などの背景疾患を持つ方は、特に定期的な医療機関での評価が推奨されています。
当クリニックでは肝臓がんの検査体制が整っており、患者ごとに最適な検査・診断をオーダーメイドで実施しています。安心な医療アクセスを活用することで、肝臓がんの早期発見と良好な予後を目指しましょう。
5.初期症状に気付いたら
初期段階で肝臓がんが診断された場合、治療の可能性は十分に広がります。ステージ1では手術が治療の中心となり、腫瘍部分の切除や肝部分切除術が行われます。患者の肝機能や腫瘍の大きさ、位置などに応じて治療計画が立案され、手術が難しい場合は局所治療も選択肢となります。
局所治療法には、肝動脈塞栓術やラジオ波焼灼療法などがあり、腫瘍局所へのアプローチを通じてがん細胞を制御します。早期発見であればあるほどこれらの治療が有効に機能し、患者の予後改善へと繋がります。
治療後も細やかな経過観察と定期フォローアップが不可欠であり、主治医および多職種医療チームとの連携のもと、患者それぞれに適したサポート体制を保持することが回復と再発予防の鍵です。
初期症状で発見できれば、肝臓がんの治療選択肢は広がる
肝臓がんは慢性肝炎や肝硬変を経て生じることが多く、近年は脂肪肝炎も注目されています。ウイルス性肝炎(B型・C型)やアルコール性脂肪肝炎、多量飲酒、非アルコール性脂肪肝(NASH)、糖尿病、肥満、高血圧、脂質異常症などが慢性炎症や線維化を引き起こし、肝硬変・肝臓がんへと進行します。
これらを予防するには、慢性肝炎や脂肪肝炎の早期発見・早期治療がきわめて重要です。加えて日常生活でリスクファクターを抑制し、医師による定期的な経過観察を受けることで、治療時期を逃さず最良の治療選択肢を得ることができます。
肝臓がんとその前段階の疾患を理解し、生活習慣改善も取り入れることで、肝臓全体の健康維持・がん予防の成果に繋がります。
初期の肝臓がんに効果的な治療法とは?
肝臓がんステージ1には複数の治療法が適応されます。手術による腫瘍摘出や肝部分切除が代表的ですが、近年は免疫療法や分子標的薬による治療も導入されてきました。
免疫療法は患者自身の免疫機能を強化し、がん細胞を排除する治療で、全身状態や合併症に応じて適応が検討されます。標的治療は、がん細胞表面の特異的な分子を狙う薬剤を用いて、正常組織への影響を減らし、副作用が比較的小さい利点があります。
こうした進歩により、患者一人ひとりの病状や予後に合わせた最適な治療戦略を提案できるため、初期の肝臓がんに対しても幅広い選択肢を持つことが可能となっています。
6.肝臓がんの初期症状まとめ
肝臓がん初期の症状はごく軽度で見逃されやすいものの、腹部の不快感や体重減少など細かな変化に気付くことが重要です。これらの症状は他の病気と共通する場合もあるため、普段から自分の健康状態について関心を持ち、異常を感じたら迅速に医師へ相談することが早期発見につながります。
日々の健康管理や定期的な診療、血液検査、超音波検査などは進行した肝臓がんや肝機能障害を未然に防ぐ最良の手段です。また、B型・C型肝炎ウイルスの感染リスクや生活習慣病を抱える方は定期的なチェックを徹底することで、治療のタイミングを逃さずにすみます。
健康的な生活習慣や医療機関との連携の中で、肝臓がんの早期発見と適切な治療を心がけることで、生存率やQOL(生活の質)の向上が期待できるでしょう。
今後も自身の体調変化に敏感になり、定期的な検査や医療相談を積極的に受ける習慣を持つことが、健康な未来を守る第一歩となります。少しでも不安や異変を感じたら、ぜひ医師に相談してみてください。

快適医療ネットワーク理事長
監修
医学博士 上羽 毅
金沢医科大学卒業後、京都府立医科大学で研究医として中枢神経薬理学と消化器内科学を研究。特に消化器内科学では消化器系癌の早期発見に最も重要な内視鏡を用いた研究(臨床)を専攻。その後、済生会京都府病院の内科医長を経て、1995年に医院を開業。
統合医療に関する幅広し知識と経験を活かして、がんと闘う皆様のお手伝いが出来ればと、当法人で「がん患者様の電話相談」を行っております。