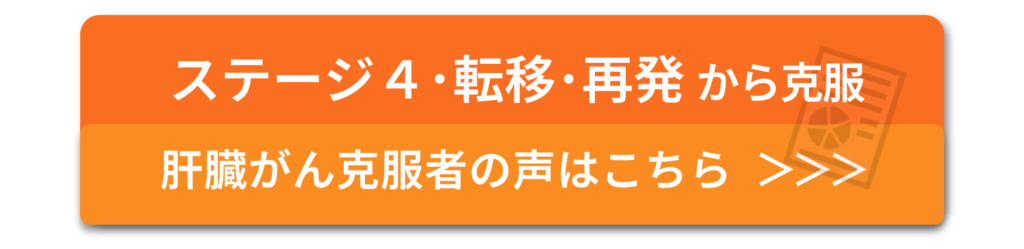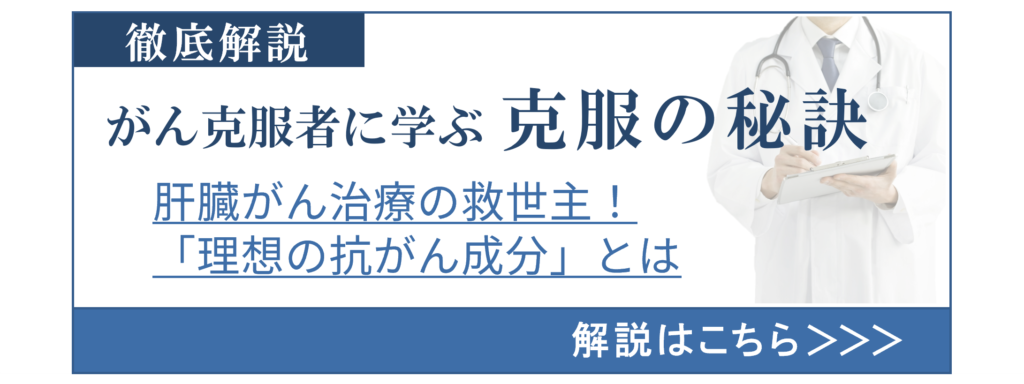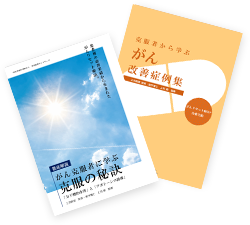- 2025.10.22
- 肝臓がん
肝臓がん患者に多い皮膚のかゆみ。症状と対策は?
肝臓癌は日本でも比較的多く見られ、慢性的な肝臓の病気を背景に発症することが少なくありません。特に、肝炎ウイルスによる感染(B型肝炎など)や、アルコールの過剰摂取、脂肪肝といった生活習慣病が主なリスクとして指摘されています。
肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、部分的な機能が低下しても症状が出にくく、人が気づいたときには病気が前に進んでいるケースが少なくありません。しかし、肝臓の機能が低下すると、全身の不調や皮膚のかゆみや発疹といった症状が出ることがあります。
これらの皮膚症状は、夜間にかゆくて眠れないといった悩みを生じさせ、日々の生活の質(QOL)に大きな影響を与えます。かゆいと感じる以外にも、脂肪の代謝異常など、肝臓癌と関係ないように感じる変化も存在します。
このコラムでは、肝臓がんにおいてなぜかゆみや発疹が生じるのかというメカニズムを解説します。また、具体的な治療法が効果を出すための管理方法や、再発への注意点、そして診療を受ける適切なタイミングについても、分かりやすくご紹介します。
肝臓がんが治る可能性、あるいは悪い経過を辿る可能性など、不安な情報も世の中にあふれています。しかし、大切なのは、信頼できる情報源に基づいた正しい知識と、自分らしい生活を保つための対策を知ることです。
このコラムが、適切な受診のタイミングを見極める一助となれば幸いです。
1.肝臓がんの症状と特徴
肝臓がんは、初期段階ではほとんど症状を示さないことが特徴です。肝臓は再生能力が高いため、機能の大部分が損なわれるまでは、ご自身で異常に気づきにくい傾向があります。
腫瘍が成長し肝機能が低下すると、全身の倦怠感、食欲不振、黄疸(皮膚や目が黄色くなる)、浮腫(むくみ)、腹部膨満感や痛みなどが出現します。特に、病状が進行すると、胆汁の流れの異常に伴い、皮膚にかゆみや発疹が現れやすくなります。
早期に診断を受け、適切な治療を行うことが、その後の見通しや生活の質の改善に役立ちます。
初期症状と進行症状の違い
肝臓がんの初期症状は非常に乏しいことが多く、多くの方は無症状のまま日常生活を送る場合が多いです。初期段階では、健康診断や人間ドックなどで画像検査や血液検査の異常が偶然見つかるケースが主です。
一方、がんが進行するにつれて、肝臓の機能低下が顕著になり、黄疸やむくみ、皮膚の異常(発疹やかゆみ)といった特徴的な肝疾患の症状が現れます。特に、胆汁の流れが悪くなることによるかゆみは、進行期の特徴的な症状の一つです。進行した症状は、日常生活に重大な影響を与えることがあります。
各ステージにおける具体的な症状
肝臓がんの進行度(ステージ)ごとに見られる症状には違いがあります。
・早期
自覚症状が極めて乏しいですが、定期健診などで肝機能の異常や腫瘍マーカーの上昇が発見されることがあります。
・中等度進行期
肝細胞の損傷や胆汁の流れの悪化により、全身の倦怠感や黄疸、尿の色の変化などが起こりやすくなります。
肝臓の腫れにより腹部膨満感や圧痛(押すと痛い)も顕著になります。
・より進行したステージ
腹水の出現、むくみ、重度の黄疸などが増加します。皮膚には、クモ状血管腫や点状出血、広範囲なかゆみなどが現れます。
また、がんが転移した部位に応じた痛みや症状が現れるのも特徴です。
病状の進行と共に症状も複雑になるため、ステージごとに専門の診療科と連携し、適切な診断・治療を受けることが不可欠です。
2.肝臓病に伴うかゆみのメカニズム
肝臓病に関連したかゆみ(掻痒症)は、多くの患者さんの生活の質(QOL)に大きな影響を与えます。このかゆみは、皮膚に直接的な発疹(皮疹)が現れない場合が多く、「一般的なかゆみ止めが効きにくい」といった特徴があります。
主な原因は、肝臓病によって胆汁の流れが滞る(胆汁うっ滞)ことです。

かゆみの原因となる生理学的要因
肝臓病に伴う皮膚のかゆみは、単なる皮膚の乾燥やアレルギーとは異なり、体内で起こる複雑なメカニズムによって生じます。
主な原因は、肝臓の働きが悪くなることによる胆汁の流れの異常です。肝炎(B型肝炎、C型肝炎、アルコール性肝炎など)や肝硬変によって肝細胞が障害を受けると、肝臓本来の機能が低下し、胆汁がスムーズに作られたり排出されたりすることが難しくなります。
通常、胆汁は肝臓で作られ、脂肪の消化を助けるために胆管という通り道を通って腸へと流れていきます。しかし、肝機能が低下したり、がんや結石によって胆管が詰まったりすると、胆汁の流れが滞ってしまいます(胆汁うっ滞)。これにより、胆汁の成分である胆汁酸などが血液中に逆流・蓄積しやすくなります。
この蓄積した胆汁酸が血流に乗って皮膚へと運ばれ、皮膚の末梢にある知覚神経を直接刺激することで、強いかゆみが発生すると考えられています。
この種のかゆみは、全身に及ぶ傾向があり、特に夜間に悪化しやすいという特徴があります。また、肝臓病に伴う全身の炎症反応によって、かゆみを引き起こすヒスタミンなどの物質が増えることも、症状の増悪に関与していることが指摘されています。
このように、皮膚の表面ではなく、体の内側から発生するかゆみであるため、一般的なかゆみ止めでは効果が出にくいことがあります。
そのため、肝臓病の診断時には、この皮膚症状の詳細な評価が重要視されるのです。
ヒスタミンと胆汁酸塩の役割
肝臓病によるかゆみは、胆汁酸塩(胆汁酸)とヒスタミンという、二つの異なる生理活性物質が複雑に作用し合うことで引き起こされます。
まず、胆汁酸塩の役割です。前述したように、肝臓の機能が低下したり胆汁の流れが滞ったりすると、本来排出されるべき胆汁酸が血液中に過剰に蓄積します。
この胆汁酸塩が血流に乗って皮膚に運ばれ、皮膚の末梢神経を直接的に強く刺激することで、かゆみが発生します。
この刺激は非常に強いため、夜間に悪化しやすく、患者の睡眠や生活の質を大きく妨げます。
次に、ヒスタミンの役割です。ヒスタミンは、アレルギー反応の際に放出される物質として知られていますが、肝臓病に伴う全身性の炎症反応によっても、その濃度が上昇することが指摘されています。
このヒスタミンが神経終末を刺激し、かゆみを感じさせます。また、炎症が起こると、神経が敏感になるため、胆汁酸塩による刺激がさらに強く感じるようになります。
このように、胆汁酸塩はかゆみの主な原因物質となり、ヒスタミンや炎症がその症状を悪化させる要因となります。
この二重のメカニズムによって発生するかゆみは、一般的な皮膚疾患(湿疹など)とは発生する仕組みが大きく異なります。
そのため、かゆみを訴える患者に対しては、肝機能の状態と皮膚の状態を両方から詳しく評価し、原因に応じた適切な治療戦略を立てることが、肝疾患の診断過程において非常に重要となるのです。
3.肝臓がんと皮膚症状の関連性
肝臓がんでは、腹部の症状よりも先に皮膚症状が現れることがあります。これらの皮膚症状には、持続的な発疹、かゆみ、皮膚の色調変化などが含まれます。
肝機能障害が進行すると、肝臓の解毒機能やホルモン調節能力が低下し、その結果、体内に蓄積した毒素や胆汁成分が皮膚に反映されます。
こうした皮膚症状は、肝疾患特有のサインとなることも多く、医学的には画像検査や血液検査と並行して皮膚の状態を重視することで、早期診断につながる例も報告されています。したがって、慢性的な皮膚の変化や全身性のかゆみに気づいた場合は、肝臓がんをはじめとする肝疾患の可能性も視野に入れ、専門医の受診を検討することが重要です。
肝臓がんにおける発疹の特徴
肝臓がんに関連する発疹は、一般的なアレルギーや感染症によるものとは異なる性質を持つことがあります。
特徴的な所見としては、次のようなものがあります。
・クモ状血管腫(スパイダー・アンギオーマ)
赤い点を中心に血管が放射状に広がる発疹で、胸部や顔面に現れやすいです。
・紫斑(あざ)や点状出血
凝固機能(血を固める力)の異常により、小さな赤~紫色の点やあざが説明なく出現します。
・黄疸
皮膚や目の色調が黄色く変化します。
・乾燥性湿疹様変化
鱗屑(フケのようなもの)を伴う乾燥性の皮膚変化が見られ、かゆみを伴うことが多いです。
これらの皮膚症状が、黄疸や倦怠感、腹部膨満といった肝疾患の全身症状とともに現れた場合は、肝機能の低下や進行した肝障害を示唆します。
皮膚症状の種類によって必要な診断や管理が異なるため、専門的な診断を受けることが大切です。
発疹が示す肝臓がんの進行
肝臓がんの進行とともに皮膚症状も変化し、病状の指標となる場合があります。
初期には軽度な皮膚の変色やかゆみ程度ですが、腫瘍の量が増加し、肝機能が著しく低下すると、クモ状血管腫が現れやすくなります。進行に伴い、凝固障害による紫斑やあざが多発するようになります。
これらの皮膚の変化や異常は、血中のビリルビン値や凝固因子の減少と密接に関係しています。
発疹の悪化や新たな出現は、既に診断を受けている患者さんの場合、肝機能の更なる低下や腫瘍の増大・転移を示唆するサインと捉えられます。
そのため、症状の変化に気づいた際は、速やかに再評価や専門医の受診が推奨されます。
4.肝臓がん発疹の変化と治療法
肝臓がんに伴う発疹は、腫瘍の進行状況と関係し、時間の経過とともに変化を示します。
・無症候期(早期)
画像や血液検査で肝障害が検出されても、皮膚症状が明確に現れないことが多いです。
・初期段階
軽度なかゆみや、胸や手足のわずかな変色が現れることがあります。
・進行期
クモ状血管腫や点状出血、あざといった出血性の皮膚変化が目立つようになり、黄疸や強いかゆみを伴うことがあります。
・末期
これらの皮膚症状が広範囲に拡大し、全身状態の悪化とともに黄疸や強い倦怠感、腹部症状なども加わります。
治療には、肝がんそのものの治療に加えて、症状の軽減や合併症の管理が重要です。
皮膚症状が明らかになった時点で、速やかに肝がんに関する専門医療機関を受診し、個人の病状や体質に合わせた治療を進めることが求められます。

治療方法とかゆみ対策
肝臓がんの治療と周辺の管理は多岐にわたります。治療方針の決定においては、がんの広がりや肝硬変の重症度を示す基準(TNM分類やChild-Pugh分類など)が用いられます。
標準的な治療法には、外科手術(切除)、内科的療法(抗がん剤、分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬などの点滴治療)、放射線治療などが考慮されます。また、カテーテル治療(TACE/TAE)も、腫瘍を局所的に制御するために広く用いられる方法の一つです。
皮膚症状の管理
特に皮膚症状への対策は、生活の質(QOL)維持のために重要です。かゆみに対しては、内服薬(かゆみ止めなど)や外用薬を用いた薬物管理が行われます。
また、皮膚の乾燥はかゆみを悪化させるため、保湿剤の使用による乾燥予防が不可欠です。栄養管理など、多面的なアプローチでQOLの維持向上を図っていきます。
5.まとめにかえて
今回のコラムでは、肝臓癌などで肝臓の機能が低下した際に人を悩ませる皮膚のかゆみや発疹がなぜ生じるのか、その概要を解説しました。
肝臓がんは、初期には症状が出ない部分が多いことは事実ですが、発疹やかゆみといった症状は病状が前に進行した際に出ることが多いです。このため、定期的な健康診断や肝機能検査を継続的に活用し、早期に異常を発見することが最も重要となります。
特に、B型肝炎などの肝炎ウイルスに感染した人や、脂肪肝といった生活習慣病のリスクを指摘されている人、アルコールの過剰摂取がある人は、悪い結果を避けるためにも注意が必要です。女性に比べてリスクが約6倍といわれる男性も、診療を受けることを強く推奨します。
しかし近年、肝臓がんの治療は目覚ましく進歩しており、治る可能性は以前と比べて格段に向上しています。早期発見ができれば、効果の高い多様な治療法の選択肢が存在します。
かゆいことで眠れないといった悩みには自己判断せずに専門医の診断を仰ぐことが、ご自身の健康と生活の質を守る第一歩となります。不安を感じることは悪いことではありません。勇気を出して一歩踏み出し、専門スタッフとともに最善の治療戦略を立てていくことが、前向きな未来につながります。

快適医療ネットワーク理事長
監修
医学博士 上羽 毅
金沢医科大学卒業後、京都府立医科大学で研究医として中枢神経薬理学と消化器内科学を研究。特に消化器内科学では消化器系癌の早期発見に最も重要な内視鏡を用いた研究(臨床)を専攻。その後、済生会京都府病院の内科医長を経て、1995年に医院を開業。
統合医療に関する幅広し知識と経験を活かして、がんと闘う皆様のお手伝いが出来ればと、当法人で「がん患者様の電話相談」を行っております。