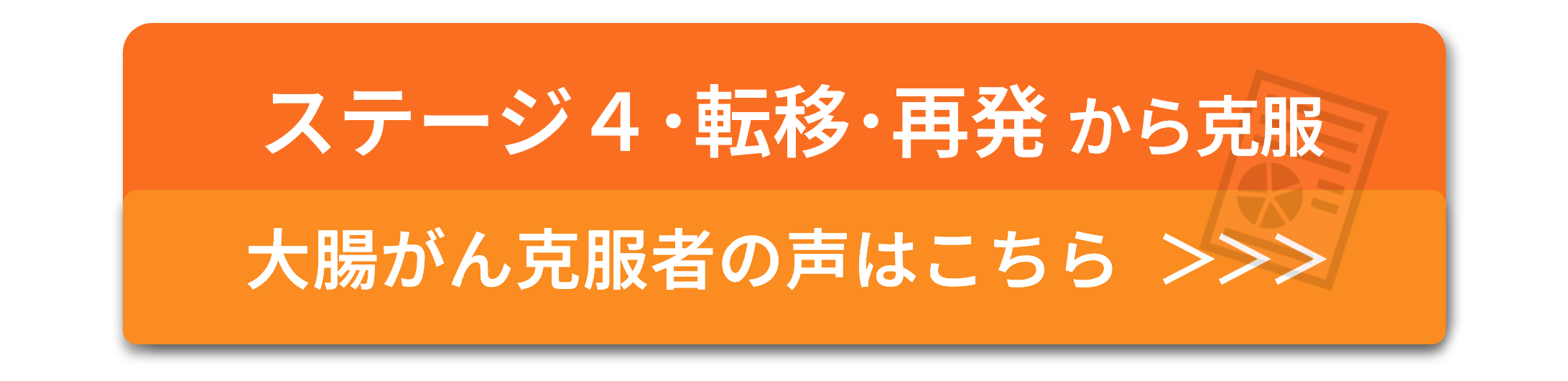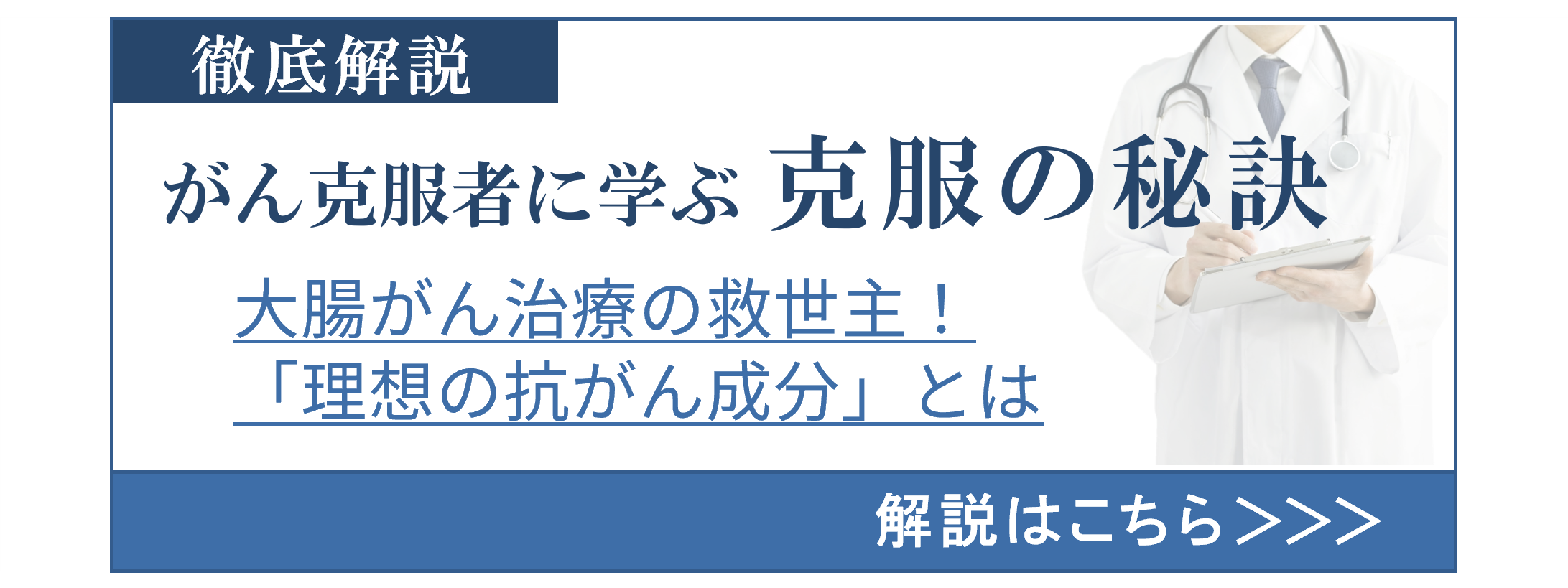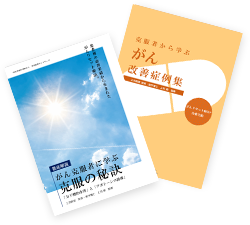- 2025.10.06
- 大腸がん
大腸がんの再発。原因・治療・予防について解説
大腸がんの治療を終え、定期的な検査を受けながら日常生活を送られている患者様とそのご家族の皆様にとって、「再発」という言葉は常に大きな懸念かもしれません。
しかし、再発について正しい情報と知識を持つことは、いたずらに不安を煽るのではなく、日々の生活で安心につながる行動を選択し、もしものときに冷静に治療へ向かうための必要な「備え」となります。
本コラムでは、大腸がんの再発の仕組みから、再発リスクの要因、治療法、そして再発予防のための生活習慣まで、医療の視点から徹底解説します。
1.大腸がんの再発とは
大腸がんの治療として手術を行い、がんが完全に切除できたと医師が判断した後も、体内にごくわずかながん細胞が残存している可能性があります。これらの細胞は、あまりにも少ないために検査で発見できず、体内に潜んでいる状態です。
再発の定義とメカニズム
術後、時間が経過してから、この残存していた微小ながん細胞が再び増殖し、目に見える(画像や検査で診断できる)大きさになって現れることを「再発」といいます。これは、切除した臓器の近くや、血流やリンパ節を通って他の臓器へ転移していた微細な病変が増殖した結果です。
特に進行したがんほど、この微小な細胞が体内に残っている可能性が高くなり、再発する率も高くなります。粘膜内にとどまる早期のがん(0期)は切除すれば再発はほとんど起こりません。
再発の時期について、大腸がんの患者様の約80%が手術から3年以内に、95%以上が5年以内に再発が発見されているという統計情報があります。そのため、術後5年間は特に慎重な経過観察が大切となります。
大腸がんが再発する背景には、手術時には切除範囲の外に、血流やリンパ節を通って肝臓や肺などの臓器へ移動している微小な転移巣(がん細胞)があります。再発は、がん細胞の「生物学的な悪性度」にも左右されます。現在、医療では、切除した組織を詳細に検査し、患者様ごとに再発リスクを正確に判断しています。
再発の種類とその影響
再発は、がんが再び起こりやすい場所によって、大きく以下の分類に分けられます。
局所再発
再発する場所:最初にがんがあった組織や、手術で切除してつないだ部分(吻合部)の近く。
特徴と影響:直腸がんは、周囲の組織を広く切除することが難しい場合があり、局所再発が起こりやすいと考えられています。切除が可能な場合は、治すことを目指した治療が行われます。
遠隔再発(転移再発)
再発する場所:大腸から離れた臓器(肝臓、肺、骨、脳など)。
特徴と影響:肝臓や肺への転移が多く、特に大腸がんでは一般的な転移経路です。治療の選択肢が広がり、切除が可能な場合もあります。
腹膜再発(腹膜播種)
再発する場所:お腹の中の臓器を覆う薄い膜(腹膜)にがん細胞が広がる状態。
特徴と影響:治療が難しいことが多く、薬物療法や温熱を用いた化学療法などが検討されます。
再発の種類と進行の程度によって、その後の治療方針や患者様の身体への負担は異なります。しかし、診断された方でも、ご自身の病気の状態を知り、最善の治療法を選択することが大切です。
2.大腸がんの再発リスク要因
大腸がんの再発は、すべての患者様に起こり得る可能性がありますが、そのリスクを高くするいくつかの要因が確認されています。
遺伝的要因と生活習慣
再発のリスクには、患者様自身の体の特性と、治療後の生活習慣が関係しています。特に、最初の病気の進行度(ステージ)分類が最も大きく再発を左右しますが、生活習慣の改善も再発の可能性を下げる上で重要な役割を果たします。
最初の病気の進行度(ステージ):ステージIIIの大腸がんは、リンパ節への転移があるため、再発率が約30%以上と高くなります。このステージの方には、術後に再発を予防する目的で化学療法(抗がん剤)が行われます。一方、ステージIは約5%と再発リスクは少ないです。
遺伝的要因:家族内に大腸がんの患者が多くいる場合や、「リンチ症候群」などの特定の遺伝性疾患がある方は、再発や新たなのがんが発生するリスクが高くなります。
肥満:治療後も適正体重を維持することは大切です。肥満状態は、がん細胞の増殖に関連する物質の量を高くする可能性が示唆されています。
喫煙・過度の飲酒:喫煙は大腸がんのリスクを確実に高くする要因であり、再発にも影響を与えると考えられています。飲酒も適度な量に抑えることが推奨されます。
運動不足:適度な運動は、免疫機能の改善や炎症の抑制を通して、再発予防に効果が期待されています。
これらのリスク要因について知っておくことは、術後の生活改善につながります。
治療後の経過観察の重要性
大腸がんの術後で最も大切なことは、医師が推奨するスケジュールに従い、定期的な検査(経過観察)を受けることです。
再発は早期に発見できれば、手術や他の治療方法で治す可能性が高くなります。経過観察で行われる主な検査は以下の通りです。
腫瘍マーカーの血液検査:再発や転移の可能性を示唆するがん細胞由来の物質の量を確認します。
CT検査:肝臓、肺、リンパ節など、遠隔転移の有無を確認するために必要な検査です。
内視鏡検査(大腸カメラ):切除した部分や大腸全体に局所再発や新たなのがんがないかを確認します。
大腸がんの経過観察は最新の情報に基づいて、病院にて厳格に行われています。検査内容や間隔は、ステージ別、がんの部位(結腸か直腸か)ごとに細かく分類されています。
特に、再発が多い術後5年以内は、血液検査やCT検査が3ヶ月~6ヶ月ごとに行われることが多く、内視鏡検査も定期的に行われます。これらの検査を定期的に受けることが、再発を早期発見し、予後も良好となるための鍵です。
3.大腸がん再発後の治療法
もしも再発が診断された場合でも、決して諦める必要はありません。医療の進歩により、再発がんに対しても多くの治療方法が開発されています。
再発時の治療の選択肢
再発後の治療方針は、「がんを治す」ことを目指すのか、「がんの進行を抑え、症状を緩和する」ことを目指すのか、患者様の状態や再発部位、数などに基づいて判断されます。
治療の選択肢は主に以下の通りです。
・手術療法(切除術)
再発した場所が肝臓や肺などの臓器に限られており、切除が技術的に可能で、患者様の全身状態が良好な場合、切除手術によって治すことを目指します。
大腸がんは、肝臓や肺へ転移しても切除によって高い効果が期待できるがんの一つです。
局所再発の場合も、手術で切除できるかどうか検討されます。
・薬物療法(化学療法、分子標的薬、免疫療法)
手術が難しい場合や、全身にがんが広がる可能性がある場合、薬物療法が治療の中心となります。
化学療法(抗がん剤)に加え、がん細胞の増殖に必要な分子を狙い撃ちする「分子標的薬」が広く利用されています。
特定の遺伝子異常があるがんの方を対象に、免疫の力を利用する「免疫チェックポイント阻害薬」などの新しい治療方法も導入されています。
これらの薬は、全ての患者様に効果があるわけではなく、がん組織を採取して遺伝子検査(バイオマーカー検査)を行うことが必要です。医師は、これらの情報をもとに、患者様ごとに最も効果が高いと判断される治療方法を選択します。
・放射線治療(放射線療法)
再発部位が限られている場合や、骨への転移による痛みなど、局所の症状を緩和する目的で行われます。
これらの治療方法は、日本癌治療研究会などが作成する診療ガイドラインに基づき、最新の情報を反映して選択されます。治療は、多くの場合、外来で行われ、患者様の生活にかかる負担を軽減することも考慮されます。
緩和ケアと患者の生活の質
再発後の治療は、がんの進行を抑えることだけでなく、患者様の生活の質(QOL)を維持・向上させることが極めて大切です。
緩和ケアは、再発治療の最初の段階から並行して行われるべきものと考えられています。
症状管理:がん自体や治療による痛み、吐き気、皮膚の変化、副作用などの身体的な症状を専門的に和らげます。
精神的・社会的サポート:不安や抑うつ、経済的な問題など、患者様やご家族様が抱えるその他の苦痛についても相談を受けます。
治療方法を選択する際には、「治す」ことと「自分らしい生活」の両立を考慮することが重要です。主治医や緩和ケアチームとよく相談して、ご自身の希望に沿った治療方針を確認して進めていきましょう。
4.再発予防のための生活習慣
大腸がんの再発を完全に防ぐ方法はまだ確立されていませんが、医学的な研究から、生活習慣の改善が再発のリスクを下げる効果が期待できることが示されています。
食事と運動の見直し
がん患者の方を対象とした研究でも、健康的な生活習慣の重要性が再確認されています。
運動習慣
適度な運動を継続することは、再発リスクを下げる効果が期待されています。目安として、週に150分程度の中等度の有酸素運動(早歩き、軽いジョギング等)を行いましょう。体力や病気の状態に応じ、医師に相談して無理のない範囲で実施することが大切です。運動は、単に再発リスクを下げるだけでなく、体力の回復、治療による疲労感の軽減、精神的な安定にも大きく貢献します。
食事内容
高カロリーの食事や、動物性の赤肉・加工肉の過剰摂取は控え、野菜、果物、全粒穀物など、食物繊維を豊富に含む植物性食品を中心としたバランスの取れた食事を心がけましょう。禁煙と節酒も、大腸がんの再発予防には極めて重要な要素です。栄養管理士などの専門家に相談して、患者様の体質や腸の状態に合った個別的なアドバイスを受けることも非常に効果的です。
定期的な検診の重要性
大腸がんの経過観察は、再発のサインを早期に見つけ、治療の成功率を高くするために不可欠な方法です。
検診を受ける際は、検査結果について疑問や不安があれば、遠慮なく医師に相談して情報を得て、納得して治療に取り組むことが何よりも大切です。
現在の医療は、再発がんに対しても様々な武器(治療方法)を持っています。不安や疑問は主治医や病院の相談窓口(がん相談支援センター等)に問い合わせ、情報を得て、前向きに生活に取り組んでいきましょう。
5.大腸がんの再発まとめ
本コラムでは、大腸がんの「再発」というテーマについて、医学的な事実に基づき解説しました。再発は決して終着点ではなく、治療やケアを続けるための新たな始まりです。
再発リスクを理解し、ご自身の生活習慣を見直し、そして何よりも定期的な経過観察を続けることが、日々の安心につながります。不安を感じたり、治療選択に迷ったりしたときは、一人で抱え込まず、必ず主治医や病院のがん相談窓口にご相談ください。専門家との対話を通じて、自分らしく生きるための最善の道を見つけることができます。
※この記事は2025年2月21日に作成され、2025年10月6日に内容を更新しました。

快適医療ネットワーク理事長
監修
医学博士 上羽 毅
金沢医科大学卒業後、京都府立医科大学で研究医として中枢神経薬理学と消化器内科学を研究。特に消化器内科学では消化器系癌の早期発見に最も重要な内視鏡を用いた研究(臨床)を専攻。その後、済生会京都府病院の内科医長を経て、1995年に医院を開業。
統合医療に関する幅広し知識と経験を活かして、がんと闘う皆様のお手伝いが出来ればと、当法人で「がん患者様の電話相談」を行っております。