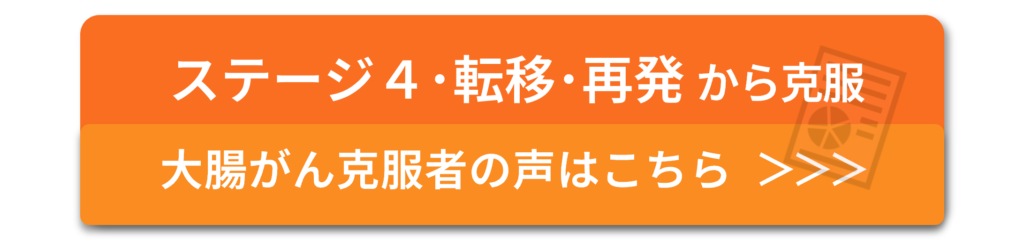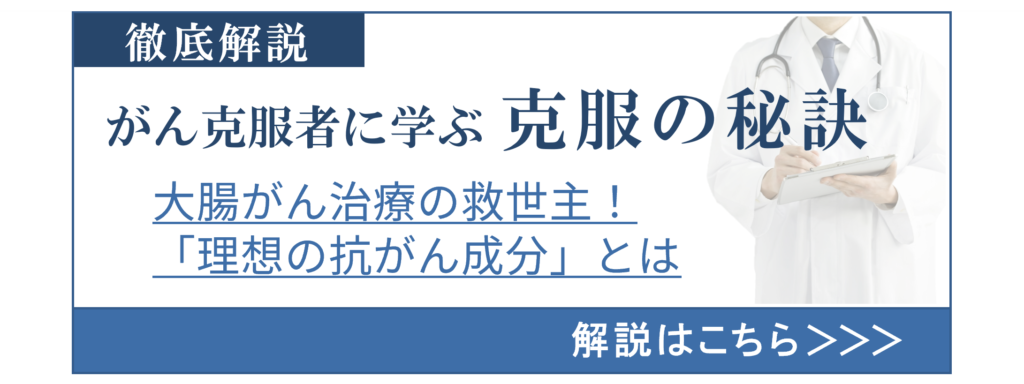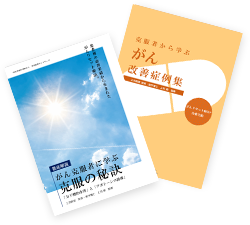- 2025.09.05
- 大腸がん
大腸がんステージ4の克服を目指す治療とは?
大腸がん、特に「ステージ4」と聞くと、多くの方が大きな不安を感じるかもしれません。
ステージ4とは、がんが大腸の壁を超えて、腸の付近のリンパ節だけでなく、肝臓や肺といった遠く離れた臓器にまで転移した状態を指します。
この状態は、以前は「手の施しようがない」と考えられていたこともありました。しかし、医学は日々進歩しています。現在ではステージ4と診断されたとしても、適切な治療を組み合わせることによって、がんと共存しながら、希望を持って日常生活を送ることができる道が開かれています。
「もう手術はできないのではないか」「どんな治療があるのか」「副作用はつらいのか」など、様々な疑問や不安を抱えている方もいらっしゃるでしょう。大切なのは、ご自身の病気について正しく理解し、どのような選択肢があるのかを知ることです。
このコラムでは、日本で現在主流となっている「標準治療」を中心に、その種類や治療の流れについて詳しく解説します。抗がん剤治療(化学療法)の役割や、緩和ケアの重要性についても触れていきます。
また、患者さん一人ひとりの状態や年齢、がんと共にどのように生きていきたいかという考え方によって、最適な治療方針は変わってきます。医師や医療チームとどのように向き合い、ご自身にとって最善の方法を見つけて、前向きに病気と向き合っていきましょう。
【最新情報】研究を重ねた結果、がんのタイプを選ばず勢いを抑える「大腸がん克服に必要な成分」を特定しました。
1.大腸がんとはどんな病気?
大腸がんは、大腸の粘膜に発生する悪性の腫瘍です。大腸は、口から食べたものが最後に通る腸管で、大きく分けて結腸と直腸からなります。
大腸がんは日本人に非常に多いがんの一つであり、近年では食生活の欧米化など、生活習慣の変化に伴い、患者数が特に増えている傾向にあります。
大腸がんの大きな特徴の一つは、早期には自覚症状がほとんどないことです。そのため、「最近お腹の調子が悪い」「便に血が混じっている」といった症状が現れたときには、すでにがんが進行しているケースも少なくありません。
ご自身やご家族の健康を守るためには、症状がないうちから定期的な健康診断や、便潜血検査を受けることが非常に重要です。
大腸がんは、進行の度合いによって「ステージ0」から「ステージ4」までの5段階に分類されます。
これは、がんが大腸の壁にどの程度深く達しているか(深達度)や、リンパ節や他の臓器に転移しているかによって決まります。例えば、大腸の壁は「粘膜層」「粘膜下層」「固有筋層」「漿膜(しょうまく)」といった層で構成されており、がんが粘膜内にとどまっている段階であれば、治療の負担も比較的少なく済みます。
一方で、がんが大腸の壁を貫いて外側の周囲に浸潤し、リンパ節や他の臓器、腹膜などに転移すると、治療はより複雑になります。
特にステージ4では、肝臓や肺などへの遠隔転移が確認されるため、治療方針は慎重に検討されることになります。
大腸がんのステージ分類とそれぞれの治療法
大腸がんの治療方法は、がんの進行度合いであるステージによって大きく異なります。
ここでは、それぞれのステージに応じた治療の考え方をご紹介します。
ステージ0・1
がんが大腸の粘膜内にとどまっている「ステージ0」、あるいは粘膜下層までにとどまっている「ステージ1」の段階では、大腸内視鏡を使った切除が第一選択肢となることが多く、多くの場合、外科手術をすることなく治療が完了します。
大腸内視鏡検査の際にがんが見つかれば、内視鏡の先端から小さな器具を挿入し、ポリープのようにがんを切除する方法が一般的です。
これは身体への負担が少なく、比較的短時間で済みます。
ステージ2・3
がんが固有筋層まで達している、あるいは大腸の壁を超えて漿膜にまで及んでいる「ステージ2」や、リンパ節への転移が認められる「ステージ3」の場合、手術によってがんを取り除くことが治療の基本となります。
手術の方法には、お腹を大きく開ける開腹手術と、小さな穴をいくつか開けて行う腹腔鏡手術があります。腹腔鏡を使った手術は、患者さんの身体への負担が少なく、術後の回復が早いという利点があります。
手術でがんを切除した後は、抗がん剤を用いた補助化学療法を行うことで、目に見えないがん細胞をたたく治療が検討されます。これにより、再発を予防する効果が期待できます。
ステージ4
がんが肝臓や肺といった他の臓器へ転移している「ステージ4」の場合、治療はより複雑になります。
しかし、決して治療をあきらめるわけではありません。近年の医療の進歩により、手術、化学療法、放射線治療、免疫チェックポイント阻害薬など、様々な治療法を組み合わせることで、がんと共存しながら生活の質を保つことが可能になってきました。
転移したがんが手術で切除可能な一部に限られている場合は、手術が優先されることもあります。
手術で取りきれない場合は、抗がん剤による薬物療法が中心となります。
化学療法は、がん細胞の増殖を抑える目的で行われ、最近では、患者さんのがんの遺伝子を調べて最適な治療薬を選ぶ個別化医療も進んでいます。
このように、大腸がんは、進行度や患者さん一人ひとりの状態によって、最適な治療法が大きく異なります。
まずはご自身の病状をしっかりと理解し、医師や医療チームと相談しながら、最適な治療方針を見つけていくことが大切です。
2.大腸がんの検査と診断
早期発見ができれば、大腸がんの治療の選択肢は広がり、体への負担も少なくなる可能性が高まります。
しかし、初期の段階では自覚症状がほとんどないことが一般的です。そのため、「自分は大丈夫」と思わずに積極的に検査を受けることが大切です。
ここでは、大腸がんを見つけるための代表的な検査と、診断の流れについて詳しく説明します。
大腸がんを見つける検査
大腸がんを見つけるための最初の検査としては、多くの自治体や企業で推奨されている「便潜血検査」です。
これは、ごくわずかな血液が大便に混じっていないかを調べる検査で、ご自宅で手軽に行えます。
仮に陽性という結果が出たとしても、必ずしも大腸がんというわけではありません。痔などの他の病気でも陽性になることがあるため、心配しすぎないことが重要です。
しかし、この結果は「精密検査が必要」という体からのサインです。
便潜血検査で陽性だった場合、あるいは腹痛や血便などの症状がある場合に最も重要な検査が「大腸内視鏡検査」です。
この検査では、肛門から細い管状のカメラを挿入し、大腸の粘膜を直接観察します。
検査中にポリープや病変が見つかった場合は、その場で特殊な電流を使い、がん化する可能性のあるポリープを切除することができます。
また、組織の一部を採取(生検)することも可能です。
採取した組織は病理検査に回され、顕微鏡で詳しく調べられます。これにより、腫瘍が悪性かどうか、がんの型や深さ、そして大腸の壁にどの程度深く達しているか(深達度)などが明確になります。
特に、がんが粘膜下層にとどまっているか、それより深い固有筋層にまで浸潤しているかは、その後の治療方針を決める上で非常に重要な情報となります。
精密検査
大腸内視鏡検査や生検でがんが確認された後は、がんがどのくらい広がっているかを調べるための精密検査が行われます。
これにはCT検査やMRI検査が一般的です。
これらの検査では、肝臓や肺、骨盤内のリンパ節など、がんが転移しやすい臓器や部位に病変がないかを確認します。
特にステージ4と診断されるケースでは、がんが腹腔内に播種(種をまいたように広がる状態)していないか、あるいは脳などの遠く離れた臓器に転移していないかなど、より詳細な検査が必要になる場合があります。
また、最近の医療では、がんの遺伝子を調べる「遺伝子検査」も重要視されています。
これによって、がん細胞の特性や、特定の治療薬が効きやすいかどうかがわかります。これらの情報を総合的に評価することで、その方に最も効果的な個別化治療を検討できるようになります。
診断が確定し、ステージが分かったら、いよいよ具体的な治療方針を医師と話し合います。
このとき、手術が可能かどうか、どの部分を切除するか、抗がん剤治療や放射線治療を組み合わせるかなど、さまざまな選択肢が提示されます。
不安なことや疑問に思うことは、どんなに些細なことでも遠慮せずに尋ねましょう。医師や看護師、薬剤師などの医療チームは、患者さんが安心して治療に臨めるよう、精一杯サポートしてくれます。
ご自身の体の状態や気持ちを正直に伝えることが、最善の治療につながる第一歩となります。
3.大腸がんステージ4の治療
大腸がんは、たとえステージ4と診断されても、決して「もう治療の選択肢はない」というわけではありません。
医療の進歩はめざましく、現在では様々な治療法を組み合わせて、がんと共存しながら前向きに生活を送ることが可能になっています。
ステージ4とは、がんが大腸の壁を超え、離れた臓器に転移している状態を指します。
この章では、進行がんである大腸がんステージ4の主な治療法について、それぞれの役割や目的を詳しく解説していきます。
大腸がんステージ4の治療方針
大腸がんステージ4の治療方針は、大きく分けて二つに分かれます。
一つは、「根治(治癒)」を目指す治療です。
これは、がんが転移した肝臓や肺など、特定の部分にとどまっており、外科手術でがんを完全に取りきれる可能性がある場合に選択されます。
もう一つは、「がんと共存する治療」です。
がんが複数の臓器に広く転移しており、手術で取りきることが不能な場合に選択されます。
この場合、治療の目的は「症状を抑え、生活の質(QOL)を保ちながら、がんの進行を抑える」ことになります。
どちらの治療方針を選択するかは、がんの広がりや患者さんの年齢、全身状態、他の病気の有無など、様々な条件を総合的に検討し、医療チームと話し合いながら決めることになります。
ステージ4大腸がんの外科手術
転移が見られるステージ4でも、外科手術は非常に重要な役割を果たします。
特に、転移巣が肝臓や肺などに限局しており、切除が可能と判断された場合には、手術によって原発巣(元々あった大腸のがん)と転移巣の両方を切除し、根治を目指すことがあります。
手術は、がんの種類や場所、患者の体力などを考慮し、開腹手術か腹腔鏡手術が選択されます。
腹腔鏡手術は、お腹に小さな穴をいくつかあけて行うため、患者の身体への負担が少なく、術後の回復が早いという利点があります。
手術のタイミングも重要です。一度に大腸と転移巣を同時切除するケースもあれば、先に抗がん剤治療(化学療法)を行い、がんを小さくしてから手術を行う方法もあります。この「術前補助化学療法」は、一般的に「ネオアジュバント療法」とも呼ばれ、残存する腫瘍を減らして、より安全に手術を行うことを目的としています。
また、直腸がんの場合、がんが肛門に近い部分にできた場合、人工肛門(ストーマ)を造設する必要が出てくることもあります。
しかし、最近では括約筋を温存する手術も一部の施設で施行されており、患者の生活の質を保つための努力がなされています。
日本では、主に大腸癌研究会によって治療のガイドラインが作成されており、国立がん研究センターなどの専門機関が協力しています。このガイドラインに基づいて、多くの病院やクリニックで質の高い治療が提供されています。
ステージ4大腸がんの化学療法
化学療法(抗がん剤治療)は、ステージ4の大腸がん治療の中心となる治療法です。その主な目的は、薬剤を用いて全身に広がったがん細胞の増殖を抑えて、病気の進行をコントロールすることにあります。
従来の抗がん剤に加え、がん細胞特有の分子を狙う「分子標的薬」や、患者自身の免疫の力を利用してがんを攻撃する「免疫チェックポイント阻害薬」など、新しい治療薬も次々と開発されています。
治療薬の選択は、がんの遺伝子変異の有無や患者の状態によって慎重に決められます。遺伝子を調べることで、その方に最も効果の高い治療薬を見つけることができ、不要な副作用を避けることにもつながります。
化学療法には吐き気や脱毛、倦怠感などの副作用がつきものですが、現在はこれらの副作用を軽減する薬も進歩しており、生活の質を保ちながら治療を続けることが可能です。治療中は、医師や看護師にこまめに相談し、身体や心の変化を伝えていくことが大切です。
ステージ4大腸がんの放射線療法
放射線治療は、転移巣や原発巣による局所的な症状を和らげる目的で用いられることが多い治療法です。
例えば、がんが大きくなり、痛みや出血といった症状が出ている場合、その部分に高周波の電流を注入する治療などを施し、放射線をピンポイントで照射することで、腫瘍を小さくし、症状を緩和する効果が期待できます。
放射線治療は、基本的に外から放射線を当てる方法が一般的です。ただ、骨盤内の直腸がんなどの特定の部位には、体の内側から放射線を当てる方法が選択されることもあります。これにより正常な臓器への影響を最小限に抑えつつ、効果的にがんを叩くことが可能になります。
緩和ケアも治療選択のひとつ
がんの治療は手術や化学療法、放射線治療だけではありません。「緩和ケア」も、がん治療において非常に重要な役割を担います。
緩和ケアとは、がんの進行度を問わず、患者の身体的な苦痛(痛み、吐き気など)や精神的な苦痛(不安、うつなど)を和らげ、自分らしい生活を続けるためのサポートです。
特にステージ4の大腸がんでは、がんとの付き合いが長期にわたることが多いため、治療と並行して緩和ケアを導入することが強く推奨されています。
緩和ケアチームには、医師や看護師だけでなく、薬剤師、管理栄養士、ソーシャルワーカーなど、様々な専門家が入れ、患者を注意して見守ります。
例えば、治療薬の副作用が強く出た際には、その症状を和らげる薬を調整したり、食事が十分に取れない問題がある時には、栄養を補給する方法を考えたりと、患者一人ひとりの状況に合わせて、きめ細かなサポートを提供します。
こうした多面的な支えがあることで、患者は治療へのモチベーションを保ちやすくなり、より良い生活を送りながら、治療を継続していくことができるのです。
4.よりよい生活のために
かつては治療が難しいとされてきたステージ4のがんですが、医療は数十年の間に大きく進歩しています。
今では、手術や化学療法だけでなく、免疫療法や分子標的薬といった新しい治療法も登場し、治療の選択肢が格段に広がっています。がんの原発巣や転移した場所、そして患者さんご自身の状態によっては、外科的にがんをすべて切除できる可能性も残されています。
このコラムで解説したように、治療のタイミングを逃さず、専門の医療機関で適切な検査と治療を受けること、そして痛みや不安を我慢せず、医師や看護師といった医療スタッフにこまめに相談することが、生活の質を守る上で非常に重要となります。
また、治療だけでなく、緩和ケアの活用や、栄養管理、適度な運動といった日々の生活習慣の見直しも、長期的な体力維持や再発予防につながります。
ぜひ主治医や医療スタッフに積極的に相談し、あなたの病状や気持ちに合った治療方針を一緒に見つけていってください。
ご自身が納得できる形で治療を進めることが、厳しい闘病生活の中でも前向きな気持ちを保ち、より良い未来を切り拓く力となります。
ステージ4という診断であっても、決して孤立せず、がんと共に生きる道を歩んでいきましょう。
※この記事は2025年2月21日に作成され、2025年9月5日に内容を更新しました。

快適医療ネットワーク理事長
監修
医学博士 上羽 毅
金沢医科大学卒業後、京都府立医科大学で研究医として中枢神経薬理学と消化器内科学を研究。特に消化器内科学では消化器系癌の早期発見に最も重要な内視鏡を用いた研究(臨床)を専攻。その後、済生会京都府病院の内科医長を経て、1995年に医院を開業。
統合医療に関する幅広し知識と経験を活かして、がんと闘う皆様のお手伝いが出来ればと、当法人で「がん患者様の電話相談」を行っております。